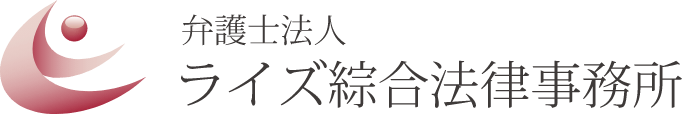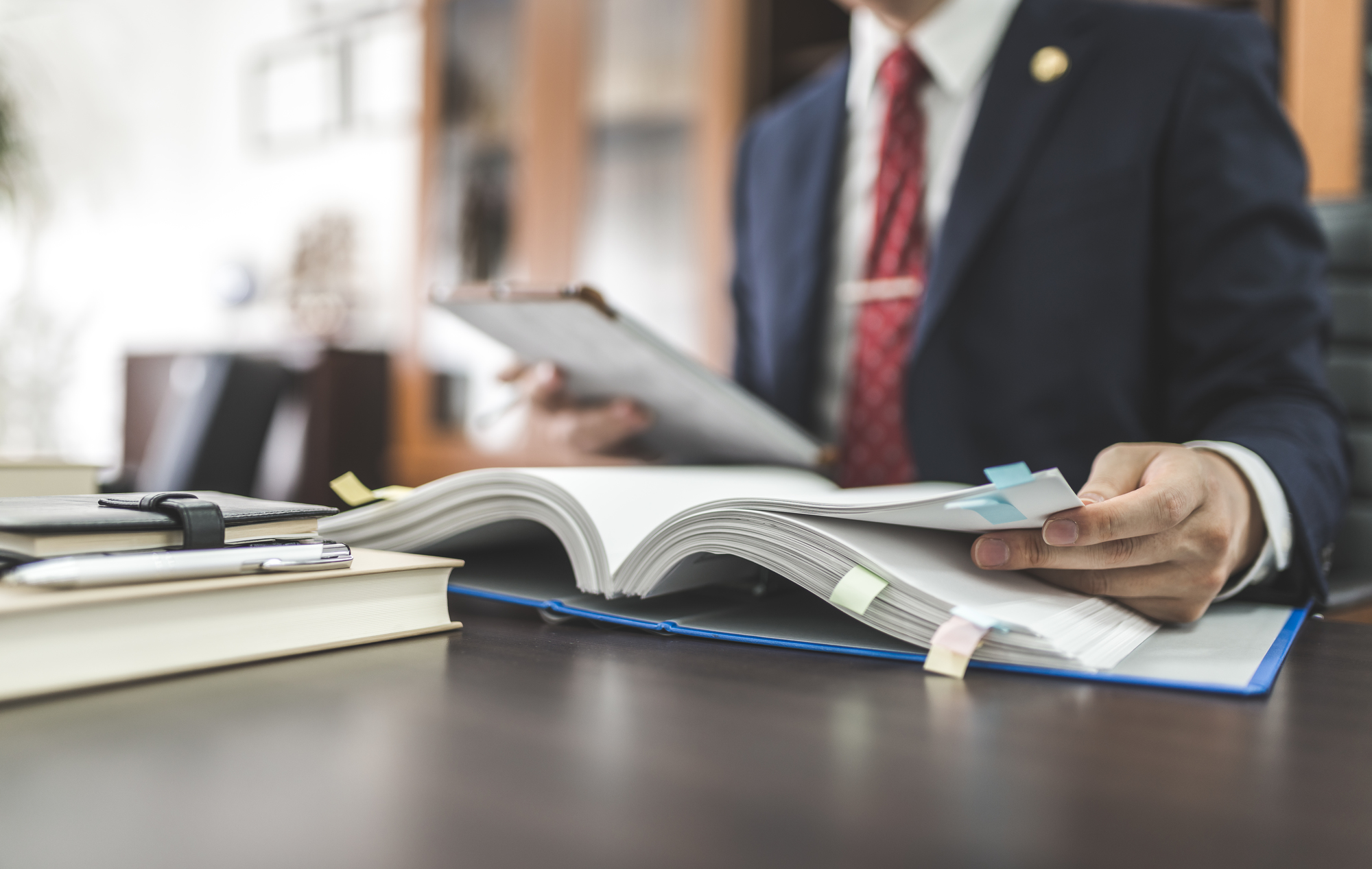
1.慰謝料とは何か
慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償です。不貞行為に対する慰謝料の請求は、民法709条・710条の不法行為に基づく損害賠償請求の一種です。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
※引用:民法|e-Gov法令検索
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
※引用:民法|e-Gov法令検索
配偶者の不倫で離婚に至ったケースや、精神的なダメージを受けた場合は慰謝料を請求することができます。
1-1 離婚慰謝料
離婚に伴い、さまざまな要因で慰謝料が発生することがあります。離婚慰謝料は、「離婚原因慰謝料」「離婚自体慰謝料」の2種類に大別できます。
| 離婚原因慰謝料 | 離婚の原因となった行為の精神的苦痛に対する慰謝料 |
|---|---|
| 離婚自体慰謝料 | 離婚せざるを得なくなったことによる精神的苦痛に対する慰謝料 |
離婚原因慰謝料の「離婚の原因となった行為」としては、配偶者への不倫やDV、モラハラなどが代表的です。
このように分類はありますが、実際の訴訟や話し合いでは、離婚するかどうかや不倫などはあくまで金額を決定するための要素として扱われます。そのため、請求する際はまとめて1つの離婚慰謝料となります。
2.不倫・浮気相手に慰謝料請求できる条件

不貞行為に対する慰謝料請求は、どのような場合でも認められるわけではありません。では、どういったケースで請求できるのか、詳しく見てみましょう。
2-1 離婚で慰謝料請求できる場合
配偶者や不倫・浮気相手に対して慰謝料を請求できるのは、不倫・浮気相手と配偶者が性的な関係にあり(または、性行為そのものでなくてもこれに匹敵する行為があり)、かつ次の条件に当てはまる場合です。
- 配偶者が既婚者であることを不倫・浮気相手が知っていた
- 既婚者だと容易に推測できる状況だった
- 夫婦関係が破綻していないと容易に推測できた
- 不倫によって円満だった夫婦関係が悪化した
まとめると、夫婦関係の継続を知っていた(または、知らなかったが容易に推測できた)状況で、不倫で夫婦関係が悪化した場合に請求の対象となります。
3.慰謝料請求できる場合の具体的な離婚理由
実は、不倫・浮気以外にも、離婚に伴い慰謝料を請求できることがあります。では、どのような理由で離婚する場合に慰謝料の請求が可能なのか具体例を見てみましょう。
3-1 不貞行為があった
配偶者に不貞行為があった場合、慰謝料の請求が可能です。
不貞行為とは、法律用語でのいわゆる「浮気・不倫」のことです。配偶者以外との性行為の存在や、それに匹敵する関係を持っている事実を証明できれば、慰謝料請求の対象となります。
原則的には「手を繋いだ」「キスをしていた」「親密にやりとりしていた」というだけでは、法律上の不貞行為には該当しません。
ただし一部の裁判例では、「既婚男女の交際として社会的に妥当な範囲を逸脱している」と認定され、慰謝料の請求が認められたものもあります。判断が難しい場合は、弁護士に相談して見解を聞いてみることをおすすめします。
3-2 悪意の遺棄があった
配偶者から明確に悪意の遺棄があった場合も、慰謝料を請求することが可能です。
「悪意の遺棄」とは、法律用語で「婚姻生活が破綻することを分かっていながら、夫婦の相互扶助の義務を一方的に放棄すること」を指します。
民法では、夫婦には「同居の義務」「協力義務」「扶助の義務」があります。悪意の遺棄に該当するのは、正当な理由なくこれらの果たすべき義務を怠った場合です。以下のようなものが代表的です。
- 配偶者を放置して勝手に別居したり一方的に家出したりする
- 同居している家から配偶者を追い出す
- 不倫・浮気相手の家に入りびたって戻らない
- 収入があるにもかかわらず配偶者に生活費を渡さない
- 家事育児を放棄している
- 病気の配偶者の世話をしない
これらは、いずれも婚姻関係を破綻させる要因です。夫婦が離婚に至れば、原因を作った配偶者に対して慰謝料を請求できます。
3-3 DV・モラハラによる怪我や精神的苦痛があった

DVやモラハラを受けていたケースも、慰謝料請求の対象になります。
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者から他方に対する身体的・精神的暴力のことです。日常的に暴行を加えられている他、相手の意思を無視して性行為を行うことも、性的暴力としてDVに含まれます。
一方、モラハラ(モラルハラスメント)は、言葉や態度による精神的暴力のことです。配偶者の人格を否定したり、友人や肉親を侮辱したり、さまざまな方法で配偶者を攻撃します。
DVやモラハラが常態化しており、それが原因で婚姻関係が破綻すると、加害側の配偶者に対して慰謝料請求できます。
3-4 婚姻を継続し難い重大な原因があった
民法では、前述の理由の他「婚姻を継続し難い重大な事由がある時」にも、離婚を認めています(民法第770条1項5号)。性格の不一致による離婚などは、ここに該当します。
この場合も、離婚に至った要因によっては慰謝料の請求が可能です。離婚トラブルの現場で散見されるのは、以下のような例です。
- 健康上の理由もないのに一方的に性交渉を拒否されている
- 相手の親などの肉親から肉体的または精神的に虐待を受けた
- アルコール中毒で生活に支障をきたしている
- 配偶者がギャンブル依存症で借金があり、生活費が足りない
このように、明らかにどちらかの配偶者が重大な離婚の原因を作った場合、慰謝料を請求できます。
4.離婚で慰謝料請求できない場合
次の条件に該当する場合、離婚による慰謝料は請求できません。
- 不法行為を証明する証拠がない
- 離婚原因が性格の不一致や価値観の相違
- 既婚者であることを知らず、知らないことに過失がない状況で性的な関係を持った
- 性行為が脅迫や強制性交など自由意志によるものではない
- 不倫が始まる前に既に夫婦関係が破綻している
- 既に十分な金額の慰謝料を受け取っている
- 時効を迎えている
離婚に至った責任が明確にどちらにあるといえない場合は、慰謝料を請求することはできません。また不倫が原因の離婚であっても、精神的苦痛を与えたことに対して不倫・浮気相手に落ち度がない場合や、夫婦関係が既に破綻していて損害がないケースは、慰謝料請求の対象とはなりません。
5.不倫・浮気されたときの慰謝料の相場

慰謝料請求を検討する上で重要なのが、具体的に「いくら請求できるか」です。相場を詳しく解説します。
5-1 一般的な慰謝料の相場
不倫による慰謝料の金額にはかなりの幅がありますが、あえて相場を提示すると「数十万円〜300万円程度」となります。
慰謝料の請求に関しては、法律で基準や計算方法が定められているわけではありません。実際の算定にあたっては、不倫の内容や受けた損害を精査し、妥当な金額を導き出します。
慰謝料ではなく、離婚時の財産分与を多めに受け取ることや、解決金という名目で合意に至ることもあるため、ケースバイケースといえます。
なお、当事者間で合意があれば、慰謝料は分割払いにすることも可能です。ただし、途中で支払いが止まることも十分に考えられます。そのため、公正証書を作成する、保証人を用意してもらうなどの工夫が必要です。
5-2 慰謝料の金額と精神的苦痛を判定する要素
前述の通り、慰謝料の金額は個別の状況によって異なります。請求金額の根拠となる、精神的苦痛の程度を測る要素としては、次のものが基準となります。
- 婚姻期間の長さ
- 不貞行為の期間の長さ
- 不貞行為の前後における夫婦関係の変化
- 夫婦関係の破綻に至った経緯
- 不貞行為による家族関係の変化
- 子どもの有無・人数
では、上記をふまえると、どういったケースで増額または減額されるのでしょうか。
5-2-1 慰謝料が増額される場合
不貞行為によって受けた精神的苦痛の度合いが大きいと判断されると、慰謝料の増額要因となります。例えば次のようなケースは、慰謝料が高くなりやすいです。
- 婚姻期間が長い
- 不倫によって離婚や別居に至った
- 不倫の期間が長い
- 不倫・浮気相手と頻繁に会っていた
- 不倫が明らかな状況で事実を否認し続けた
- 一度解消した不倫関係を復活させた
- 不倫・浮気相手との間に子どもがいる(妊娠している)
- 配偶者の不貞行為によって精神疾患を発症した
- 夫婦の間に未成年の子どもがいる
- 子どもの人数が多い
長期間にわたり夫婦として暮らしていたものの、その一方で不倫・浮気相手との関係を長期にわたり平行して継続していた場合などは、高額な慰謝料になる可能性があります。
5-2-2 慰謝料が減額される場合
一方で、精神的苦痛が少ないと判断されると、それほど高額な慰謝料を請求できないこともあります。例えば、次のようなケースでは減額される傾向にあります。
- 婚姻期間が短い
- 不貞行為の発覚後も離婚していない
- 不貞行為の期間が短い
- 配偶者と不倫・浮気相手が会っていた頻度が少ない
- 不倫関係をすぐに解消しようとしていた
- 配偶者が不倫・浮気相手に夫婦関係の破綻を告げていた
- 夫婦の間に子どもがいない
- 不貞行為に及ぶ前から夫婦関係が悪かった
- 職場に知られるなどすでに社会的制裁を受けている
仮に、婚姻期間の短い配偶者がマッチングアプリで一度だけ相手と関係した場合などは、慰謝料は少額に留まる可能性があります。
6.慰謝料請求の方法と手続きの流れ
では、実際に慰謝料を請求する際はどのような方法があり、どういった流れで進むのでしょうか。詳細を解説します。
6-1 慰謝料の請求書を送付する
多くのケースでまず行うのが、慰謝料請求の事実と金額を記載した請求書の送付です。慰謝料の請求書を送付する方法は郵送が一般的ですが、FAXで送るケースもあります。
慰謝料の請求書をはじめ、法的文書の送付方法としてよく用いられるのが普通郵便や内容証明郵便です。内容証明とは、一般書留に付けられるオプションサービスの一種で、郵便局で送付書類の複製を保管してくれます。
これにより「誰に、いつ、どのような内容の書類が発送されたか」を証明できます。また、書留で配達されると受け取りの記録が残ることから、相手方の「届いていない」という主張を封じることが可能です。
何も連絡がない場合は、電話や普通郵便で再度送付して督促を行います。
6-2 話し合いによる交渉を行う
慰謝料の請求書を送付しても慰謝料が支払われない場合や、相手方から支払い条件などに関する連絡があった場合は、話し合いで交渉を行います。話し合いは面談や電話などで行い、合意に至ったらその内容を示談書にまとめましょう。
なお、相手方の態度に不安を感じるケースなどでは、書面を公正証書にすることもあります。これにより、書面の効力や、強制されて同意したものではないことなどを、第三者(公証人)に証明してもらえます。
6-3 裁判所で法的手続きを行う

話し合いで協議がまとまらないケースでは、裁判所に調停または訴訟を申し立てて、慰謝料を請求することができます。
6-3-1 配偶者に請求する場合
配偶者に慰謝料を請求するケースでは「離婚する場合」「離婚しない場合」「離婚後に請求する場合」で、それぞれ手続きが異なります。
いずれの場合も最初は話し合いによる解決を図りますが、まとまらない場合は調停や訴訟に移行するのが通例です。
【離婚する場合】
家庭裁判所の「夫婦関係調整調停(離婚) 」を利用できます。調停とは、第三者の調停員が間に入って行う、裁判所での話し合いのことです。調停がまとまらない場合、調停は不成立となり、家庭裁判所の離婚訴訟に移行します。
【離婚しない場合】
簡易裁判所の民事調停を利用できます。調停を利用しない場合や、話し合いがまとまらない場合は、簡易裁判所または地方裁判所の慰謝料請求訴訟を提起します。
【離婚後に請求する場合】
家庭裁判所で調停を行う場合と、簡易裁判所や地方裁判所で訴訟を起こす場合があります。
6-3-2 不倫・浮気相手に請求する場合
不倫・浮気相手に請求する場合、まずは話し合いによる解決を図ります。まとまらない場合、調停や訴訟による手続きを行います。
不倫・浮気相手に対する慰謝料請求の調停は、一般の民事調停です。不倫・浮気相手の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。ただし、不倫の慰謝料請求では、調停は行わず訴訟を提起することがほとんどです。
手続きの結果、条件への同意や和解に至る、または慰謝料の支払いを命じる判決が出たら、不倫・浮気相手からの慰謝料の支払いに繋げることができます。
7.離婚での慰謝料請求に関する注意点
離婚で慰謝料を請求する際はいくつか押さえておきたい注意点があります。「慰謝料請求には時効があること」「求償権に注意する」「ダブル不倫の末離婚する場合は相手方から慰謝料を請求されることがある」以上の3点を詳しく見てみましょう。
7-1 時効が成立すると慰謝料請求ができない

慰謝料請求の権利には消滅時効が存在します。不倫の慰謝料請求の時効は「不貞行為の事実と不倫・浮気相手を知った時点から3年」または「不貞行為があった時から20年」が経過すると成立します。
不倫を知ってからも、いわゆる仮面夫婦状態で放置してしまうケースもあるのですが、時効を考慮するとおすすめできません。そのため、知った時点で早めに動く必要があります。
時効成立まであまり時間がない場合は、内容証明郵便の送付や、訴訟の提起によって、時効の完成猶予をさせることもできます。
7-2 不倫・浮気相手から「求償権」を行使される可能性がある
慰謝料を支払った不倫・浮気相手から、配偶者に対して求償権が行使されることがあります。
不倫による慰謝料の請求先は選ぶことができます。考えられるのは「配偶者のみ」「配偶者と不倫・浮気相手」「不倫・浮気相手のみ」の3つのパターンです。
慰謝料を支払う責任は、配偶者と不倫・浮気相手が連帯して負うものであり、上記のどのパターンでも全額を請求可能です。ただし、どちらか一方のみが全額慰謝料を支払った場合、支払った側はもう一方に対して肩代わりした分を請求できます。この権利を求償権と呼びます。
例を挙げてみましょう。Aさんの配偶者BさんがCさんと不倫をしたので、Aさんは慰謝料200万円を請求します。Aさんは、Cさんにのみ200万円を満額請求し、Cさんは支払いに応じました。この場合、Cさんは、慰謝料の連帯債務者であるBさんに求償権を行使し、200万円のうちBさんの負担分を払うよう請求できます。ここで、BさんとCさんの負担割合を1:1とすれば、Cさんは、Bさんに対して、求償権の行使として、100万円を支払うように求める権利があります。
不倫した配偶者と離婚しない場合、受け取った慰謝料のうち、配偶者の負担分を家計から出さざるを得ないケースもあります。結果として相殺がなされたのと同様の状態になることもあるため、求償についても話し合い、トラブルにならないよう、例えば、不倫・浮気相手には,慰謝料の支払いがなされた後、不倫をした配偶者に対する求償権の行使をしないように合意を求める必要があります。
7-3 ダブル不倫の場合は不倫・浮気相手の配偶者からも慰謝料請求される可能性がある
注意しなければならないのが、自分の配偶者と不倫・浮気相手がどちらも既婚者だった、いわゆる「ダブル不倫」の場合です。このケースでは自分から不倫・浮気相手に慰謝料を請求できますが、不倫・浮気相手の配偶者からも慰謝料を請求される可能性があります。
家庭単位で見れば、自分側と不倫・浮気相手側の双方が慰謝料を請求し合う関係になります。離婚しないのであれば、夫婦の家計が同一だと入ってきた分が出ていくだけなのでメリットがありません。
離婚するのであればあまり関係ないのですが、そうでない場合は注意が必要です。
ダブル不倫の解決策の1つとして、双方の夫婦が離婚しない時は「双方の夫婦がお互いに慰謝料を請求しない」という「四者ゼロ和解」をすることもできます。
8.離婚での慰謝料請求に関するQ&A
離婚での慰謝料請求に関して、当事務所によく寄せられる質問を紹介し、回答していきます。「離婚を検討しているけれど、自分のケースでは慰謝料を請求できるか分からない」という方はぜひ参考にしてください。
8-1 離婚しなくても慰謝料請求できる?
慰謝料請求の条件に「夫婦関係の悪化」とありますが、実は離婚まで至らずとも慰謝料は請求できます。
ただし、離婚しないことで「夫婦関係に与えた影響が小さい」とみなされ、慰謝料の金額が減少する傾向にあります。
8-2 離婚後も慰謝料請求できる?
離婚時に発生した慰謝料は離婚後も請求できます。ただし、次の点にあてはまらないか確認をしておきましょう。
- 離婚時に「慰謝料の支払いはない」旨の取り決めをしていないこと
- 慰謝料請求の消滅時効が成立していないこと
慰謝料請求の時効については「時効が成立すると慰謝料請求が出来ない」の段落を参照してください。
9.離婚の慰謝料請求の交渉をスムーズに進めるポイント
不倫の慰謝料請求は、個人で進めるには限界があり、弁護士のサポートを受けることが望ましいです。請求にあたって事前にいくつか準備しておくと、有利に交渉を進められます。
スムーズに進めるためのポイントを紹介します。
9-1 有利になる証拠を確保する

不倫の慰謝料請求では、証拠なしで不貞行為を認めさせるのは難しい場合が多い傾向です。そのため、交渉までに、請求に有利な証拠を確保しておきましょう。例えば、次のようなものが証拠として活用できます。
- 性行為や性交類似行為の場面を撮影した写真や動画
- ホテルに出入りする動画や写真
- ホテルへの出入りの事実を探偵が証言する報告書
- 性的な関係の存在を示唆するメールやSNSのやりとり
ただし、証拠の内容次第では証明力が弱い場合があります。また、違法な手段で集めた証拠は裁判での証拠能力が否定されることがあり得るため、自己判断は危険です。弁護士と相談の上、有効なものを少しずつ集めていきましょう。
9-2 話し合いで決着する
傾向として、話し合いで決着させたほうが希望に近い金額を受け取りやすいです。訴訟に発展した場合、過去の裁判例に基づいて慰謝料の金額が定まる傾向にあるため、十分な慰謝料を受け取れないことがあります。
話し合いであれば交渉次第で自由に金額を定められるため、まずは話し合いの席を設けてみましょう。
ただし、1人で話し合いを行うと、相手方が連絡を無視したり、不当に低い金額を提示されたりと、不誠実な対応を取られることもあります。個人では交渉が難航する可能性が高いため、弁護士に依頼するのが無難です。
では、具体的にどのような弁護士に依頼すればよいのでしょうか。
9-3 離婚の慰謝料請求に強い弁護士を選ぶ
弁護士にもそれぞれ得意分野があるため、不倫問題では慰謝料請求に強く、実績が豊富な弁護士を選びましょう。慰謝料請求に強い弁護士を選ぶことで、次のようなメリットがあります。
- 本気度を示し相手方にプレッシャーを与えられる
- 証拠集めから示談や裁判までトータルサポートしてくれる
- 弁護士が代理人として全ての交渉を代行してくれる
弁護士に依頼した際の費用相場は次の通りです。
| 相談料 | 5,000円~1万円 (無料の事務所もあり) |
|---|---|
| 着手金 | 20万円~50万円程度 (無料の事務所もあり) |
| 報奨金 | 15万円~20万円+回収額の10%~20%程度 |
10.離婚の慰謝料請求は支払わせるための交渉がカギ!少しでも早く解決するために弁護士に依頼しましょう

離婚の重大な要因である不倫の慰謝料請求では、請求しても「お金がない」「不倫はしていない」などと主張され、取り合ってもらえないことも多いです。相手にプレッシャーを与え、誠意ある対応を促すためにも、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
ライズ綜合法律事務所は、法律相談30万件以上の相談実績を誇る民事専門の法律事務所です。不倫慰謝料請求の専門チームがあり、皆様の問題解決をお手伝いしております。
ADP認定夫婦カウンセラー®の資格を持ったスタッフが在籍していますので、離婚したい場合だけでなく、配偶者と再構築したい場合もご相談頂くことができます。
相談料、着手金は無料です。「とりあえず相談だけ」という方もお気軽にお問い合せください。
このページの監修弁護士
弁護士
三上 陽平(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)
中央大学法学部、及び東京大学法科大学院卒。
2014年弁護士登録。
都内の法律事務所を経て、2015年にライズ綜合法律事務所へ入所。
多くの民事事件解決実績を持つ。第一東京弁護士会所属。