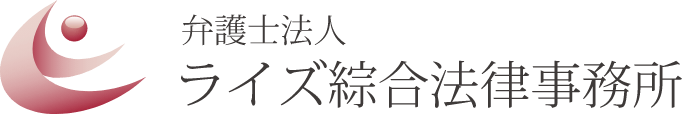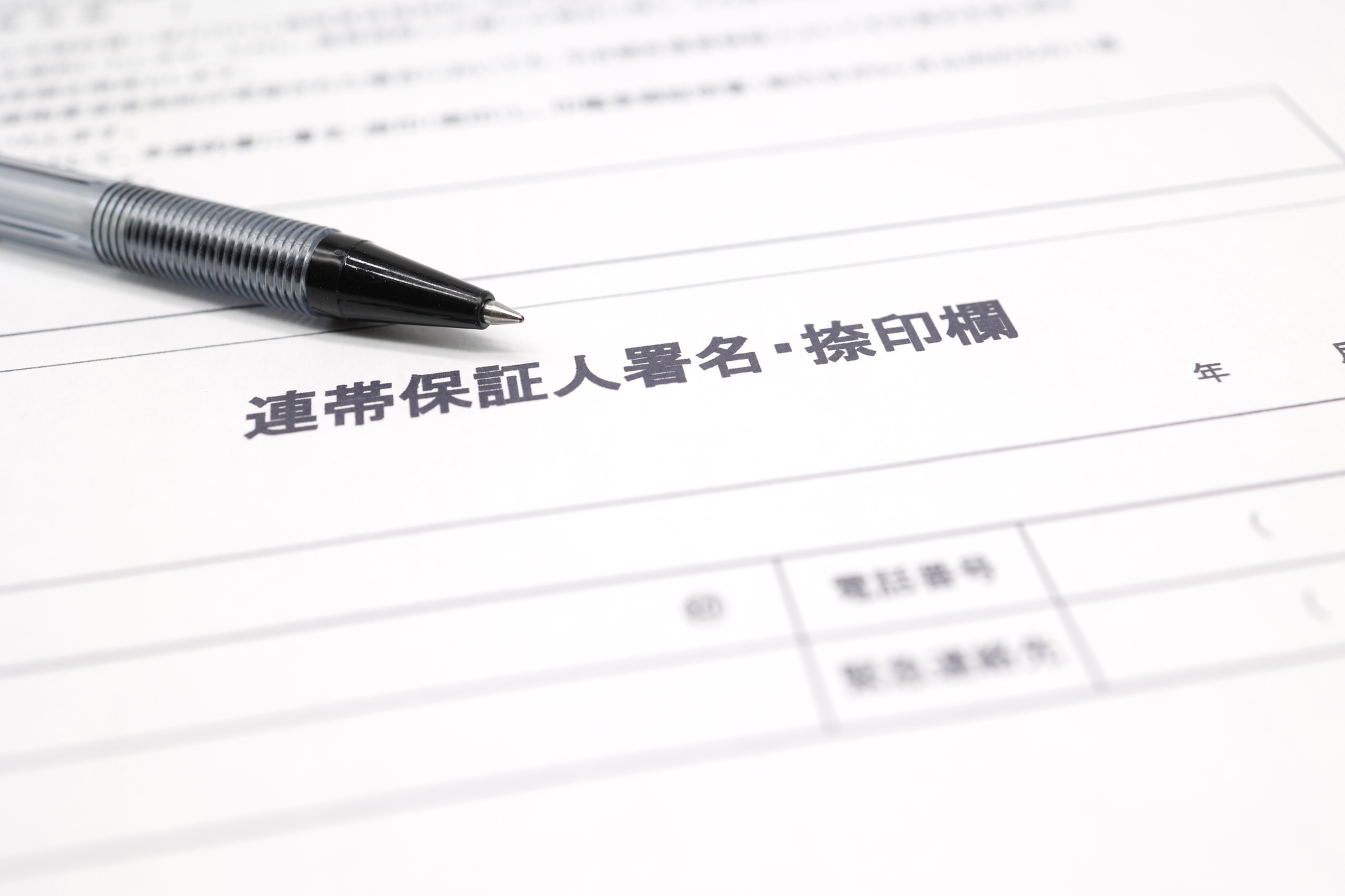
1.連帯保証人の概要
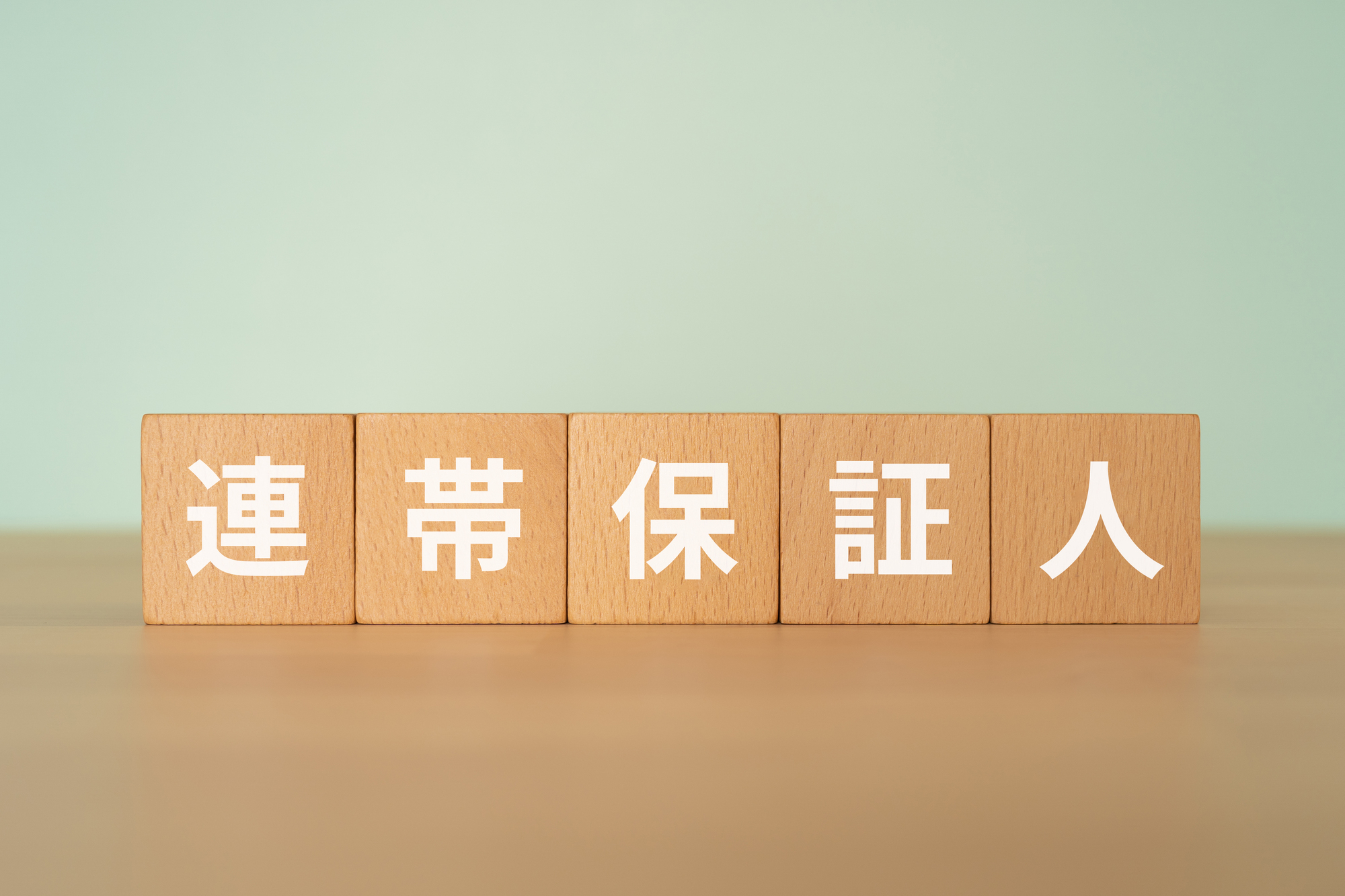
まずは連帯保証人とはどういうものかということを知っておきましょう。
ここでは、連帯保証人の概要について解説します。
1-1 連帯保証人は主債務者と同等の責任を負う
連帯保証人は保証人の一種で、主債務者と同様の返済義務を負います。そのため、通常の保証人よりも債権者に対する責任が重くなります。
住宅ローンの借入、賃貸借契約の締結、借金の返済などの際に、主債務者が何らかの理由で返済できなくなったときのために、連帯保証人をつけてほしいと求められることがあります。
ここで、「保証人」とは債権者との保証契約によって主債務者の代わりに返済義務を負う方のことをいいます。特に、連帯の特約が付いている保証人のことを、「連帯保証人」といいます。
「保証契約」は保証人と債権者の間で締結され、主債務者の合意は必要ありません。また、保証契約は書面で締結しなければ効力は生じません。
なお、連帯の特約がない場合、通常の保証(単純保証)となりますが、借金や賃貸借契約では、ほとんどの場合、連帯保証契約をするのが一般的です。連帯の特約を付けるためには、単に、契約書に「連帯保証人」と記載していれば良いです。また、債務が主債務者の商行為により生じた場合、あるいは保証が商行為である場合も、当然に連帯保証になります。
2.連帯保証人が必要になる主なケース

債権者から連帯保証人を求められるのは、どのようなケースなのでしょうか。具体例を紹介します。
2-1 保証会社と連帯保証人が必須な賃貸物件の契約
連帯保証人を求められる代表的な例の1つが、賃貸物件の契約です。マンションやアパート、戸建てなどの物件を借りる際に、家賃や修繕費などの費用の保証のため、連帯保証人を求められることがあります。
賃貸物件の契約では、連帯保証人を立てるほか、保証会社と契約することも一般的です。どちらが必要かはオーナーの意向によって異なりますが、概ね以下のいずれかになります。
- 連帯保証人だけを立てる
- 保証会社のみで契約できる
- どちらも必須
少数派ですが、UR都市機構など連帯保証人不要の物件も一部存在します。連帯保証人が見つからないときはこちらも検討できるでしょう。
2-2 住宅・自動車などのローン契約
金額の大きな買い物でローンを組む際も、連帯保証人を求められるケースがあります。住宅や自動車などが代表的です。
こうした場合でも必須というわけではありませんが、以下のような状況では連帯保証人を求められることがあります。
- 借入金額が大きい場合
- 収入合算やペアローンで住宅を購入する場合
- ローンを申し込んだ人の経済的信用に不安がある場合
住宅の場合は「収入合算」「ペアローン」などやや特殊な審査・契約方法があり、この場合は連帯保証人が必要です。
| 収入合算 | 配偶者や親の収入を足した金額で審査を受ける方法 収入を合算する相手が連帯保証または連帯債務を負うことが一般的 |
| ペアローン | 同居している配偶者や親などと1つの物件に対し2つの住宅ローン契約を結ぶ方式。2つのローンは債務者同士が連帯保証人になり合う |
2-3 奨学金や教育ローンなどの教育資金
奨学金や教育ローンなども、貸付け金額が大きいことから、連帯保証人を求められます。民間の金融機関でも学資を貸し付けるローンはありますが、ここでは公的な側面が強い「学生支援機構の奨学金」と、「国の教育ローン」を例に挙げて見てみましょう。
| 学生支援機構の奨学金 |
独立行政法人日本学生支援機構が運営する貸付型の奨学金 連帯保証は
のどちらかを選ぶことができる |
| 国の教育ローン |
日本政策金融公庫と沖縄振興開発金融公庫が取り扱う教育ローン 連帯保証は
のどちらかを選ぶことができる |
どちらを申し込む場合でも、主債務者は学生となるため経済的な信用が低く、何らかの形で連帯保証人を用意することが必要です。
3.連帯保証人になれる方・なれない方

連帯保証人は主債務者と同様の返済義務を負うため、債務の返済能力が必要になります。これを踏まえると、連帯保証人になれる方・なれない方は次のようにまとめることができます。
3-1 連帯保証人になれる方
連帯保証人になれるのは、次のような条件に当てはまる方です。
- 主債務者の両親や兄弟などの親族
- 主債務者の知人や仕事上の関係者
- 安定した職業や継続的な収入がある方
- 日本国内に居住し、連絡が取りやすい方
- 不動産など可処分財産がある方
- 連帯保証人になることを承諾している方
- 債権者に本人確認書類、収入証明書、財産証明書などを提出できる方 など
なお、債権者次第では上記の要件を満たしていなくても連帯保証人として認めてもらえる場合があります。
3-2 連帯保証人になれない方
一方で、一般的に以下のような場合は連帯保証人にはなれません。
- 無職または収入が少ない方
- 可処分財産が何も無い方
- 破産者や成年被後見人、未成年
- 債務整理をしている方
- 公的年金収入しかない高齢の方(公的年金は差し押さえできない)
- 海外在住などで連絡が取りづらい方
- 連帯保証人になることを承諾していない方 など
連帯保証人は、経済的な信用が一定以上あり、かつ何かあった際に問題なく支払いが可能かを評価されます。住宅ローンなどでは、誰を連帯保証人にするかも審査に大きく影響します。
4.連帯保証人と保証人の違い
連帯保証人と保証人は、債権者との保証契約によって効力が生じ、保証債務という責任を負う(民法第446条)点が共通しています。保証債務とは、主債務者の債務を保証したとき、保証人が負う債務のことです。その意味で、債権者に対する担保(人的担保)という見方もできます。
また、連帯保証人も保証人も主債務者に代わって返済した場合は、返済した分を主債務者に求償請求することが可能です。これを求償権といいます。
一方で、連帯保証人と保証人は債務返済について負う責任の重さが以下のように異なります。
| 連帯保証人 | 保証人 | |
|---|---|---|
| 債務者としての地位 | ほぼ主債務者と同じ | 万一の際副次的に履行を求められる(補充性) |
| 返済の時期 | 返済を請求されたとき | 主債務者が返済困難になったとき |
| 返済の範囲 | 全額 | 保証人の人数で割った金額(分別の利益) |
| 請求や強制執行への反論 | 主債務者より先に請求されても反論できない | 主債務者の後にするよう要求できる(催告・検索の抗弁権) |
4-1 催告の抗弁権
保証人は金融機関など主債務者に貸したお金の返済を受ける権利を持つ債権者から返済の履行を請求されたときに「まずは主債務者本人に請求してください」と言い、自らの返済を拒否することができます。これを催告の抗弁権といいます(民法第452条)。
保証債務は、主債務者が債務を履行できなくなったときに初めて、履行する義務が生じる二次的な債務だからです(補充性)。
しかし、あらかじめ合意でこの補充性を排除することもでき、連帯保証人には、この催告の抗弁権が認められていません。
従って、債権者は主債務者に返済の履行を督促していなくても、いきなり連帯保証人に対して債務返済の履行を請求することができます。
そのため、連帯保証人は事情を問わず、債務返済の義務を負うことになります。
4-2 検索の抗弁権
保証人は、主債務者が債務を一部でも返済できるだけの資力を有しており、かつ強制執行が容易であることを証明すれば、債権者から返済の履行を請求されたときに「まずは主債務者の財産や給料を差し押さえてほしい」と言い、自らの返済を拒否することができます。
これを検索の抗弁権(民法第453条)といい、主債務者が返済のための十分な資力があるのにもかかわらず返済を履行しない中で保証人に請求がきた場合に主張できます。
連帯保証人には、この検索の抗弁権が認められていません。
例えば、保証人が債権者に対し、「主債務者は〇〇銀行〇〇支店に預金口座を持っており50万円の預金がある」と指摘した場合、これは強制執行が容易な財産と言えますから、債権者は、まずこの預金から取立をしなければなりません。
そして、債権者が保証人の言うとおりに取立をしなかった場合、保証人は、主債務者の財産から得られるはずだった金額について、支払い義務がなくなります。例えば、債権者が50万円の取立の機会を逃して1円も回収できなかった場合は、保証人は、50万円の限度で保証債務も免れることになります。
しかし、連帯保証人には検索の抗弁権がないため、主債務者が財産を持っていたとしても、請求を受ければ全額を支払わなければなりません。
4-3 分別の利益
通常の保証では、1つの債務について保証人が複数いる場合、各保証人は債権者に対して保証人の人数で等分された部分のみ債務を負担することになります。これを分別の利益といいます(民法第456条)。
例えば、500万円の保証債務に対して保証人が5人いる場合、保証人は1人当たり100万円の返済を履行すれば良く、残りの400万円には返済義務を負わなくて良いのです。
連帯保証人には、この分別の利益が認められていません。
従って1つの債務に対して連帯保証人が複数いる場合でも、各連帯保証人は債務の全額について債権者に責任を負うことになります。
なお、連帯保証人の間では各連帯保証人に負担部分が存在するため、連帯保証人の1人が自己の負担額を超えて債務を返済した場合、主債務者だけでなく、ほかの連帯保証人に対して、その分を支払うよう求償請求することもできます(民法第442条、第465条第1項)。
5.連帯保証人が支払いを求められる具体的なケース
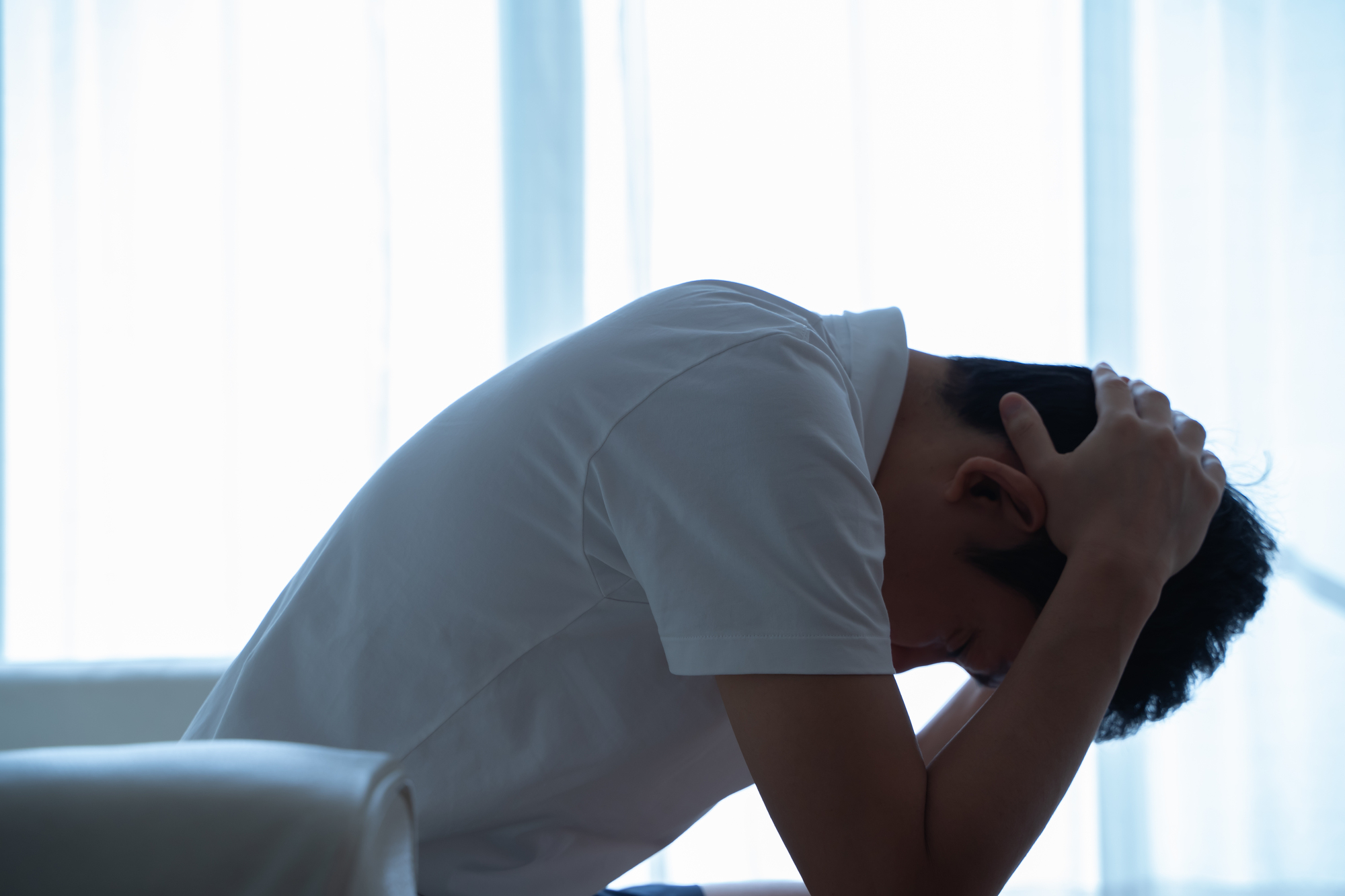
連帯保証人になったとしても、ただちに主債務者の債務を返済しなければならないわけではありません。返済の履行義務が発生するのは、債権者から請求があったときです。
ただし、連帯保証人になった以上は債務に対する責任やリスクが大きくなることも事実です。
ここでは、連帯保証人になることでどのようなリスクや影響があるか解説します。
5-1 ケース1.主債務者が滞納・拒否した
債権者に対して主債務者が債務履行を滞らせると、次は連帯保証人に請求が来ます。
借金の場合、不可抗力をもって抗弁することはできません。つまり、いくらやむを得ない理由があっても債権者の損害賠償請求権は発生します。
一般的には、借金の元本・利息・遅延損害金・違約金の支払い義務を負うことになります。
なお、遅延損害金の額は法定利率に基づきますが、約定利率が法定利率よりも高ければ約定利率に従って支払わなければなりません。
賃貸借契約の場合は契約内容によりますが、家賃の滞納分・主債務者が負担すべき修繕費・原状回復費用となることが一般的です。
5-2 ケース2.主債務者と連絡が取れなくなった
連帯保証契約を締結する際、通常は連帯保証人の連絡先や身元などを明らかにします。
そのため、債権者が主債務者と連絡が取れなくなった場合、確実に連帯保証人のもとに請求が来るといって良いでしょう。
連帯保証人になる以上は、主債務者が蒸発してしまうこともリスクとして捉えておく必要があります。
5-3 ケース3.主債務者が死亡してしまった
連帯保証は、契約書で「主債務者の死亡により本件連帯保証は消滅する」などと明記されていないかぎり、主債務者が死亡しても基本的に継続します。
従って、主債務者が死亡した時点で連帯保証の対象となる借金や家賃支払いがある場合、連帯保証人は債務の履行義務を負うのです。主債務者が死亡した場合、様々な理由で、主債務者の相続人が支払いに応じないことがあります。そのため、連帯保証人が請求を受けることになるわけです。
5-4 ケース4.主債務者が自己破産・民事再生(個人再生)をした
債務者が法的手段または交渉を通じて借金問題を解決する方法を、債務整理といいます。
債務整理には自己破産や民事再生(個人再生)などがあります。
詳細は後述しますが、債務整理が申し立てられた時点で債権者から連帯保証人に請求が来ることが一般的です。
6.主債務者が債務整理のうちの自己破産・民事再生(個人再生)をしたときに連帯保証人に及ぶ影響と対処法
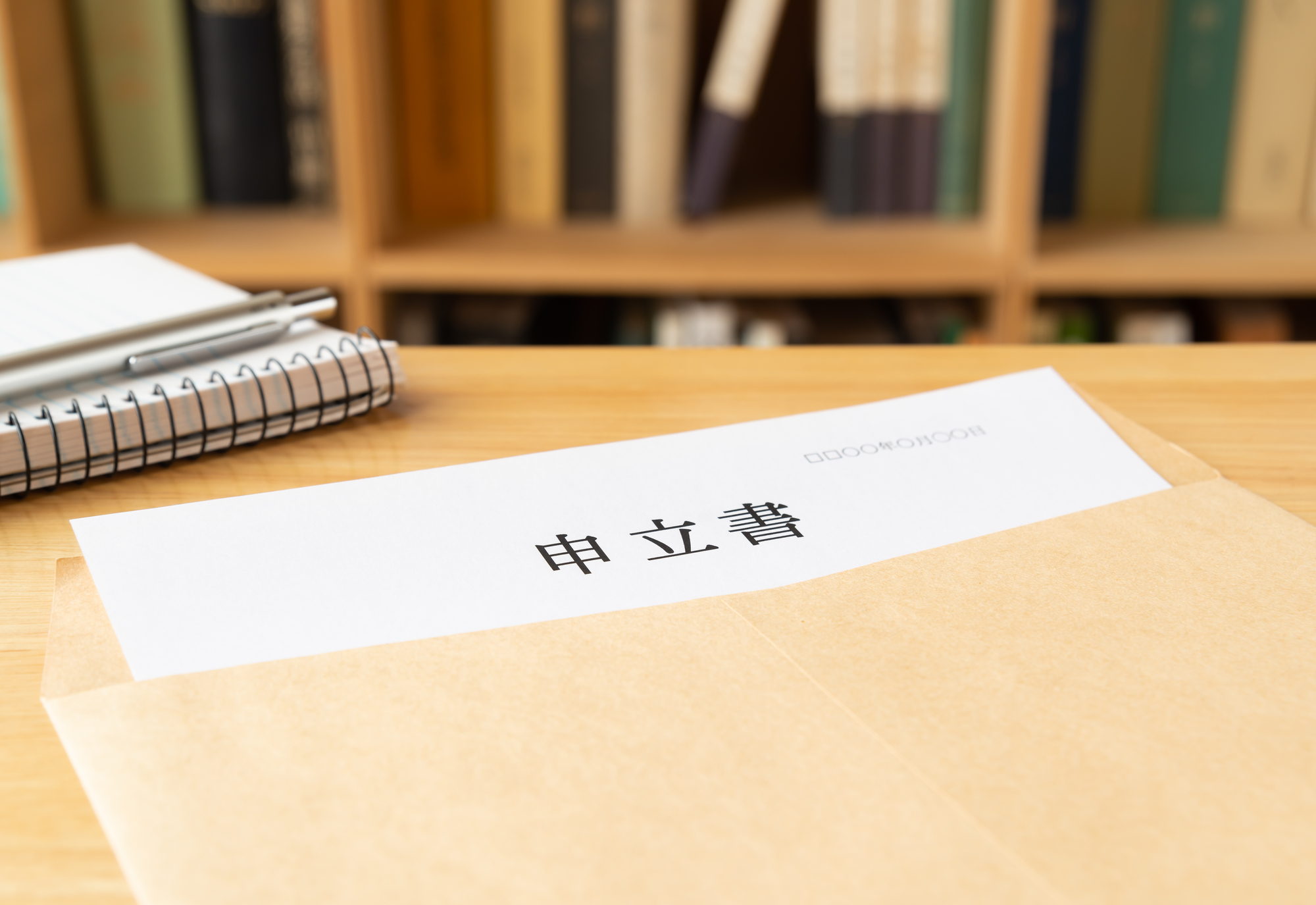
ここでは、主債務者が自己破産または民事再生(個人再生)を行った場合に連帯保証人に及ぶ影響と対処法について解説します。
自己破産は広く利用されている債務整理の方法であり、自己破産・民事再生(個人再生)のどちらも連帯保証人に一定の影響を及ぼし、それぞれ手続きや効果が異なります。
債務整理について詳しく知りたい方は、以下の関連記事も参考にしてください。
債務整理とは?3種類のメリット・デメリットや生活への影響を解説
6-1 自己破産をしたとき
自己破産は、破産法に規定されている債務整理の方法です。
裁判所に自己破産を申し立て、免責許可決定(債務を免除するという裁判所の決定)が下りると、破産法所定の非免責債権を除いて借金の支払い義務がなくなります。
ただし、連帯保証人としての債務は免責になりません。主債務者に自己破産が認められると、債権者は主債務者に請求できなくなるため連帯保証人に請求が来ます。
この場合、連帯保証人には分割による返済が認められず、一括返済を求められることが一般的です。
もし連帯保証人として返済できない場合、連帯保証人自身の自己破産または個人再生を検討する必要が出てきます。
自己破産の詳細は、下記のページも参考にしてください。
自己破産するとどうなる?メリット・デメリット、生活への影響をわかりやすく解説
6-2 民事再生(個人再生)をしたとき
民事再生(個人再生)は、民事再生法に規定された債務整理の手続きです。
裁判所に申し立てを行い、借金を減額した上で減額後の債務を原則3年〜5年以内に完済します。
自己破産と大きく異なる点が、民事再生(個人再生)では主債務者に借金の支払い義務が継続する点です。
主債務者が民事再生(個人再生)を申し立てると、減額された分について債権者から連帯保証人に請求が来ます。自己破産と同様に一括返済を求められることが一般的です。
また、連帯保証人は主債務者に代わって返済した分を主債務者に請求することはできません。
従って連帯保証人として債務を返済できない場合、自己破産のケースと同様に、連帯保証人自身の自己破産または個人再生を検討する必要が出てきます。
民事再生(個人再生)の詳細は、下記のページも参考にしてください。
個人再生(民事再生)とは?メリット・デメリットと費用の相場も解説
7.2020年の民法改正による連帯保証人制度の変更点

これまで解説したように、連帯保証人になることで大きなリスクと責任を背負い込むことになります。実際に連帯保証人になったばかりに思わぬ債務を抱え、人生が大きく変わってしまったというケースも多々あるのです。
そこで2020年の民法改正により、連帯保証人に関する規定が大きく変更されました。
具体的には、安易に連帯保証人になることの防止、不適切な契約により連帯保証人になったため債務を抱え苦しむ方の救済を目的としています。
ここでは、連帯保証人に関する民法改正のポイントについて解説します。
なお、詳細は法務省の下記資料もご確認ください。
参考:2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わります|法務省
7-1 極度額を定めていない個人根保証契約は無効
根保証とは、一定範囲内の金額(極度額)で継続的に発生する不特定の債務を、包括的に保証するものです。
①アパートの賃貸借契約の際に、毎月の家賃の保証人となる場合、②病院や介護施設に入る際に、毎月の診療費用等の保証人となる場合、③会社が取引先と継続的取引をする際に、その会社が取引先に対して負担する全ての債務をまとめて保証する場合などが代表例です。
根保証の注意点は、主債務の金額が分からないため、将来、保証人が想定外の債務を負うことになりかねないことです。特に、保証会社ではなく個人が保証人となる場合は、主債務者との人間関係をきっかけに、保証のリスク計算を十分にせずに保証を引き受ける場合があったため、保証人の保護が必要と言われてきました。
そこで改正民法第465条の2では、個人が締結する根保証契約では貸金契約に限らず全ての契約において極度額を定めないと効力を生じないとされました。(なお、貸金契約の場合は、すでに、2005年4月1日から、民法よりも厳しいルールが定められており、極度額の定めも義務付けられています。)
極度額は書面などで「○○円」と定め、当事者間の合意が必要になります。
7-2 公証人による保証意思確認手続の新設
公証人とは、判事(裁判官)、検事、法務事務官などを長く務めた法律実務の経験豊かな者の中から、公証人法の規定により、法務大臣が任命した者のことをいい、公証役場で勤めています。公証人が作成した公正証書は、真正な公文書と推定されます(民事訴訟法第228条2項、公証人法第2条)。
改正民法第465条の6から9では、個人が事業用融資の保証人になる場合、事前に公証人による保証意思の確認と公正証書による債務保証履行の意思表示が義務化されました。これが欠けた保証契約は無効です。
これにより、事業用融資に際し、その事業に関与していない親戚や友人などの第三者が安易に保証人になってしまい、多額の債務を負うというリスクが減る効果が期待できます。
7-3 情報提供義務の新設
主債務者の財産や収入の状況が分からない状態で(連帯)保証人になることは、リスクが大き過ぎます。
そこで改正民法第465条の10では、事業用融資に際し、個人を(連帯)保証人として保証契約を締結する際に債務者は事前に保証人または連帯保証人に対して財産と収支の状況、債務の有無および履行状況、担保の状況を開示することが義務付けられました。
もし主債務者から十分な情報提供がない状態で事業用融資の(連帯)保証契約を締結したとき、(連帯)保証人はその(連帯)保証契約を取り消すことができます。
また、(連帯)保証人が個人の場合、主債務者が返済を滞らせ債権者が一括返済を求めたとき(期限の利益の喪失)、債権者はそれを知ってから2ヶ月以内に(連帯)保証人に知らせることが義務化されました(民法458条の3)。
主債務者が期限の利益を喪失していることを保証人が知ることで、(連帯)保証人はすぐに主債務者に代わって返済し遅延損害金の発生を防ぐことができます。
8.連帯保証人に関するよくある質問/対処法

最後に、連帯保証人についてよくある質問をご紹介します。
8-1 知らないうちに勝手に連帯保証人にされた場合はどうすれば無効にできますか?
契約は両者の合意がないと成立せず(民法522条第1項)、連帯保証契約は債権者と連帯保証人になる方との書面による契約が無ければ効力が生じません。
従って、知らない間に連帯保証人にされていた場合の連帯保証契約は基本的に無効と考えられます。
ただし、主債務者に騙されて連帯保証契約に署名捺印していた場合、債権者保護のために表見代理が認められ連帯保証債務を負う可能性があります。
いずれにしても、自分の意思に反した連帯保証契約は事実関係を整理した上で早急に弁護士に相談してください。
8-2 連帯保証人を辞めたいときはどうすればいいですか?
民法第521条の契約自由の原則により、契約したあと、債権者と債務者が合意に達した場合は契約を解除できます(合意解除)。
これは連帯保証契約も同様で、債権者が合意さえすれば、連帯保証人を辞めることができるのです。ただし、連帯保証契約の無効や取消を主張しても、契約そのものに不備がなければ解除は難しいと考えられます。
交渉の方法としては、新たな連帯保証人を立てたり土地や建物など物的担保を提供することが考えられます。
連帯保証契約は一度締結すると債権者との交渉が難しいことが多いため、弁護士に相談することがおすすめです。
8-3 離婚するので住宅ローンの連帯保証人から外れることはできますか?
日常の家事債務に関する夫婦の連帯責任の規定(民法第761条)では、夫婦は一方が行った法律行為により生じた債務についてお互いに連帯して責任を負うと定めています。
婚姻期間中に発生した債務であれば、離婚したあとも主債務者と同様の責任を負うことになるのです。
そのため、債権者の同意がないかぎり離婚を理由に配偶者の住宅ローンの連帯保証人から外れることは難しいといえるでしょう。
対策としては、新たな連帯保証人を立てるか、別の金融機関で住宅ローンを借り換えることが考えられます。
元夫婦とはいえお互いの利害関係や債権者の債権保全が絡むことなので、交渉は難航することが予想されます。
従って、早めに弁護士に相談することがおすすめです。
8-4 親が連帯保証人になっており先日死亡しました。相続は発生しますか?
連帯保証人となっている方が亡くなった場合、被相続人(亡くなった方)の連帯保証債務も相続財産の対象です。
相続人が複数いる場合は法定相続割合に応じて、あるいは相続人同士の話し合いで決めた割合に応じて、各相続人は連帯保証債務の返済義務を負うことになります。
財産に対して連帯保証債務の方が多い場合は、相続放棄を検討する必要があります。相続放棄をすれば最初から相続人ではなかったことになるため、被相続人の連帯保証債務を負う必要はありません。
相続は複雑でトラブルが発生しやすいものです。もし被相続人が連帯保証人になっていることが分かった場合は、早めに弁護士にご相談ください。
8-5 連帯保証人になるメリットは?なってはいけないと聞いたのですが頼まれたらどうやって拒否すればいいですか?
主債務者にとっては、連帯保証人を付けることで、アパートに入居しやすくなったり、病院や施設に入りやすくなったり、ローンを組みやすくなるといったメリットがあります。
しかし、連帯保証人にとっては、法的には、メリットはありません。連帯保証人になると、主債務者が支払いを滞納した際などに、代わりに債務の全額に対して支払い義務を負うことになります。
もちろん、子どもの進学を支援できたり、配偶者の連帯保証人になったりすることで家を購入できるといった間接的なメリットはありますが、直接的に何らかの利益を得られるものではありません。頼まれた場合でも、軽率に引き受けるべきではないでしょう。
友人や知人などから頼まれた場合は、保証会社の利用や親族に連帯保証を依頼するようすすめてみてください。
相手が連帯保証人になるよう執拗に求めてくる場合など、さらなるトラブルに発展する恐れがあるときは、早めに弁護士に相談してください。
9.連帯保証人を引き受ける前に慎重な判断を!困ったときは弁護士の力を借りよう!

これまで解説した通り、連帯保証人になることは、債務の返済について主債務者と同等の大きな責任を負うことを意味します。
もし主債務者が返済できず連帯保証人として返済することになれば、金額によっては財産の全てを失うことになりかねません。
従って親しい方から連帯保証人になってほしいと言われても、返事をする前に冷静になり、よく調べ、よく検討するようにしましょう。安易に連帯保証人を引き受けると、近い将来に深く後悔することになる可能性があるのです。
連帯保証人になるように頼まれている方、あるいは連帯保証人になってしまったためお困りの方は弁護士にご相談ください。
弁護士は連帯保証契約を無効・解除するための債権者への連絡といった事務処理や、連帯保証債務の負担を減らすためのサポートなどを提供しています。
当事務所は法律相談30万件以上の相談実績を誇っており、借金問題を取り扱った経験が豊富なスタッフが多数在籍しています。
連帯保証人になるべきかお悩みの方、連帯保証人になってしまったためトラブルとなり弁護士に依頼したいとお考えの方は、お気軽にご相談ください。
このページの監修弁護士
弁護士
三上 陽平(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)
中央大学法学部、及び東京大学法科大学院卒。
2014年弁護士登録。
都内の法律事務所を経て、2015年にライズ綜合法律事務所へ入所。
多くの民事事件解決実績を持つ。第一東京弁護士会所属。