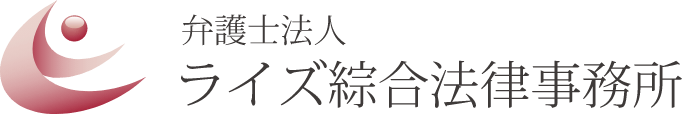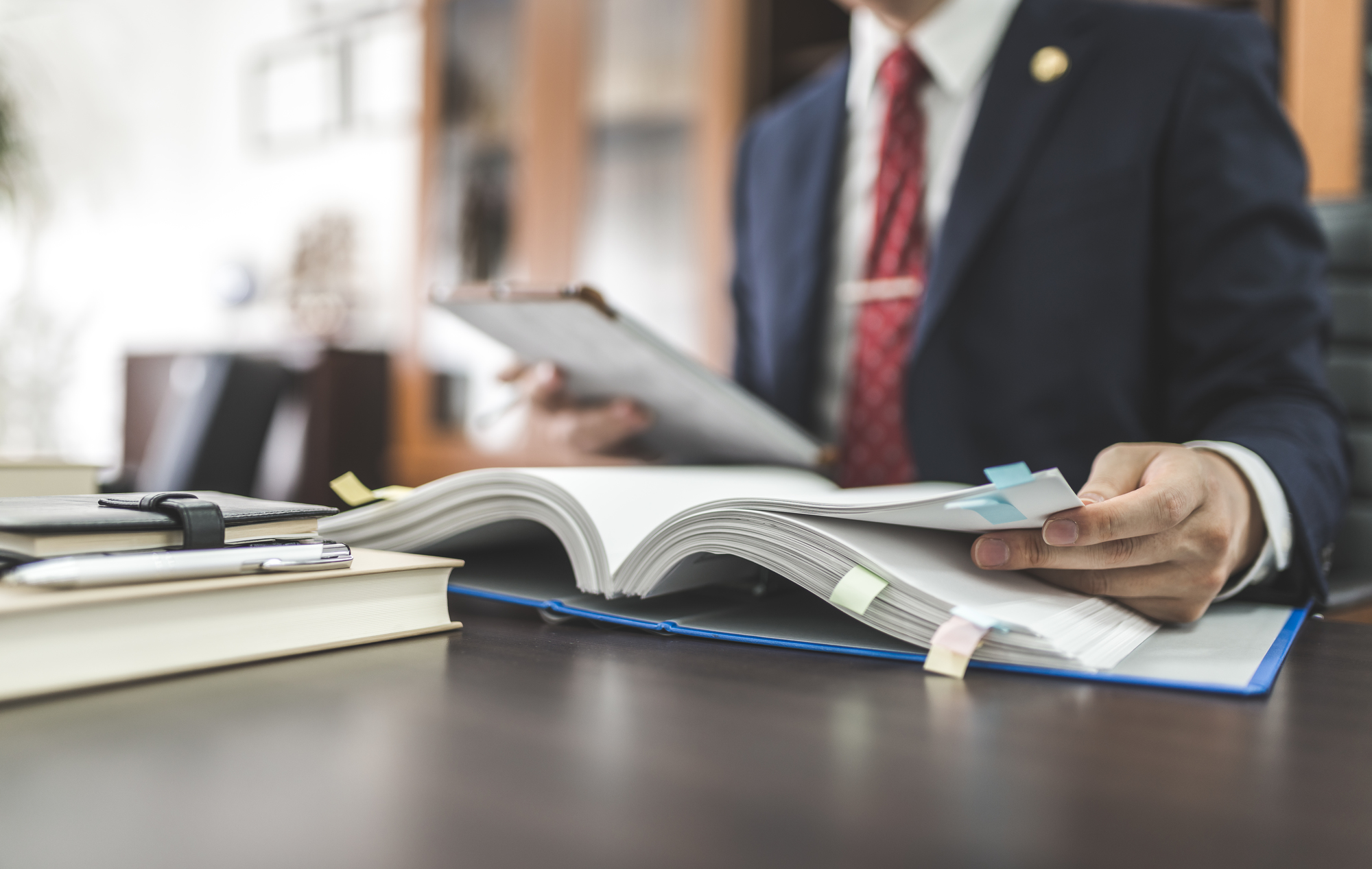1.養育費とは

養育費とは、簡単にいうと離婚後に発生する、子どもを育てるのにかかる費用です。子どもが経済的、社会的に自立するまでに必要な生活費などの費用を指します。
子どもを監護している親は、監護していない親に対して養育費を請求できます。例え離婚して別の場所で暮らしていても、子どもの親であることには変わりがなく、子どもを育てるのに必要なお金を負担する義務があるためです。
養育費には、例えば以下のような費用が含まれています。
- 子どもの生活費
- 学費など教育費
- 医療費
- 交通費
- 娯楽費やお小遣い
便宜上、養育費を受け取る側の親を「権利者」と呼びますが、厳密にいうと養育費は子どもの権利です。養育費の支払い条件や金額は法律で定められていません。そのため「何歳まで払うのか」「金額はいくらか」といった内容は父母の協議によって決定します。
1-1 婚姻費用との違い
養育費と似た言葉として「婚姻費用」があります。養育費との違いは「配偶者の生活費が含まれるかどうか」です。
婚姻費用は、夫婦間の扶養義務を根拠としているため、夫婦のうちどちらかが無職のケースなどは、もう片方が婚姻費用を負担することとなります。婚姻費用には子どもの生活費だけではなく配偶者の生活費も含まれるため、養育費と比較すると高額になりがちです。
支払いのタイミングも異なります。婚姻費用は夫婦が離婚すると、それ以降支払う必要はなくなりますが、養育費は離婚後に発生する費用です。
2.養育費の決め方
養育費の金額や支払い条件は法的に定められていないため、夫婦間の協議によって決定します。その際に何を決めるのかは、夫婦によってさまざまです。しかし、後々揉めないためには、最低限以下の項目は話し合っておきましょう。
- 養育費の金額
- いつまで支払うのか
- 支払いのタイミング
- 振込先
- そのほか特別の出費があったときの負担
話し合いがまとまらない場合、「養育費請求調停」や「夫婦関係調整(離婚)調停」を家庭裁判所に申し立てましょう。調停委員が相互の言い分を聞き、落としどころをまとめて提案してくれます。
調停がうまくいかず不調に終わった場合、訴訟で決着をつけることになります。養育費の決め方の詳細は、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
離婚後の養育費はどうなる?決め方や平均相場を詳しく解説
養育費に関する約束は口頭でも成立します。しかし、支払いが滞った際にトラブルになる可能性も高く、前述のように調停や訴訟で紛争に発展するケースも少なくありません。そのため、書面に残しておくことをおすすめします。
相手の支払い能力や誠実さに不安があり、養育費が支払われないことが懸念される場合は、「強制執行認諾文言」付きの公正証書にしておくことがおすすめです。公正証書は公証人の立ち会いのもと作成するため、通常の契約書と比べて証拠能力が高いという特徴があります。
公正証書に「強制執行認諾文言」を付与することで、差押えなどの強制執行に必要な「債務名義」となり、支払いが滞った際に訴訟や調停の手続きをしなくても財産を差押え可能です。
公正証書に関しては以下の記事で詳しく紹介しています。
公正証書とは?作成までの流れやメリット・デメリットについて解説
3.養育費の相場

養育費は法律で金額等は決められていませんが、裁判所が司法研究の一環として公開している「養育費算定表」という目安があります。ここでは、算定表のデータや平均値など、裁判所の公開情報を紹介します。
3-1 養育費算定表から見る相場
養育費算定表は、家庭裁判所の司法研究をもとに作成されたものです。父母の年収と子どもの年齢・人数から養育費を簡易的にまとめたもので、多くのケースで養育費算出の参考にされています。この表のデータをもとに、養育費の相場を見てみましょう。
厚生労働省の「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果の概要」によると、 子どもを養育していることが多い母子家庭(同居親族を含む世帯全員の収入)の世帯年収の平均額は373万円です。そのため、権利者の年収を母子家庭の世帯年収に近い350万円(自営なら256万円)と仮定し、支払義務者の年収(給与所得者)ごとに養育費の金額を紹介します。
参考:令和3年度 全国ひとり親世帯等調査の結果を公表します|厚生労働省
参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所
3-1-1 年収300万円
支払義務者の年収が300万円の場合、子どもの人数別の月額養育費は次の通りです。
【月額養育費の目安】
| 月額養育費 | |
|---|---|
| 子1人(14歳以下) | 2万円~4万円 |
| 子2人(どちらも14歳以下) | |
| 子2人(15歳以上と14歳以下1人ずつ) | |
| 子2人(どちらも15歳以上) | |
| 子3人(全員14歳以下) | |
| 子3人(1人のみ15歳以上) | |
| 子3人(うち2人が15歳以上) |
※権利者の収入を350万円(自営業者の場合256万円)と想定
3-1-2 年収400万円
支払義務者の年収が400万円の場合、子どもの人数別の月額養育費は次の通りです。
【月額養育費の目安】
| 月額養育費 | |
|---|---|
| 子1人(14歳以下) | 2万円~4万円 |
| 子2人(どちらも14歳以下) | 4万円~6万円 |
| 子2人(15歳以上と14歳以下1人ずつ) | |
| 子2人(どちらも15歳以上) | |
| 子3人(全員14歳以下) | |
| 子3人(1人のみ15歳以上) | |
| 子3人(うち2人が15歳以上) |
※権利者の収入を350万円(自営業者の場合256万円)と想定
3-1-3 年収500万円
支払義務者の年収が500万円の場合、子どもの人数別の月額養育費は次の通りです。
【月額養育費の目安】
| 月額養育費 | |
|---|---|
| 子1人(14歳以下) | 2万円~4万円 |
| 子2人(どちらも14歳以下) | 4万円~6万円 |
| 子2人(15歳以上と14歳以下1人ずつ) | 6万円~8万円 |
| 子2人(どちらも15歳以上) | |
| 子3人(全員14歳以下) | |
| 子3人(1人のみ15歳以上) | |
| 子3人(うち2人が15歳以上) |
※権利者の収入を350万円(自営業者の場合256万円)と想定
3-1-4 年収600万円
支払義務者の年収が600万円の場合、子どもの人数別の月額養育費は次の通りです。
【月額養育費の目安】
| 月額養育費 | |
|---|---|
| 子1人(14歳以下) | 4万円~6万円 |
| 子2人(どちらも14歳以下) | 6万円~8万円 |
| 子2人(15歳以上と14歳以下1人ずつ) | |
| 子2人(どちらも15歳以上) | 8万円~10万円 |
| 子3人(全員14歳以下) | |
| 子3人(1人のみ15歳以上) | |
| 子3人(うち2人が15歳以上) |
※権利者の収入を350万円(自営業者の場合256万円)と想定
3-1-5 年収800万円
支払義務者の年収が800万円の場合、子どもの人数別の月額養育費は次の通りです。
【月額養育費の目安】
| 月額養育費 | |
|---|---|
| 子1人(14歳以下) | 6万円~8万円 |
| 子2人(どちらも14歳以下) | 10万円~12万円 |
| 子2人(15歳以上と14歳以下1人ずつ) | |
| 子2人(どちらも15歳以上) | |
| 子3人(全員14歳以下) | |
| 子3人(1人のみ15歳以上) | 12万円~14万円 |
| 子3人(うち2人が15歳以上) |
※権利者の収入を350万円(自営業者の場合256万円)と想定
3-1-6 年収1,000万円
支払義務者の年収が1,000万円の場合、子どもの人数別の月額養育費は次の通りです。
【月額養育費の目安】
| 月額養育費 | |
|---|---|
| 子1人(14歳以下) | 8万円~10万円 |
| 子2人(どちらも14歳以下) | 12万円~14万円 |
| 子2人(15歳以上と14歳以下1人ずつ) | 14万円~16万円 |
| 子2人(どちらも15歳以上) | |
| 子3人(全員14歳以下) | |
| 子3人(1人のみ15歳以上) | 16万円~18万円 |
| 子3人(うち2人が15歳以上) |
※権利者の収入を350万円(自営業者の場合256万円)と想定
3-1-7 年収1,500万円
支払義務者の年収が1,500万円の場合、子どもの人数別の月額養育費は次の通りです。
【月額養育費の目安】
| 月額養育費 | |
|---|---|
| 子1人(14歳以下) | 14万円~16万円 |
| 子2人(どちらも14歳以下) | 20万円~22万円 |
| 子2人(15歳以上と14歳以下1人ずつ) | 22万円~24万円 |
| 子2人(どちらも15歳以上) | 24万円~26万円 |
| 子3人(全員14歳以下) | |
| 子3人(1人のみ15歳以上) | |
| 子3人(うち2人が15歳以上) | 26万円~28万円 |
※権利者の収入を350万円(自営業者の場合256万円)と想定
3-1-8 年収2,000万円
支払義務者の年収が2,000万円の場合、子どもの人数別の月額養育費は次の通りです。
【月額養育費の目安】
| 月額養育費 | |
|---|---|
| 子1人(14歳以下) | 20万円~22万円 |
| 子2人(どちらも14歳以下) | 28万円~30万円 |
| 子2人(15歳以上と14歳以下1人ずつ) | 30万円~32万円 |
| 子2人(どちらも15歳以上) | 32万円~34万円 |
| 子3人(全員14歳以下) | 34万円~36万円 |
| 子3人(1人のみ15歳以上) | |
| 子3人(うち2人が15歳以上) | 36万円~38万円 |
※権利者の収入を350万円(自営業者の場合256万円)と想定
3-2 ひとり親がもらっている養育費の平均額
厚生労働省の統計資料に、子どもの数ごとの養育費の平均金額があります。令和3年の平均値は以下の通りです。
【子どもの人数別養育費の平均額(1世帯当たり、月額)】
| 母子世帯 | 父子世帯 | |
|---|---|---|
| 1人 | 4万468円 | 2万2,857円 |
| 2人 | 5万7,954円 | 2万8,777円 |
| 3人 | 8万7,300円 | 3万7,161円 |
| 4人 | 7万503円 | (該当データなし) |
| 5人 | 5万4,191円 | (該当データなし) |
※数値引用:令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果 表17-(3)-13 子どもの数別養育費(1世帯平均月額)の状況|厚生労働省
4.養育費の計算に必要となる収入の調べ方

適正な養育費を請求するためには、相手の収入に対しいくらが相場なのかを知らなければなりません。では、相手の収入はどのように調べれば良いのでしょうか。
ここでは、相手が会社員の場合、自営業者の場合に分けて、それぞれ調べる方法を紹介します。
4-1 会社員の場合
相手が会社員の場合は、原則として昨年の源泉徴収票を参照します。「支払金額」の項目があるので、この金額が相手の収入ということになります。「支払金額」は、税金や社会保険料など、各種控除が差し引かれる前の給与額です。
源泉徴収票を紛失している場合などは、給与明細や給与口座の振込記録などから、概ねの年収が確認できます。
賃貸用の不動産を所有していて賃料収入がある場合や、副業でも収入を得ている場合は、市区町村役場の発行する課税証明書を取得するのが確実です。
4-2 自営業者等の場合
相手が自営業者の場合は、一般的に所得税の確定申告書が収入の証明書になります。「課税される所得金額」の項目で年収を確認してください。
ただし自営業者の確定申告書には、会社員の社会保険料などとは違う「実質的には収入の減少に影響していないが、所得からは控除されている項目」があります。青色申告特別控除などが代表的な例です。
こうした事情から、実質的な年収を評価するのが難しいケースも少なくありません。通帳や請求書などからもおおよその売上を確認できますが、確定申告書を弁護士に見てもらうのが確実でしょう。
5.養育費が相場よりも高くなる要素

養育費は、前述の算定表の数値に近い金額となることが多いのですが、場合によっては相場より高くなる、増額請求ができるといったこともあります。では、どのようなときに相場より高くなるのか、詳しく見てみましょう。
5-1 子どもを監護する親の収入が低くなる
子どもを監護する親の収入が低い場合や、金額を取り決めた当初の金額より下がった場合には養育費の金額が高くなることがあります。
例えば、子どもを監護している親がケガや病気で働けなくなったり、勤め先が倒産して無収入になったりしたときなどが代表的です。このように、収入が減少し、子どもの生活費が不足すると、追加で請求できる可能性があります。
5-2 監護をしない親の収入が上がる
子どもを監護していない親の収入が上がると、養育費増額の要因となることがあります。子どもの養育費の決定には父母の収入が大きな要因となっており、収入が大きく増加した場合などは、その分の養育費の増額を求められる可能性があります。
5-3 子どもが病気になる
子どもが大きな病気にかかったケースなども、養育費増加の要件です。
子どもが病気にかかると、通院や入院により医療費が増加します。看護をしていない親にもその分を負担するよう求めることができるため、養育費として請求可能です。また、監護している親が看病で働けず収入が減少すると、子どもの生活費が足りなくなります。この点も、養育費の増額を求める根拠となります。
5-4 子どもが高校や大学に進学する
子どもの進学により教育費がかかったときも、その分養育費を増額できる可能性があります。例えば、子どもが大学に進学しその分の学費が発生すると、養育費という形で監護していない親に負担を求めることが可能です。
前述の算定表でも子どもが15歳になったタイミングで養育費が増加しています。なお、請求できるのは授業料だけでなく、教材費や進学先の寮費なども対象です。
6.養育費に関するよくある疑問

ここでは、養育費に関するよくある疑問を紹介します。
以下の記事でも、養育費が発生する要因や、面会交流との関係について疑問に回答しています。こちらもご覧ください。
離婚後の養育費はどうなる?決め方や平均相場を詳しく解説
6-1 一括払いは可能ですか?
養育費の受け取り方に決まったルールはないため、父母両者の同意があれば一括で受け取ることも可能です。
養育費の支払いは10年以上の長期に渡ることも多く、支払義務者に環境の変化があると、途中で途絶えてしまうこともあります。こうしたときに備えて、あらかじめ全額または1年単位など一定期間分を受け取ることで、確実な養育費の確保が可能です。
ただし、まとまった養育費を受け取るとなると金額も相応に大きくなります。支払義務者の経済状況によっては受け取りが難しいかもしれません。
6-2 過去に遡って養育費をもらうことは可能ですか?
原則的に、養育費の取り決めをしていなかった場合に、過去に遡って請求することは難しくなります。ただし、以下のようなケースでは養育費を受け取れる可能性があります。
- 相手と交渉し養育費を支払うことの了承を得た
- 別居した時点で認知が確定していないなど養育費を請求できない事情があった
- 家庭裁判所が養育費を支払う必要があると判断した
- 相手が離婚時に取り決めた養育費を滞納している
養育費について取り決めずに離婚したのであれば、早めに相手に連絡して協議を持つことが大切です。話がまとまらない場合は、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てることをおすすめします。
請求や調停の手続きが不安であれば、家事事件に精通した弁護士に相談してみてください。
6-3 監護親の方が収入が高いときの養育費はどうなりますか?
子どもを育てている監護親の方が収入が高い場合でも、養育費は受け取れます。子どもを養育することは父母双方の義務であり、収入が監護親より少なくともその点は変わりません。ただし、算定表を見ても分かるように、養育費の金額は両者の収入に大きく依存します。監護親の方が収入が高いと、相場より高い養育費を請求することは難しいでしょう。
6-4 養育費は途中で増額できますか?減額になることもあるのでしょうか?
養育費の支払い条件は父母の間で決められるため、双方の同意があれば途中で受け取る金額を増額できることもあります。自分や子どもの状況が変化し、子育てにかかる費用が増えたときは増額を打診することも選択肢の1つです。
ただし、協議で金額を変更できるのは増額するケースだけではありません。支払義務者の収入の減少や、両親どちらかの再婚などにより減額を求められることもあります。
6-5 未婚の場合の養育費の相場はどのくらいですか?
父親が子どもを認知していれば、未婚の場合でも夫婦が離婚したときと同等の養育費を請求できます。認知とは、戸籍上未婚の男女の間に生まれた子どもを、男性側が自分の子どもであると法的に認めることです。
話し合いによって認知を求めることが難しい場合は、調停や訴訟の手続きを行い、強制的に認知させることも可能です。
なお、認知されていない場合であっても、父親が養育費の支払いに同意しているのであれば受け取ることはできます。
6-6 住宅ローン支払いがある場合は養育費を減額できますか?
住宅ローンの返済を養育費に代えることができるかどうかはケースバイケースです。
原則子どもの父母両者の合意に基づきますが、認められるかどうかは以下の通り状況によって異なります。そのため、住宅ローンの返済や売却なども含めて、弁護士に相談するのが望ましいです。
| 減額しやすいケース |
|
| 減額しにくいケース |
|
6-7 離婚後に養育費を支払ってもらえない場合はどうすれば良いでしょうか?
離婚後に養育費の支払いが滞ることは珍しくありません。この場合、一般的に以下の段階を踏んで請求を行います。
- 電話やメッセージで催促する
- 内容証明郵便で請求を行う
- 裁判所に調停や審判を申し立てる
- 履行勧告や履行命令を行う(※)
- 強制執行を行う
※調停での取り決めを守らない相手に対して裁判所から説得または命令してもらうこと。
2番目以降は自分で行うのは難しいため、弁護士に相談することをおすすめします。
7.養育費の相場は状況によって異なる!不倫・浮気の慰謝料問題についてもお悩みなら弁護士に相談を

養育費は父母の収入や子どもの人数、年齢などによって決まるため、ケースごとに金額は異なります。通常は紹介した養育費の算定表に近い金額に収まることが多いのですが、この金額は法律で決まっているわけではありません。そのため、当事者間で協議した結果、相場よりも高い、もしくは低い養育費になるケースもあります。
なお、離婚の原因が配偶者の不貞行為であれば、養育費とは別に慰謝料を請求できます。慰謝料は夫婦間の損害賠償の一種であるのに対し、養育費は子どもが経済的、社会的に自立するのに必要な費用です。どちらも適正な金額を受け取ることが大切です。
ライズ綜合法律事務所は、夫婦や家庭の法律問題に関する経験の豊富なスタッフが多数在籍しています。慰謝料の請求を任せられる弁護士をお探しであれば、お気軽にご相談ください。
このページの監修弁護士
弁護士
三上 陽平(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)
中央大学法学部、及び東京大学法科大学院卒。
2014年弁護士登録。
都内の法律事務所を経て、2015年にライズ綜合法律事務所へ入所。
多くの民事事件解決実績を持つ。第一東京弁護士会所属。