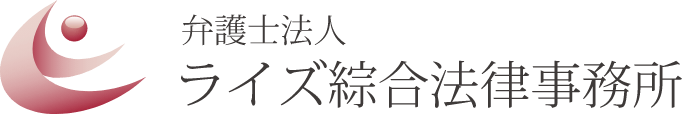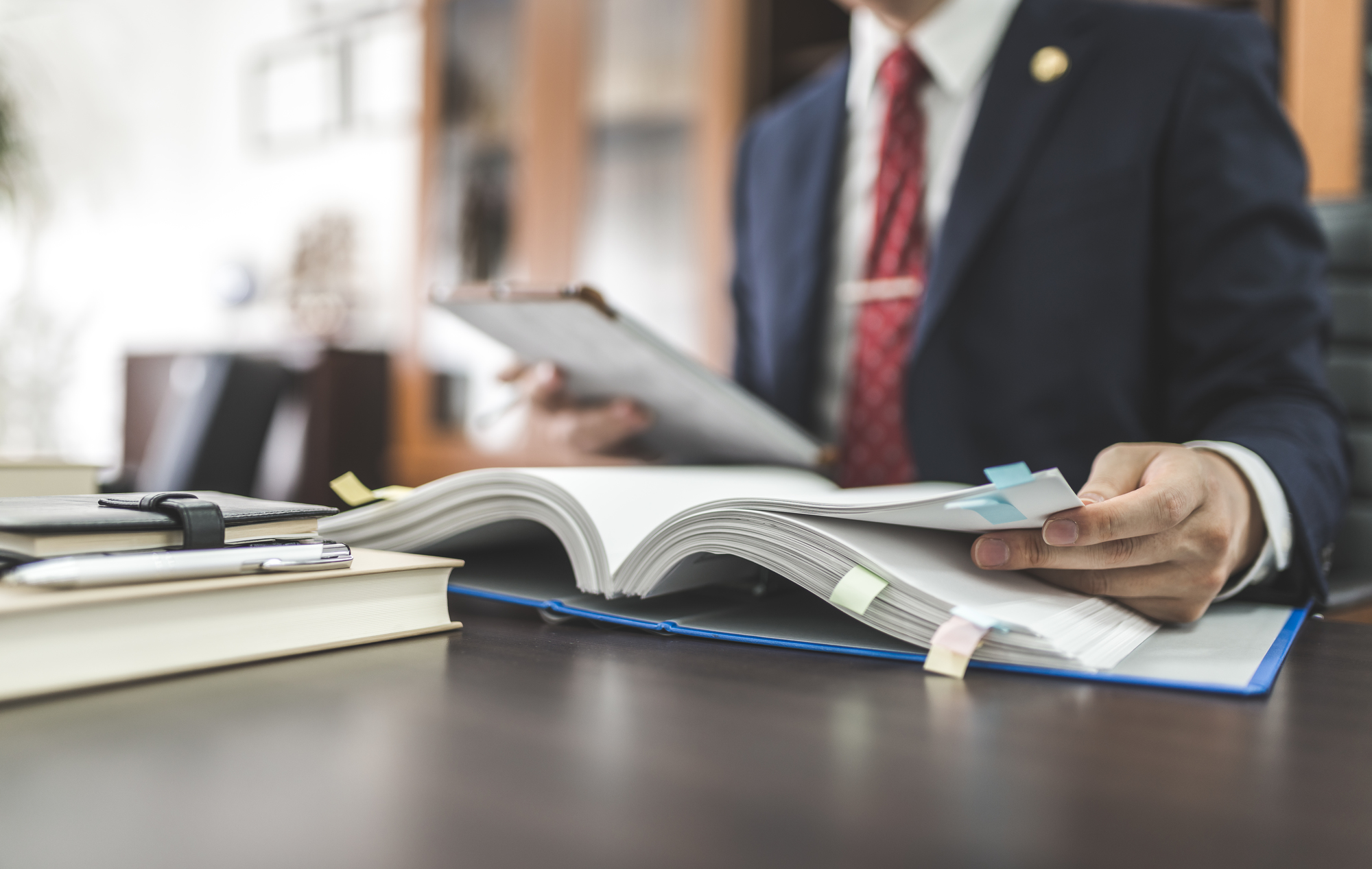1.配偶者に不貞行為の慰謝料を請求できる条件

民法上の不法行為とされる不倫とは不貞行為、つまり配偶者以外の者と肉体関係(性行為)を持つことです。
慰謝料を請求するためには、不倫の事実を裏付ける証拠があること、あるいは、相手方が不倫した事実を認めることが必要です。相手方が不倫の事実を認める場合には、必ずしも証拠が必要とされるわけではないですが、相手方が不倫の事実を争う場合には、不倫の事実を裏付ける証拠が必要になります。
慰謝料を請求できる条件に関しては、以下の記事でも詳しく紹介しています。こちらも参照してください。
慰謝料請求できる条件は?金額の相場や請求方法、注意点を解説
1-1 不貞行為の証拠がある
相手が不倫していた事実を素直に認めれば、証拠は必要ありません。一方で、証拠がない状態で相手方が不倫を認めなければ、慰謝料を請求することは難しくなります。
不倫の事実を相手方が認めようとしない状態で慰謝料を請求するためには、誰が見ても明らかに不倫していたと分かる証拠が必要です。例えば、不倫・浮気相手と一緒に映っている写真(不貞行為中の写真や、ラブホテルに二人で入っている写真など)や密会をしたことが分かるSNS・メールの履歴などといったものです。
証拠がない状態で配偶者に不倫の事実を問い詰め慰謝料を請求しても、その事実を認めないばかりか残っている証拠が処分されてしまう可能性があります。また、慰謝料請求できるような証拠があるかどうかは弁護士でなければ判断できない場合もあり、素人判断は危険です。
1-2 法律上の夫婦関係にある
損害賠償請求の対象となる不倫とは、原則、法律上の夫婦関係にある男女の一方が配偶者以外の異性と肉体関係(性行為)を持つ不貞行為のことです。
ここでいう法律上の夫婦とは、民法が定める手続きに従い役所に婚姻届を提出した夫婦のことをいいます。
また、法律上の夫婦関係がある場合に準じて、内縁関係や婚約関係にある場合も慰謝料請求できる余地があります。
ただし、婚約に関しての書面などがなく口約束に過ぎない場合、婚約関係にあるとは評価されないこともあるため注意してください。
1-3 婚姻関係が破綻していない
法律上の夫婦であっても、その関係が事実上破綻している場合は慰謝料の請求が認められません。
民法は、夫婦が守らなければならない基本的な義務として、不倫しないという貞操義務のほかに同居義務・協力義務・扶助義務を定めています。そのため、別居状態である、同居していても関わりがない、お互い会話が一切ないといった状態では、婚姻関係が破綻していると判断されるかもしれません。(ただし、破綻というためには、婚姻関係が完全に復元の見込みがなくなっていなければならないとされています。そのため、裁判所は破綻の有無を厳格に審査するのが通常です。)
婚姻関係が破綻していると、相手が不貞行為をしていても慰謝料を請求することはできません。
1-4 不貞行為に対する消滅時効が完成していない
不倫した配偶者に慰謝料を請求する権利は、以下のどちらかの年数を経過すると時効によって消滅します。
- 配偶者が不倫している事実(不法行為)を知ったときから3年間
- 配偶者が不倫したとき(不法行為)から20年間
これらの時効期間が経過すると慰謝料を請求する権利は消滅し、たとえ不倫した事実の明らかな証拠があっても、裁判では不貞行為として認められなくなります。
証拠集めなどで時間がかかっており慰謝料の請求までに時効期間が経過するおそれがあるときは、すみやかに弁護士に相談し、時効の中断(期間の更新)をしてください。時効を中断するためには、配偶者に内容証明郵便で慰謝料の支払いを請求し、6ヶ月以内に訴訟を提起することが必要です。
1-5 離婚はしなくてもOK
配偶者による不倫は、民法に規定する離婚原因の1つです。ただし、配偶者が不倫したとしてもただちに離婚となるわけではありません。不倫された方が婚姻関係の継続を望めば、法律上の婚姻関係を継続する余地があります。子どものことや今後の生活のことを考えたら、たとえ配偶者が不倫したとしても法律上の婚姻関係を継続することは選択肢の1つでしょう。
このように、離婚しなくても不倫した配偶者に対し慰謝料を請求できます。ただし、離婚しないのであれば、不倫が原因で婚姻関係が破綻し離婚した場合と比べて慰謝料の金額は低くなる可能性はあります。
2.配偶者に不貞行為の慰謝料を請求できないケース
不倫の慰謝料はどのようなケースでも請求できるわけではありません。以下のようなケースでは慰謝料を請求できない可能性があります。
- 食事デートのみなど肉体関係(性行為)や類似の行為がない
- 用意した証拠が肉体関係(性行為)を立証するには不十分
- 肉体関係(性行為)が不倫・浮気相手からの脅迫や強要によるものだった
- 不倫をしていた時点で婚姻関係が破綻していた
- 既に時効が成立している
- その不倫に対して既に十分な慰謝料を不倫・浮気相手から受け取っている
3.不倫・浮気相手に不貞行為の慰謝料を請求できる条件
民法では、不貞行為は配偶者と不倫・浮気相手方による共同不法行為です。よって配偶者だけでなく不倫・浮気相手もまた、不倫をされてしまった被害者の精神的苦痛について「連帯してその損害を賠償する責任を負う」としています。つまり、不倫が原因で受けた精神的苦痛に対する慰謝料は、配偶者だけではなくその不倫・浮気相手にも請求可能です。
つまり、配偶者が既婚者と知って不貞行為をした者、もしくは注意をすれば既婚者だと分かるような状態であれば、不倫・浮気相手にも慰謝料を請求することができます。
4.不倫・浮気相手に不貞行為の慰謝料を請求できないケース
不倫では、配偶者が不倫・浮気相手に対して独身と偽っているケースもあります。そのため、以下の要件に該当する場合は、慰謝料請求を請求するのは難しいでしょう。
- 配偶者の不倫・浮気相手が「配偶者が既婚者であること」を知らなかった
- 上記を知らなかったことについて不倫・浮気相手に過失がない
まとめると、配偶者の不倫・浮気相手が、配偶者が既婚者と知って不貞行為をした、もしくは注意をすれば既婚者だと分かるような状態でなければ、慰謝料を請求できないことになります。
5.不倫の慰謝料の相場はいくらか?

不倫に対する慰謝料の金額は、法律などで具体的な基準や計算方法などが定められているわけではありません。そのため、裁判での判決を除き、慰謝料の金額は配偶者や不倫・浮気相手との話し合いで決まります。
当事者間の話がまとまらず調停や裁判で決める場合でも慰謝料の金額はかなり幅が大きく、高くて300万円ほどでしょう。もちろん、当事者や不倫の状況などによってはさらに高くなることもありますし、まったく受け取れないこともあります。
慰謝料が決定される要素はさまざまですが、金額を左右する大きな要因の1つが、不倫によって夫婦が離婚するかどうかです。離婚の有無による金額の変動は概ね以下の通りです。
| 全体的な相場 | 50万円~300万円 |
| 離婚に至らない場合 | 50万円~100万円 |
| 離婚に至った場合 | 100万円~300万円 |
6.不倫の慰謝料が高額になるケース
不倫の慰謝料は、それが原因で受けた精神的苦痛のほかに不倫が及ぼしたマイナスの影響およびこれまでの夫婦生活に対する裏切りの観念などが総合的に勘案されます。また、以下のような影響があれば、不貞行為があっただけの場合よりも慰謝料の金額は高くなると考えられます。
- 不倫が原因で離婚する
- 夫婦間に幼い子どもがおり離婚後は引き取る方針
- 家庭に影響を及ぼすほどの金銭を不倫・浮気相手に渡していた
- 不倫の事実が世間に知られた
- 不倫した配偶者や不倫・浮気相手の社会的地位や収入が高い
- 不倫していた期間が長く、不貞行為の回数も多い
- これまでの婚姻期間が長い
- 不倫・浮気相手に子どもを産ませていた
7.不倫の慰謝料が減額になるケース
上記とは対照的に、以下のような場合は不倫の慰謝料金額が相対的に下がる可能性があります。
- 不貞行為があった時点で結婚生活が事実上破綻していた
- 離婚せず婚姻関係を継続する
- 子どもがいない、いてもある程度分別のつく年齢に達している
- 不貞行為が家庭の生計や子どもの養育状況に特段の影響を及ぼしていない
- 不倫をした配偶者や不倫・浮気相手に慰謝料を支払う資力に乏しい
- 配偶者が既婚者であることを不倫・浮気相手が過失なく知らなかった
- 不倫していた期間が短く、不貞行為の回数も少ない
- 婚姻期間が短い
8.不倫の慰謝料請求を成功させるためのポイント

慰謝料の請求については当事者同士の話し合いで解決できれば良いのですが、現実はなかなかそうもいきません。相手方が話し合いを拒絶する、不倫したことを認めない、慰謝料支払いに応じないといったことは珍しくありません。そのため、当事者同士の話し合いだと解決までに時間がかかるおそれがあります。
そのような事態を防ぎ、慰謝料の請求を成功させるためのポイントについて解説します。
8-1 弁護士に相談・依頼する
不倫の場合、集めた証拠の有効性や請求しやすい慰謝料の金額などは、事案ごとに異なります。そのため、不倫の慰謝料を請求するときは不倫を始めとする男女問題のトラブル解決に多くの実績がある弁護士に相談することが成功の鍵です。
直接交渉では、相手方は口裏合わせした上で不倫の事実を否定してくる可能性もありますし、問い詰めるタイミングを誤れば証拠を隠滅されるかもしれません。最初から正しい行動をしないと、請求できるはずだった慰謝料が請求できなくなる、大幅に減額されるといったリスクがあります。
弁護士に相談することで証拠や慰謝料の相場などについてのアドバイスだけではなく、依頼者の代理人として相手方と慰謝料の支払いに関する交渉を行います。専門家である弁護士に依頼することで、単独で行うよりもより良い結果となるでしょう。
8-2 不貞行為の客観的な証拠を集める
不倫の慰謝料を請求するには、誰が見ても明らかな「不貞行為の証拠」と、「故意または過失の存在を示す証拠」が必要です。それぞれ、証拠として以下のようなものが利用できます。
| 不貞行為の証拠 |
|
| 故意または過失の存在を示す証拠 |
|
ただし、ご自身では決定的な証拠を得たと思っていても、内容や証拠収集のやり方によって、裁判では証拠として機能しないということもあり得ます。時間と手間を無駄にしないために、どのようなものが証拠として有効か、弁護士と相談しアドバイスを得ながら慎重に集めてください。
9.不倫の慰謝料請求をするときの流れ
不倫の慰謝料を請求するときは、決して感情的になってはいけません。弁護士と相談しながら然るべき手続きを冷静に、確実に進めることが重要です。以下では、不倫の慰謝料請求を成功させるためのポイントについて解説します。
9-1 弁護士に相談し、弁護士が直接交渉し、通知文書を送る
まずは弁護士に事実や証拠を余すことなく明らかにして、相手方が証拠を隠滅しないうちに今後の進め方を相談してください。
依頼を受任した弁護士は、証拠の状況などを踏まえ配偶者および不倫・浮気相手と直接の交渉を試み、慰謝料を請求できると判断する場合は通知文書を送付し慰謝料の支払いを請求します。
場合によっては内容証明郵便を使用することもありますが、内容証明郵便を送付したからといって相手に何らかの法的拘束力を持たせるものではありません。しかし、内容証明郵便の送付と併せて訴訟を提起することで、損害賠償請求の時効を中断させられます。
また、内容証明郵便は記載された内容を日本郵便に証明してもらえるため、慰謝料請求の意思表示をした事実の有無について相手方との水掛け論を防ぐ効果もあります。
9-2 簡易裁判所に調停を申し立てる
交渉しても相手方が慰謝料の請求に応じないのであれば、簡易裁判所に調停を申し立てることを検討します。
調停では調停委員とよばれる人が間に入り、離婚や慰謝料の支払いに関する話し合いを行います。調停委員が間に入ることで配偶者やその不倫・浮気相手と顔を合わせずにすむことから、冷静な話し合いが期待できます。もちろん、弁護士は調停に同席可能です。
調停で慰謝料の支払いについて合意がとれると、その合意内容について調停調書が作成されます。これにより、相手方が合意したはずの慰謝料が支払われない場合は財産の差押えなどの強制執行が可能です。合意に至らない場合は、裁判への移行を検討します。
なお、弁護士が代理人になる場合、夫婦間の離婚調停ではない限り、慰謝料請求のみ単独で調停を行うケースは実務上さほど多くはありません。
9-3 訴訟を提起する
調停が不調に終わった場合は訴訟を提起します。なお、弁護士が代理人になる場合は、ほとんどの場合、調停を経ずに訴訟提起を行います。
訴訟では、配偶者や不倫・浮気相手を被告として慰謝料の支払いを求めます。訴訟を提起すると、裁判所を介してやり取りが行われ、訴訟上の和解の成立、または判決の確定で決着します。
直接交渉や調停と同様に、訴訟したからといって満額の慰謝料を勝ち取れるわけではありません。
一方、訴訟が直接交渉や調停と異なる点は、お互いが納得できなくても最終的に裁判所の判決で結論が確定すること、判決が出るまで費用と期間が相応にかかることです。また、訴訟では証拠が一層重要視されるようになります。
10.不倫の慰謝料請求に成功した実際の事例

不倫の慰謝料請求について相談する弁護士を探すときは、男女問題の解決および実際に不倫についての慰謝料を獲得した実績のある弁護士を第一候補にすべきでしょう。弁護士法人ライズ綜合法律事務所では、これまでたくさんの方の慰謝料請求をサポートしてきました。実際の事例の一部をご紹介します。
10-1 夫婦関係の破綻を主張する夫から慰謝料を獲得
定年退職した夫の不倫を疑い夫を尾行した妻は、夫が見知らぬ女性とホテルに入るところを目撃しました。夫を問いただしたところ不貞行為を否定するばかりか「そもそも夫婦関係は破綻している」と主張し自ら離婚を切り出す始末です。
妻の依頼を受けた弁護士は、自分の主張を繰り返す夫と交渉した結果、慰謝料を獲得しました。
10-2 証拠を示し夫から慰謝料を獲得
友人から、夫が知らない女性とホテルに入っているところを目撃したとの話を聞いた妻は、夫を問いただしても事実を認めないため弁護士に相談しました。妻の友人は夫が女性とホテルに入る姿を写真に撮っていたため、弁護士はそれを証拠として夫と交渉を重ね、慰謝料を獲得しました。
10-3 妻の不倫・浮気相手から慰謝料を獲得
妻の不倫を友人から聞いた夫が妻を問いただしたところ、妻は不倫の事実を認め謝罪し不倫・浮気相手とは今後一切連絡を取らないことを約束したので、夫は婚姻関係の継続と共に妻を許すことにしました。
しかし、妻の不倫・浮気相手の男性をどうしても許せないため、慰謝料の請求について弁護士に相談。弁護士は交渉のみで妻の不倫・浮気相手の男性から慰謝料を獲得しました。
10-4 結婚した当初から関係が続いていた妻の不倫・浮気相手から慰謝料を獲得
結婚2年目の妻のスマートフォンに不倫・浮気相手からのメッセージが表示されており、妻を問いただしたところ事実が発覚。それも夫との結婚当初から相手の男性と関係していました。
夫と妻は同じ職場に勤務しているため、直接顔を合わせる気まずさもあり、弁護士に交渉を依頼しました。
話し合いの結果、お互い退職はせず、相手方からしっかりと慰謝料を受け取ることで解決。また、不倫・浮気相手と妻は今後一切会わないという約束を書面で取り付けることができました。
11.不倫での慰謝料請求に関するQ&A

不倫での慰謝料の請求は、要件が複雑です。「自分の場合は請求できる?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。ここでは、当事務所に相談者様からよく寄せられる質問をピックアップし、回答を紹介します。
慰謝料請求の条件に関しては以下の記事でも詳しく紹介しています。こちらも参照してください。
慰謝料請求できる条件は?金額の相場や請求方法、注意点を解説
11-1 不倫の慰謝料を配偶者と不倫・浮気相手に請求できますか?
不貞行為への賠償は配偶者と不倫・浮気相手の双方が責任を負うため、配偶者と不倫・浮気相手の両方に慰謝料を請求できます。
ただし、2人に請求するからといって金額が倍になるわけではないため注意してください。例えば、慰謝料300万円が相当なケースでは、2人に請求する場合でも総額は300万円です。
なお、不倫のほかに暴力やモラハラ、借金などを受けているケースもあるかもしれません。この場合、不倫の慰謝料とは別件に当たるため二重取りにはなりません。
11-2 ダブル不倫の場合も慰謝料を受け取れますか?
自分の配偶者と不倫・浮気相手がどちらも既婚者である、いわゆる「ダブル不倫」の場合でも、慰謝料の請求は可能です。ただし、離婚しない場合は注意が必要です。
ダブル不倫においては、自分側の夫婦と不倫・浮気相手側の夫婦で慰謝料を請求し合う構図になります。離婚しない場合はお互いの家計や共有財産に影響することも多い傾向です。
離婚を前提としない場合は、夫婦間で「お互いに慰謝料を請求しない」という形で和解することも選択肢の1つとなります。
11-3 不倫・浮気相手が夫の子どもを妊娠した場合は慰謝料を多くもらえますか?
不倫・浮気相手が夫の子どもを妊娠した場合、一般的には被害者である妻の精神的苦痛が大きいと判断されます。そのため、相場よりも高額な慰謝料を請求できる可能性があるでしょう。
ただし、慰謝料の請求の可否や金額が決まることには、以下のようにほかの要素も関係してきます。
まず、慰謝料を請求できるのは不倫関係にあったときから20年、もしくは不倫の事実を知ってから3年以内です。また、既に夫と別居して3年~5年経過していると、裁判では「婚姻関係が破綻している」と判断され、慰謝料を請求できない可能性があります。(単身赴任などによる別居は例外)。
夫と離婚しない場合も、不倫によって受けた損害が小さいと判断される傾向にあり、慰謝料が離婚する場合より低額になることが一般的です。
12.単独での慰謝料の交渉はトラブルの可能性も!弁護士に相談して早期の解決を目指そう
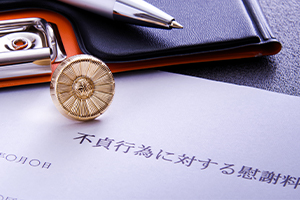
不倫は配偶者とその不倫・浮気相手の不法行為であり、その被害者は慰謝料を請求する権利があります。
一方で、慰謝料請求は必ずしも成功するとは限りません。また、民事紛争であることから特有の交渉技術や法的知見が必要になりますので、ご自身単独で請求するよりも専門家である弁護士にお早めに依頼した方がより良い結果となるでしょう。
不倫の慰謝料を請求するときは、弁護士法人ライズ綜合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人ライズ綜合法律事務所は、累計30万件以上の法律相談実績があります。不倫慰謝料請求の専門チームやADP認定夫婦カウンセラー®の資格を持ったスタッフが在籍しており、ご相談者様に寄り添った対応を提供しております。
また、全国からご相談を承っており、着手金および相談料は0円です。弁護士法人ライズ綜合法律事務所はあなたにとって最良の結果を目指してサポートします。不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
このページの監修弁護士
弁護士
三上 陽平(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)
中央大学法学部、及び東京大学法科大学院卒。
2014年弁護士登録。
都内の法律事務所を経て、2015年にライズ綜合法律事務所へ入所。
多くの民事事件解決実績を持つ。第一東京弁護士会所属。