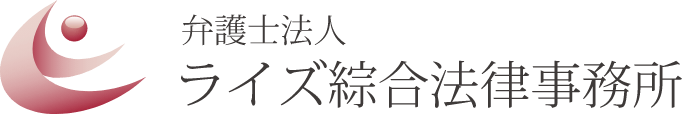1.ブラックリストとは

借金に関する情報を調べていると、「ブラックリスト」という言葉が時折現れますが、実はブラックリストといったものは存在しません。
一般的には、後述の個人信用情報に「金融事故情報」が存在することを、ブラックリスト入りしているといいます。金融事故情報があると、信販会社や金融機関などがサービスを提供することを敬遠するため、このような俗称がついたとされています。
日本では、個人に対する借入や信販契約などの信用情報の履歴を記録することが義務づけられ、自分のローンに関する状態を金融業者や消費者金融に隠すことはできません。
2.個人信用情報とは
個人信用情報は、簡単にいうとクレジットやローンに関する履歴のことです。クレジットカードの支払い履歴や、金融機関のローン、ショッピングの分割払い(信販契約)などを利用すると、その内容が記録されます。
履歴が残る情報は、新規契約やその内容、返済状況など多岐にわたります。個人信用情報のなかでも、滞納・代位弁済・官報情報など、信用に対する悪影響が大きいものが「金融事故情報」です。金融事故情報が記録されている状態のことを、俗にブラックリスト入りと呼んでいます。
3.日本の個人信用情報機関とは
日本には、個人の信用情報を管理する三つの個人信用情報機関があります。国内の金融機関や信販会社など、金融系のサービスを提供している機関は、業種に応じていずれかに加盟しなければなりません。
【日本の個人信用情報機関】
| 加盟者 | |
|---|---|
| CIC(株式会社シー・アイ・シー) | クレジットカード会社や信販会社、農協など。 |
| JICC(株式会社日本信用情報機構) | 消費者金融が主。そのほか信用金庫など。 |
| KSC(一般社団法人全国銀行協会) | 都市銀行・地方銀行・インターネット銀行など各種銀行が多い。 |
なお、必ずしも上記の表のように業種ごとに加盟先が明確に分かれているわけではありません。例えば、銀行がKSC以外の個人信用情報機関に加盟していることもあります。確実に加盟先を知りたい場合は、各会社の公式情報や問い合わせで確認するようにしましょう。
4.なぜブラックリストはあるのか

個人信用情報は、個人と金融サービスを提供する会社の間での、適正な取引のために存在します。
個人信用情報を閲覧するのは、おもに金融機関などサービスの提供側です。個人の経済的信用と、貸し付けに対するリスクがどの程度か、といったことを確認するために利用されます。
個人信用情報に問題があると、返済能力に不安があるのではないか、と判断されがちです。「一度ローンに関して何か問題を起こした人は、返済能力に問題があるのではないか」と懸念され、サービス提供側にとっては「リスクの高い契約相手」といえるでしょう。貸し付けたお金が返済されないと赤字となってしまうからです。
このように、個人信用情報は加盟会社のリスク管理のために存在し、十分な返済能力がある人と円滑に取引するために利用されます。
5.ブラックリストに載る条件
個人信用情報に事故情報が記録される「ブラックリスト入り」は、誰でも起こるわけではありません。どのような場合にブラックリストに載るのか、条件とポイントを紹介します。
5-1 支払いの滞納や複数回の延滞がある
お金を借りた際に期限通りに返済できない延滞や滞納をすると、ブラックリストに載ることがあります。例えば、過去にローンを長期間滞納したり、現在進行形で滞納したりしていると、ブラックリスト入りしているかもしれません。
お金を返せない人に新たに貸し付けても、回収できない可能性があるため、新規契約を敬遠されることとなります。
5-2 任意整理や自己破産などの債務整理をした
過去に債務整理をしている場合も、ブラックリストに載っている可能性があります。
債務整理とは、法的に借金を減額・免除する手続きの総称です。「任意整理」「民事再生(個人再生)」「自己破産」といった言葉を聞いたことはないでしょうか。
債務整理は、債務の支払いを軽減できる反面、債権者からすると「通常の支払いができない」ことを意味します。そのため、債務整理の内容に応じた情報が、一定期間個人信用情報機関に登録されるのです。
例えば自己破産の手続きをした事実は「官報情報」として掲載され、手続き完了から約5年〜7年程度の間、事故情報が掲載されます。
5-3 保証会社によって代位弁済・保証履行された
保証会社によって代位弁済・保証履行が行われた場合も、ブラックリストに載ります。代位弁済や保証履行とは、お金を借りている人が返済できなくなった場合に、保証会社などの第三者が代わりに返済を肩代わりすることです。
個人信用情報には「保証履行」または「代位弁済」と登録されることになります。そのため、新規のクレジットカードの発行やローンを契約する際に個人信用情報を参照されると、過去に返済不能になったことが知られてしまうでしょう。
5-4 短期間に複数のローン申込みをした
短期間に複数のローンやクレジットカードの申し込みをしたときも、ブラックと見なされることがあります。
個人信用情報には申し込みの履歴も記録されるため、何社ものローンに次々と申し込んでいると、情報を参照した際に知られてしまいます。
消費者金融などのローンを多重利用していると「経済的に困窮している」と推測することが自然です。申し込みの情報自体は事故情報ではありませんが、連続で申し込んでいるとブラック扱いになる点に注意してください。
なお、住宅ローンに関しては複数社の仮審査を利用することが一般的なため、申し込みによってブラックリスト入りすることはありません。
5-5 過払い金請求をした
過去に違法な高金利で借り入れを利用している場合、現行の基準を超過して支払った部分が過払い金として戻ってくることがあります。過払い金請求には、ブラックリストに載るケースと載らないケースがあり、どちらに該当するのか確認が必要です。
過払い金で借り入れ残高を完済できる場合、ブラックリストには載りません。一方、払いすぎた分を残高の精算に充てても完済に至らない場合はブラックリスト入りします。
6.ブラックリストに載ったときの影響

ブラックリストに載ると、実生活にはどのような影響が出るのでしょうか。代表的なものを5例紹介します。
6-1 新たなローンの審査に通らなくなる
ブラックリストに掲載された状態では、ローンの審査に通らなくなる可能性があります。金融事故情報は、金融機関にとって返済能力の低さや経済的困窮を意味する記録です。審査の際に事故情報が見つかると、貸し付けのリスクが高いと判断されます。
これは消費者金融などが提供するフリーローンや小口の貸し付けだけではなく、ビジネスローンや住宅ローンなども該当します。ただし、国や自治体の借り入れ制度や職場の従業員貸付制度など、利用者を助ける目的のものでは、金融機関以外が主体となる貸し付けの場合は必ずしも制限されるわけではありません。
ローンの契約ができない間は、低価格のものを現金で購入したり、家族の名義で契約したりすることで対処が可能です。例えば、車を購入したい場合でも自動車ローンの契約ができないことが予想されるため、現金で購入できる範囲の中古車に絞って探す、といった工夫が必要になります。
6-2 クレジットカードの利用が止められる
クレジットカードを持っている状態でブラックリストに載ると、既存のクレジットカードが無効にされる可能性があります。
クレジットカード会社が個人信用情報を参照したタイミングでブラックリスト入りが発覚するため、無効になるタイミングは発行元によってさまざまです。数日後に無効になるケースのほか、有効期限更新のタイミングで使えなくなるケースもあります。
既に持っているクレジットカードが無効になるのか、いつ止められるのか、そのまま使用できるのか、クレジットカード会社によって対応は異なるため注意してください。
ただし、クレジットカードは利用できなくても、即時引落のデビットカードやプリペイドカード、スマホのキャリア決済などは利用できます。ETCカードについてもプリペイドタイプのものがあるため、こうした代替手段を活用できないか検討してみてください。
6-3 賃貸契約ができない場合がある
ブラックリストに載っていると、賃貸契約ができない場合があります。正確には、賃貸契約そのものが制限されるわけではないのですが、契約に伴う保証契約の締結ができない可能性があるのです。
賃貸保証会社のなかには、個人信用情報を参照できる会社も多くあり、契約時に経済的な信用を確認されます。ブラックリストに載っていて、リスクの高い顧客と判断されると、保証契約を断られることがあるのです。
賃貸契約では、保証会社の代わりに家族や親しい人を連帯保証人に立てることで、契約できることもあります。
また、賃貸保証会社を選べる場合、個人信用情報機関に加盟していない賃貸保証会社と契約することでも、入居審査に通る確率を上げられます。UR賃貸や公営住宅などを検討するのも良いでしょう。
6-4 携帯電話・スマホ端末の分割購入ができない
携帯電話・スマホの端末代金を分割払いするときも、支払いが滞るとブラックリスト入りする可能性があります。
実は、端末代金の分割払いは「個品割賦販売契約」という信用購入の一種です。携帯電話サービスの会社が一時的に代金を立て替える代わりに、個人信用情報への履歴の記録が義務付けられます。
携帯電話・スマホの端末は高額なものも多く、分割払いによる契約も一般的です。気軽に利用できる反面、借金に近い性質のものなので滞納時のリスクも相応にあります。計画的に利用するよう注意しましょう。
端末を購入する際は、分割払いでなくても支払える機種を一括払いで購入する、中古の端末を検討する、プリペイド式やレンタル携帯を使うといった対処が必要になります。
6-5 ローンの保証人になれない
ローンの保証人になりたい場合も、事故情報の存在が発覚すると審査で落とされてしまう可能性は高いでしょう。
例えば、夫を契約者に、自分を連帯保証人として住宅ローンを契約したい場合でも、ブラックリストに載っていると多くの場合審査で落とされます。こちらも、金融機関が主体ではなく審査の際に個人信用情報を参照しない場合はこの限りではありません。
7.ブラックリストに載っているかどうか確認する方法

ブラックリストに載っているかどうか確認するには、個人信用情報機関の本人開示制度を利用することが最も確実です。
日本には3つの個人信用情報機関があり、利用したサービスの加盟先に情報が登録されることになります。例えば、利用した消費者金融がJICCの加盟会員なら、取引情報はJICCが管理しています。情報開示は原則本人のみ可能ですが、代理人や法定相続人による手続きも可能です。
カード会社や消費者金融などの会社がどの機関の会員かは、公式ホームページの利用規約などに記載されていますので確認してみてください。ここでは、各個人信用情報機関の情報開示の手続きを紹介します。
7-1 CIC
CICは、クレジットカード会社や信販会社が加盟する個人信用情報機関です。情報開示の手続きはインターネットと郵送で行えます。
【CICでの情報開示の方法】
| インターネットで開示 | 郵送で開示 | |
|---|---|---|
| 開示までの期間 | 即時 | 申し込みから約10日で書面が到着 |
| 用意するもの |
|
|
| 手数料 | 500円 | 1,500円 |
| 支払い方法 |
|
|
なお、窓口での開示手続きは2023年2月に終了しているため、上記2つの方法のいずれかでのみ開示ができます。
7-2 JICC
JICCはおもに消費者金融が加盟しています。情報開示の方法や手数料は以下の通りです。
【JICCでの情報開示の方法】
| スマホアプリ | 郵送 | |
|---|---|---|
| 開示までの期間 | クレジットカード + 電話認証:数分~数時間 本人確認書類認証:最大5日 マイナンバーカード認証:1日~3日程度 |
申込み完了後5日~7日程度 |
| 用意するもの |
|
|
| 手数料 | 1,000円 | 1,300円 |
| 支払い方法 |
|
|
参考:
本人による開示申し込み(スマホ申込) | 日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関
本人による開示申し込み(郵送等) | 日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関
以前は窓口での開示にも対応していましたが、窓口での手続きは2024年10月に終了しました。現在はスマホアプリか郵送のどちらかを選択する必要があります。
7-3 KSC
KSCは全国銀行協会が設置、運営している個人信用情報機関です。情報開示の手続きはインターネットと郵送で行えます。
【KSCでの情報開示の方法】
| インターネット | 郵送 | |
|---|---|---|
| 開示までの期間 | 3営業日~5営業日 | 1週間から10日 |
| 用意するもの |
|
|
| 手数料 | 1,000円 | 1,679円~1,800円 コンビニによって異なる |
| 支払い方法 |
|
|
参考:
郵送による開示手続 | 本人開示の手続き | 一般社団法人 全国銀行協会
本人開示の手続き | 全国銀行個人信用情報センター | 一般社団法人 全国銀行協会
なお、KSCでは窓口での開示は受け付けていません。ご注意ください。
8.ブラックリストから情報を消すためには
ブラックリストは金融機関の利益のために存在するもので、情報を登録されている本人が希望したからといって消すことはできません。
ただし、各金融事故情報は一定期間経過すると消えるため、永久に残るわけではありません。登録が解除されるまで何年かかるかは、金融事故情報の種類や個人信用情報機関によって異なりますが、約5年〜7年程度です。
また、対象の貸金債権が時効を迎えたときや、情報が誤って登録されているときは手続きによって削除できるケースもあります。
9.ブラックリストに影響がないもの
ブラックリストに載ったからといって、全ての金融系サービスの利用や社会生活に影響が出るわけではありません。以下のものは、ブラックリストに載っても特に変化はありません。
- 金融機関の口座開設
- 携帯回線の契約(端末の分割払いは不可)
- 結婚
- 子どもの進学
10.ブラックリストでお困りのときは弁護士への相談がおすすめ

借金に困っていて、現在ブラックリストに載っている場合、弁護士に相談して解決することをおすすめします。
借金は、債務整理によって負担を軽くできる場合があります。例えば、任意整理をすれば月々の返済を減らして利息分が増えないようにできますし、個人再生で債務の金額を大きく削減することも可能です。債務整理をするとその情報が個人信用情報機関に記録されますが、借金の負担を軽減し生活を建て直せるようになるでしょう。
検討できる債務整理の方法は複数存在し、どのような解決策が自分に適しているかは人によって異なります。メリット・デメリットを知りながら比較するために、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
11.ブラックリストかどうかは個人信用情報機関で確認を
ブラックリストという名簿は実際には存在しません。しかし個人信用情報機関に事故情報が掲載されると、新規の契約を敬遠されることが多いため、俗に「ブラックリスト入り」しているといわれています。
ブラックリストに掲載されると、ローンやクレジットカードの利用ができなくなるといった悪影響が生じます。自分がブラックリストに載っているか不安な場合、今回紹介した開示請求の手続きを利用し、確認するのがおすすめです。
借金問題で悩んでいるのであれば、まずは弁護士に相談し、最適な解決方法を探ってみましょう。ライズ綜合法律事務所は、債務整理の専門知識を持つプロフェッショナルが多数在籍しております。「借金を減らしたい」「毎月の支払いを軽くしたい」このような場合は一度ご相談ください。
このページの監修弁護士
弁護士
三上 陽平(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)
中央大学法学部、及び東京大学法科大学院卒。
2014年弁護士登録。
都内の法律事務所を経て、2015年にライズ綜合法律事務所へ入所。
多くの民事事件解決実績を持つ。第一東京弁護士会所属。