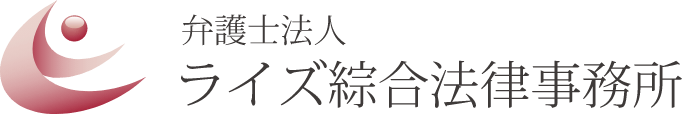借金の返済に追われ、個人再生を検討しつつも「本当に個人再生が自分に適しているのか」「デメリットはないのか」と不安を感じている方もいるでしょう。失敗した場合のリスクを考え、なかなか一歩踏み出せずに悩んでしまう方も少なくありません。
本記事では、個人再生を検討している方に向けて、デメリットとメリットの両面を整理し、事前に知っておきたい注意点を分かりやすく解説します。
【この記事で分かること】
- 個人再生(民事再生)の具体的なデメリットとメリットの比較
- 手続き中に起こりうるリスクや失敗した際の対応策
- 手続きにかかる費用相場と流れ
1.個人再生(民事再生)の概要
個人再生(民事再生)は、法的な手段で借金の整理をする債務整理手続きの一つです。裁判所への申し立てが必要となります。
個人再生では、現在ある借金の最大9割(通常8割)を削減したと仮定し残高を計算します。仮計算の結果に基づき完済までの再生計画案を作成し、予定通りに返済できれば削減した分の支払いは免除される仕組みです。
返済期間は原則3年、特別な事情があり許可を得れば5年に設定されるため、その期間で返済ができるようスケジュールを作成します。
※個人再生の減免割合について
債務の合計額(住宅ローン等は除く)が100万円~5000万円のいくらかによって、0%~90%まで減免割合が変動します(後述)。500万円~1500万円の場合は8割減免します。
1-1 自己破産との違い
自己破産は、個人再生と同じく裁判所に申し立てて行う債務整理の一種です。個人再生とは、免除される借金の金額と、手元に財産を残せるかどうかが異なります。
【自己破産と個人再生の違い】
| 自己破産 | 個人再生 | |
|---|---|---|
| 借金の削減割合 | 全額免除 ※一部対象外の債務あり | 一部免除(通常8割) |
| 財産 | 一定額以上の財産は原則全て失う | 残せる ※債務の削減額に影響する。(清算価値保障原則) |
自己破産と個人再生で迷ったときは、残したい財産の有無や、現実的な再生計画が立てられるかどうかなどを総合的に判断し、決定することとなります。
1-2 任意整理との違い
任意整理は、債権者(金融機関や消費者金融など)との交渉により、現在負っている債務の元本払いを認めてもらうなど、毎月の返済額を見直す債務整理手続きです。
個人再生との大きな違いは、手続き方法や削減額にあります。
| – | 任意整理 | 個人再生 |
|---|---|---|
| 借金の削減割合 | 将来の利息や遅延損害金をカット ※元本の削減は通常できない。 | 元本も含めて一律に削減される(通常8割) |
| 手続き方法 | 当事者間で協議 | 裁判所に申し立てる |
| 財産 | 残せる | 残せる ※債務の削減額に影響する。(清算価値保障原則) |
自己破産や個人再生と比べて元本額は減らせない一方で、簡略な手続きで支払いの負担を軽くできます。
2.個人再生(民事再生)の種類
個人再生(民事再生)には、申立人の区分によって大きく2通りの手続きが用意されており、それぞれ利用できる条件が異なります。
2-1 小規模個人再生
小規模個人再生は、個人事業者、会社員など、継続的に収入を得ている個人が対象となる手続きです。小規模個人再生の利用には以下の条件をどちらも満たしている必要があります。
【小規模個人再生を利用する条件】
- 住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であること
- 継続的に収入を得られる見込みであること
再生計画案を作成した後、債権者の同意を得る必要があります。反対が、債権者数の半数又は債権額の2分の1を超えた場合、不認可となります。
2-2 給与所得者再生
給与所得者再生は、会社員など給与所得者のみを対象とした手続きです。可処分所得額によって、最低弁済額が決まるという特色があります。利用には、以下の条件を全て満たす必要があります。
【給与所得者再生を利用する条件】
- 住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であること
- 給与が主な収入であること
- 継続的に収入を得られる見込みであること
給与所得者再生では、小規模個人再生とは異なり、再生計画案に対する債権者の同意は必要ありません。そのため、過半数の反対が予測される場合は、給与所得者再生を選ぶ必要があります。
しかし、給与所得者再生の場合は、法律に基づき可処分所得額(収入から最低限の生活費や税金などを除いた額)の2年分を算出し、この金額以上を支払わなければなりません。もともと、給与所得者は自営業者と比べると可処分所得額が多くなりやすく、収入の多い人、扶養家族のいない人などは、さらに多くなりやすいです。そのため、減免があまり得られないこともあります。
3.個人再生(民事再生)のメリット
個人再生(民事再生)の手続きにはどのようなメリットがあるのでしょうか。特に重要な4つのポイントを紹介します。
3-1 借金を減らせる
個人再生の最も大きな効果が、借金を大幅に削減できることです。
個人再生でいくら借金を減らせるかはケースバイケースですが、裁判所の基準として「最低弁済額」が設定されています。これは、個人再生で最低いくら借金を支払わなければならないか、借金の金額から目安を割り出したものです。
【個人再生手続きの最低弁済額(小規模個人再生手続きの場合)】
| 債務の金額 | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 全額 |
| 100万円以上500万円以下 | 100万円 |
| 500万円超1,500万円以下 | 総額の5分の1 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 300万円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 総額の10分の1 |
ただし、必ずしも最低弁済金額まで減額できるわけではありません。個人再生手続きにおいては、破産配当以上の額(清算価値)を弁済しなければならないという清算価値保障原則があります。そのため、処分できる財産が多い場合は、清算価値が最低弁済額を押し上げることになります。
【給与所得者等再生手続きの場合】
上記の表の金額と、清算価値の額と、自分の可処分所得額の2年分を比べ、最も多い額を弁済する必要があります。
「自分の場合はいくら減額できるか」を正確に知りたい場合、弁護士に相談して試算してみてください。
※参考:裁判所 – Courts in Japan.「個人再生手続き・受付相談Q&A集」,(参照2025-12-17).
3-2 住宅や車などの財産を残せる
自己破産と比較した際の大きなメリットが、財産を残して借金を整理できることです。個人再生では、配当手続きがないため、住宅や車などを強制的に処分されることはありません(清算価値に影響する場合はあります)。
特に、住宅は生活再建のための重要な財産です。仮に住宅ローンが残っている場合でも、住宅ローンを整理対象から除外する特例制度を利用できるため、家を失わずに済みます。新しく家を探す労力も必要なく、家族への影響を最小限にとどめられるでしょう。
3-3 返済期間中は利息が発生しない
借金をしている人にとって大きな負担となるのが「早く返済しなければどんどん利息が膨らんでしまう」という精神的な不安です。個人再生の手続きを利用すると、債務の金額は固定されるため、返済中の利息は発生しません。
これは返済期間が3年の場合でも、5年に延長された場合でも同じです。作成した再生計画通りに無理なく返済を続けることで、確実に借金を減らせます。
3-4 職業に関する制限がない
自己破産では、申し立てから免責許可決定が出るまでの期間に就けない職業があります。
【自己破産で制限の対象となる職種(一例)】
- 弁護士や司法書士などの士業
- 商工会議所や信用金庫の役員
- 生命保険の募集人
- 貸金業や質屋
- 警備員
個人再生では職業に関する制限がないため、上記の職業の人でも休職・退職は必要ありません。
4.個人再生(民事再生)のデメリット
個人再生(民事再生)は借金減額の効果が大きい反面、いくつかのデメリットもあります。個人再生したらどうなるのかという不安を解消するためには、事前にリスクや影響を正しく理解し、自分の状況に適しているのかを判断することが重要です。
ここでは代表的な注意点について解説します。
4-1 借金が全額免除にはならない
自己破産とは違い、借金が全額なくなるわけではない点が個人再生のデメリットです。個人再生では最大10分の1まで圧縮できるものの、最低弁済額を原則3年で分割返済する義務が残ります。そのため、手続き後も安定した収入が求められます。
また住宅ローン特則を利用して持ち家を残す場合、住宅ローンは減額されずそのまま残ります。
個人再生を選んだ場合のメリットとデメリットを比較する際は、圧縮後の返済額と住宅ローンを合わせ、無理なく支払える家計状況なのかがポイントとなります。返済が滞ると計画が崩れるリスクがあるため、家計全体での慎重な試算が必要です。
4-2 個人信用情報機関に記録される
個人再生のデメリットとして避けられないのが、信用情報機関への事故情報登録、いわゆるブラックリスト入りです。手続き後5~7年程度は記録が残るため、この期間中は新規のクレジットカードやローン契約、携帯電話の分割購入といった審査に通りにくくなります。個人再生を個人で行うデメリットとして、こうした生活への影響が生じる可能性が高いです。
しかし、これは借金に頼らず生活を再建する期間とも捉えられます。いつまで制限が続くかは機関によりますが、将来の計画に個人再生の影響がどのように出るのか、家族とも相談しておく必要があります。
4-3 官報に掲載される
個人再生には、国が発行する機関紙「官報」に氏名や住所が掲載されるというデメリットもあります。官報は、一般の方が日常的に読むものではありません。そのため、近所や職場に知られる可能性は低いですが、誰でも閲覧可能なため完全に秘密にはできません。
また掲載情報を元に金融業者からDMや郵便物が届くケースもあり、個人再生のリスクの一つといえます。ただし、掲載は手続き開始時など数回に限られるため、過度に恐れる必要はありません。
4-4 手続きが難しい
小規模個人再生などのデメリットとしてよく挙げられるのが、手続きが複雑で専門知識が必要であり、期間も長くかかる点です。裁判所への申し立てには、家計収支表をはじめとする様々な資料収集に加え、法的要件を満たした再生計画案の作成など専門知識が不可欠です。これを知識のない個人が自力で進めることは現実的ではありません。手続き期間も半年以上要し、その間は裁判所から収入・支出や再生計画の妥当性について厳格な審査を受けます。
いわゆる個人再生のデメリットとして手続きの負担は大きいですが、弁護士に依頼すれば複雑な処理を任せられます。個人再生の手続きを円滑に進め、借金減額を成功させるには専門家の支援が最善です。
4-5 収入が不安定だと利用しにくい
個人再生は、減額された借金を原則3年から5年かけて分割返済する手続きです。そのため、継続して返済を続けられる安定した収入があることが認可の必須条件となります。例えば、無職の方は原則として利用できません。
またアルバイトや派遣社員、完全歩合給などで毎月の収入に大きな変動がある場合には、裁判所に「履行可能性がない(返済を継続できない)」と判断され、不認可となるリスクが高まります。病気などで定職に就くことが難しいケースも同様です。
収入の安定性が厳しく問われる点は、柔軟な返済が難しい個人再生のリスクといえます。自身の雇用形態や収支で利用可能か、事前に確認が必要です。
4-6 財産を全て申告する必要がある
個人再生では、預金、持ち家、車、保険(解約返戻金)、有価証券など、保有する全ての財産を裁判所に申告しなければなりません。これは清算価値保障原則というルールにより、所有している財産の総額以上の金額を返済総額に設定する必要があるためです。詳細な資産開示はプライバシーの観点で抵抗があるかもしれませんが、避けては通れません。
もし財産隠しが発覚した場合、不認可や手続きの廃止となるだけでなく、詐欺再生罪などの刑事罰に問われる可能性もあります。個人再生のデメリットとして、厳格な財産調査が行われる点は理解しておく必要があります。
4-7 ある程度の費用負担が必要となる
個人再生を申し立てる際は、裁判所費用と弁護士費用を合わせて一般的に50万~85万円程度の費用がかかります。借金の負担を減らすための手続きとはいえ、経済的に困窮している中で一時的にまとまった費用が必要になる点は、大きなデメリットといえます。
ただし、この費用は一括で支払う必要がないケースがほとんどです。多くの弁護士事務所では分割払いに対応している他、要件を満たせば法テラス(日本司法支援センター)の費用立替制度も利用可能です。目先の費用負担だけで諦めず、将来的に借金が大幅に減るメリットと比較して検討することをおすすめします。
※費用の目安は2025年12月16日時点の情報です。
5.個人再生(民事再生)の費用相場
個人再生(民事再生)の手続きにかかる費用は、大きく分けて「弁護士に支払う報酬」「裁判所へ支払う手数料等」の2種類があります。管轄の裁判所や弁護士事務所によって詳細は異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。
| 内訳 | 金額目安(税込) |
|---|---|
| 裁判所に支払う各種経費 ・申立手数料 ・官報公告費 ・予納郵券(郵便切手代) を含む |
~5万円 |
| 予納金(個人再生委員への報酬) ※個人再生委員が付いた場合 |
15万~20万円 |
| 弁護士に支払う報酬 | 40万~60万円 |
| 合計 | 50万~85万円程度 |
※費用の目安は2025年12月16日時点の情報です。
支払いについて不安がある場合、初回の相談の際に概算の費用を確認してみましょう。費用と削減できる借金の見込みを確認した上で、依頼するかどうか決定してください。
6.個人再生(民事再生)の流れ
弁護士に個人再生(民事再生)を依頼する場合、準備や手続きはどのように進めるのでしょうか。完了までの流れをみてみましょう。
6-1 弁護士に相談する
まずは、法律事務所に相談の上、依頼先の弁護士を決めて解決までのおおまかな方針を決定します。
相談前の準備として、まずは今ある借金の詳細をまとめておきましょう。「どこに」「いつ」「いくら」借りたかを、簡単なメモでよいので整理しておきます。記憶があいまいなときは、借入先の利用履歴や銀行口座の明細などを確認してください。
「借金が多いので正直に話すのが恥ずかしい」と感じるかもしれませんが、全て提示しなければ正確に手続きできません。
ライズ綜合法律事務所の場合、弁護士は多重債務者の方と日常的に関わっており、相談者の方のそうした心情もよく理解しています。安心してご相談ください。
6-2 過払い金がないか確認する
過去に利息制限法の上限を越えた金利で返済していた場合、払い過ぎているお金がないか確認し、必要に応じて借金の金額を再計算します。
2010年6月に貸金業法が改正されるまで、貸金業者による上限を超過した金利での貸付が横行していました。そのため、その時期に借入を行っていた場合、払い過ぎていた分の利息が返還される可能性があります。
過払い金が発生していると借金がゼロになったり、残高の一部と相殺して借金を減額したりできます。ただし、過払い金の請求には、借入時期や経過年数の条件があるため注意が必要です。詳細は以下の記事を参照してください。
▼債務整理をしながら過払い金請求は可能?両者の違いや成功の秘訣とは
6-3 裁判所に申し立てる
借金の金額や借入先が確定し、準備が整うと管轄の裁判所へ申し立てが行われます。こちらは担当の弁護士が行うため、依頼者がやることは特にありません。その後、約1カ月で本格的に個人再生の手続きが開始します。
6-4 裁判所から銀行や金融機関に債権届出書が送付される
手続きの開始後、裁判所では個人再生に伴う財産の調査や履行テストが始まります。
履行テストとは、債務の弁済ができる経済状況かどうかを、実際に債務者に返済させて確認するものです。裁判所にもよりますが、再生計画が認可されるまで、月に一度の支払いを6回程度テストするのが一般的です。
履行テストや調査の結果、個人再生が妥当と判断されると、各債権者に債権届出書が送付されます。これは金融機関や消費者金融が債権者として名乗り出て、配当を受けるために必要な書類です。
届出書が全てそろうと、対象となる債務の金額が確定し、再生計画案の作成に入ります。
6-5 再生計画案を作成する
弁護士によって、再生計画案の作成が行われます。
具体的には、債務の金額を所定の最低弁済額未満にならないよう仮計算して削減し、算出した金額を3年または5年で完済できるよう返済プランを立てていきます。
弁護士から、事前に無理のない支払い額の聞き取りがありますので、経済状況を考慮して、妥当な金額を考えてみましょう。
6-6 返済と個人再生が完了する
再生計画案の認可が決定すると、その内容に従って返済を開始します。再生計画通りに完済できれば、残りの債務は免除され、個人再生の手続きは完了です。
返済中に、やむを得ない経済状況の悪化などにより返済が難しくなった場合、裁判所に再生計画の変更の申し立てができます。変更が許可されれば、返済期間は最大2年延長されます。もし返済が難しくなった場合、弁護士に相談して対処法を検討しましょう。
7.個人再生(民事再生)をする上で考えられるリスク
個人再生は借金を大幅に減らせる有効な手段ですが、メリットばかりではありません。手続きの過程や認可後にはいくつかのリスクも潜んでいます。申し立てる前にこれらのリスクを正しく把握し、準備をしておくことがポイントです。
7-1 資料の準備で日々の負担が増す
個人再生の申し立てには、裁判所での厳格な審査を通過するために膨大な資料の提出が求められます。これが日々の生活において大きな負担となるリスクになるのです。具体的には、過去2年分などの通帳のコピー、給与明細、源泉徴収票、課税証明書、保険証券や解約返戻金証明書、車検証や査定書、退職金見込額証明書など多岐にわたります。
これらを集めるだけでも相当な労力ですが、最も負担となるのが家計収支表(家計簿)の作成です。申し立ての準備期間から手続き完了まで、半年から1年以上にわたり、毎月の収支を正確に記録し、提出しなければなりません。仕事や家事と並行してこの作業を継続する必要があり、精神的・時間的なストレスを感じる方は少なくありません。不備があると審査が長引く原因にもなるため、まめな対応が求められます。
7-2 再生計画案が認可されない可能性がある
苦労して準備をしても、提出した再生計画案が裁判所に認可されず、手続きが失敗に終わる可能性があります。不認可になる主な原因は、収入に対して返済計画が現実的でない(履行可能性がない)場合や、財産隠しや報告の矛盾が疑われる場合です。
また個人再生には清算価値保障原則があり、所有する財産の総額以上の金額を返済しなければなりません。この基準を満たさない計画案も不認可となります。弁護士のサポートがあれば回避できるケースが大半ですが、万が一不認可となった場合、準備負担が再発生し、自己破産など別の債務整理を一から検討し直す必要が出てきます。
7-3 返済が滞ると計画が廃止になる
再生計画案が無事に認可されても、そこで終わりではありません。計画通りに完済できなければ、途中で計画が廃止(取り消し)になるリスクがあります。返済期間は原則3年(最長5年)ですが、この間に支払いが滞ると、債権者の申し立てなどで手続きが廃止されます。廃止が決定した場合、減額された借金は全て元の金額に戻り、遅延損害金も加算されるので注意が必要です。
また、それまでに弁護士や裁判所に支払った費用も返還されません。一度廃止になると再度の個人再生は困難となる場合が多く、最終的に自己破産を選択せざるを得なくなるケースが多いです。完済するまで気が抜けない手続きであることを理解しておきましょう。
8.個人再生(民事再生)に失敗したときの対応
個人再生が不認可や廃止となって失敗した場合は、減額されるはずだった借金は全て元に戻ります。そのまま放置すれば、一括請求や給与の差し押さえといったように、生活が立ち行かなくなるリスクが高まるでしょう。最悪の事態を避けるため、個人再生に失敗した際の具体的な対応策について解説します。
8-1 自己破産へ切り替える
個人再生が頓挫した場合に、多く選ばれる選択肢が自己破産への切り替えです。個人再生は借金を減らして返済を続ける手続きですが、自己破産は裁判所に認められれば、借金の支払い義務が原則全て免除されます。そのため、収入が激減したり無職になったりして返済能力が完全に失われた場合でも、生活再建が可能です。
注意点は財産の処分です。持ち家を守りたいという理由で個人再生を選択した場合は、残念ながらその希望を叶えることは難しくなります。自宅や一定価値以上の車などの財産は管財人により処分・換価され、債権者への配当に充てられるためです。しかし、財産を失う代わりに借金はリセットされます。返済のプレッシャーから完全に解放され、ゼロから人生をやり直すための、国が認めた有力な救済手段といえます。
8-2 任意整理へ切り替える
「官報への掲載を絶対に避けたい」「どうしても特定の財産への影響を避けたい」といった強い事情がある場合は、任意整理への切り替えを検討します。任意整理は裁判所を通さず、弁護士が債権者と直接交渉する手続きです。個人再生のように厳格な財産処分のルールがないため、特定の資産を守りやすいというメリットがあります。
しかし、この選択肢はハードルが非常に高いのが現実です。個人再生は元本を大幅に減額する手続きですが、任意整理は原則として将来利息のカットにとどまり、元本は全て返済しなければならないからです。減額された個人再生の計画ですら返済が難しかった状況で、減額幅の小さい任意整理で完済できるケースは限定的です。実現できる可能性があるのは、親族からの資金援助が得られる場合や、極端な家計の見直しで返済原資を確保できる場合などに限られます。慎重な判断が必要です。
8-3 弁護士に相談して方針を決める
返済が苦しくなったり、不認可の可能性を感じたりした段階で少しでも早く弁護士に相談することが重要です。自己判断で放置し、給与差し押さえなどの強制執行を受けてからでは、取れる手段が限られてしまいます。
早めに相談すれば、状況に応じた柔軟な対応が可能です。例えば、病気やリストラなど予測できない特別の事情で返済ができなくなった場合は、裁判所に申し立てることで、返済期間(履行期限)を最大2年間延長できる可能性があります。これにより毎月の返済額を下げ、計画を維持できるかもしれません。
また、これ以上の返済が不可能と判断されれば、速やかに自己破産へ移行したり、生活保護などの公的支援につなげたりするアドバイスも受けられます。専門家とともにその時点での最善の再建プランを練り直すことが解決への近道です。
9.個人再生(民事再生)で借金を減らそう!まずは弁護士に相談へ
個人再生(民事再生)は、事故情報の登録や官報への掲載といったデメリットがありますが、持ち家を守りつつ借金を大幅に減らせるという大きなメリットもある手続きです。自身にとってメリットとデメリットのどちらが大きいかを考えて、個人再生をするか検討すると良いでしょう。
しかし、複雑な要件やリスクを考慮しつつ、自分の状況で本当にメリットが上回っているかを一人で判断するのは容易ではありません。少しでも不安を感じた場合には、まずは弁護士などの専門家の視点を借りることが解決への近道です。
ライズ綜合法律事務所は、月間4,000件かつ年間5万件を超える豊富な相談実績を誇ります。何度でも相談は無料で、電話やメール、LINEでの問い合わせにも対応しています。
一人で抱え込まず、まずは無料相談であなたに合った解決策を見つけてみませんか?まずはお気軽にお電話ください。
【ご相談専用フリーダイヤル】
0120-657-001(9:00-21:00土日祝も受付中)
このページの監修弁護士

弁護士
久松亮一(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)
東京大学法学部、及び法政大学法科大学院卒。
2012年弁護士登録。
弁護士歴10年以上の知見を活かし、法律の専門家として、債務整理、慰謝料請求・立ち退き問題など、同事務所が取り扱う幅広い法律問題に従事している。