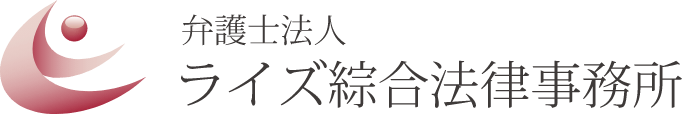1. 立退料の相場はいくら?相場算定・内訳・成功交渉の具体ポイント
大家都合での退去を求められたとき、「いくらもらえるのか」は借主にとって最も気になる部分です。相場の理解と自分のケースに合った交渉の準備が重要になります。
1-1 実態からみる相場感 ― 家賃の6〜12ヶ月分が基本
実務では、一般的な賃貸住宅において家賃の6〜12ヶ月分が相場として押さえられています。例えば月額家賃15万円であれば、およそ90〜180万円が相場です。
これは単なる目安ではなく、立退料として補償されるべき費用の合計がちょうどそのレンジに収まるからです。具体的には以下の要素が含まれています:
- 引越し代・荷造り費等の実費
- 新居契約に伴う敷金・礼金・仲介料などの経費
- 移転後の家賃アップ分(家賃差額補償)
実際にはこれに加えて、精神的な負担や営業損失なども考慮の対象になります。
1-2 自身のケースで金額に説得力を持たせる方法
-
補償項目を整理し、各々金額を見積もる
家賃差額が月2万円、補償期間を24ヶ月とすれば48万円、引越し20万円・契約費30万円を加えると100万円近くに。月額家賃15万円である場合、家賃換算では約6~7ヶ月分相当になります。 -
補償内容の合理性を明示する
差額の算出根拠や見積書・契約書などの資料を示すことで、「○ヶ月相当の補償根拠」が明らかになります。 -
相場の“範囲”を交渉材料にする
提示された金額が相場の下限を下回るようでしたら、「妥当な最低額」の説明を求めるべきです。逆に、自身の希望する金額が相場の上限を超える場合には「なぜその額が必要なのか」を確認した上で、合意形成を目指しましょう。 -
希望額は高すぎず低すぎず
相場の中間〜上限付近を目安にしつつ、自分の事情が反映されていること(例:子どもの転校費用、身体的負担など)を交渉の根拠として加えると説得力が増します。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 証拠の提示 | 見積書、家賃相場資料、契約書を用意 |
| 根拠ある説明 | 「家賃差額×補償期間+実費」で妥当性を示す |
| 相場との比較 | 6〜12ヶ月の範囲に照らした合理性を提示 |
| 柔軟な交渉姿勢 | 理由を説明し、視点の相違を防ぎながら交渉する |
こうした準備をしておくことで、何の根拠もない「ノー」と言われる状況を避け、納得できる条件へ導きやすくなります。提示額が基準に満たない場合は、文書で理由や根拠の開示を求め、その後必要に応じて弁護士など専門家に相談することをおすすめします。
次章では、立退料の相場の目安を掘り下げていきます。
2. 相場の目安:物件の用途に応じて範囲は異なる

立退料の金額は、一律ではなく、住居・事務所・店舗などの用途に応じて変わります。以下に各用途で目安となる範囲を整理しました。
2-1 住居タイプの場合:家賃数ヶ月〜1年分程度を目安に
一般的な賃貸住宅での退去では、提示される立退料は「家賃の数ヶ月から半年〜1年分程度の幅」で落ち着くケースが多いです。これは、引越し費用・契約関連費用・家賃差額などを合算した額がこの範囲に収まることが多いためで、実際には100〜200万円ほどで妥結されることも珍しくありません。
2-2 事務所・店舗利用ではより広い幅に
事務所利用では設備移転や業務に伴う調整費用などが追加されるため、「家賃の1年〜3年分程度」の相場となることが多いです。
一方、店舗ではさらに業種や売上損失、リピーター客を立て直す費用なども影響し、数百万円〜千万円を超える高額補償が認められる場合もあります。
2-3 自分のケースで考えるためのポイント
- 大まかな範囲を確認する:住居なら数ヶ月〜1年、事務所は1〜3年、店舗はさらに広い範囲というイメージを持つとよいでしょう。
- 自分の事情に応じた補償項目を整理する:引越し・契約費用、業務中断のコストなどを具体的に洗い出し、合計額と比較します。
- 提示額をこの範囲と比較する:「この金額では不十分」と思う場合は、どの項目が欠落しているか確認し、根拠を求めましょう。
立退料は、物件の種類によって大きく目安が変わります。住居タイプなら比較的低め、事務所や店舗では大きな幅で高額になる傾向があります。あなたのケースで納得できる交渉にするためには、目安を把握しつつ、自分の補償項目に合った具体的な準備が欠かせません。
3. 立退料の算出方法:収益還元方式・内訳方式・相場方式の比較
3-1 比較しやすい3つの算出方法
立退料の算定には「どの方法を使うか」で大きく金額が変わります。主に用いられる3方式の違いと、それぞれの特徴を整理しました。
収益還元方式(差額賃料還元方式)は、移転先と現在の賃料差に注目し、将来の補償額を現在価値に換算する計算法です。具体的には、「差額×複利年金現価率」で算出されるのが一般的で、現実の生活費を基に補償額を数値化できる点が利点です。
割合方式は土地+建物の価格に、借地権割合や借家権割合を掛けることで借主の利用権を評価する方法です。地域によっては標準で30%などが目安となり、一定の計算根拠を示せるのが利点です。
収益価格控除方式は、「物件を自用したときの価値」と「借家としての価値」の差分を補償金とする方法です。実際に貸すことで生じる価値の低下分を補填する考え方です。
比準方式は、実際に取引された借家権の事例価格を参考に、その物件に類似した事例との比較倍率を掛ける算定法です。ただし、借家権単独の取引が少ないため、現実にはあくまで補足的な位置づけです。
3-2 実際の交渉に強いのは〇〇方式?
一般的に、実務で支援しやすく賃借人にも分かりやすいのは 収益還元方式と割合方式です。
前者は「家賃差額×補償期間」の考え方に近く、交渉の際に金額の根拠を明示しやすく、家賃差額補償や引越費用などと一緒に提示すると説得力が高まります。
後者では、借家権割合を用いた理論的根拠を示せるので、特に長期間住んでいた借主の権利価値を主張する際に有効です。
収益価格控除方式や比準方式は複雑な評価を求められるため、実務では収益還元方式または割合方式を併用して補償額を構築するケースが多く見られます。
3-3 押さえておきたいポイント
- 算式や方式を丸暗記する必要はなく、自分のケースに合った実費と損失補償を「算式で示せる」ことが重要。
- 家賃差額に補償期間を掛ける収益還元方式は、交渉資料として非常に使いやすい。
- 借地権割合を使った方式は、借主としての権利価値の裏付けに有効。
- 複雑すぎる方法を複数持ち出すより、「根拠を示せる一方式+実費項目」の組み立てが、交渉成功のカギになります。
これらの算出方法を理解し、あなたのケースに合った算式や根拠を持って交渉に臨むことで、納得できる条件を引き出す確率が格段に高まります。
4. 詳細な内訳:立退料に含めるべき費用項目
立退き交渉で受け取る立退料は、単に「家賃●ヶ月分」ではなく、賃借人が被る損失や負担を合算した金額で構成されます。以下は主な構成要素です。
4-1 実費補償部分:家賃差額・新規契約金・引越し費用
まず基本となるのは、以下のような実費項目です:
- 家賃差額補償:現在の家賃と移転先物件の家賃差額×補償期間で算出。相場として1~3年分程度が交渉材料になります。特に現在の家賃が相場より低い場合、差額は大きくなる傾向があります。
- 新規契約金:敷金・礼金・仲介手数料などで、通常は「家賃1~2ヶ月分」の範囲で認められやすいです。
- 引越し費用:荷造り、搬出・搬入、清掃までの実費。領収書や見積書をもとに請求可能です。
4-2 その他補償部分:迷惑料
- 迷惑料(精神的負担):通学・勤務環境の変化や慣れた生活から離れるストレスを補償対象とする交渉もあり得ます。
4-3 事業用物件に特有の項目:営業補償
店舗や事務所の場合は、事業に関わる費用も含められます:
- 休業補償:移転期間中に失った売上や必要経費(家賃・人件費)を基礎とし、その期間と利益額に応じて算定されます。
- 営業補償(顧客離脱など):常連顧客の減少などに伴う損失も交渉に含めるケースがあります。
- 主に家賃10万円程度の店舗で、営業補償を含めると1,000万~1,500万円の立退料が認められる裁判例もあります。
4-4 交渉に向けた具体対応策
| 費用項目 | 準備すべき証拠や資料 |
|---|---|
| 家賃差額 | 周辺の同条件物件の相場データ |
| 新規契約金 | 不動産会社発行の見積書または領収書 |
| 引越し費用 | 引越し業者の見積書・領収書 |
| 迷惑料 | 通学・通勤時間の変化などを文章化 |
| 営業補償 | 過去の売上データ、休業日数、経費一覧など |
提示された金額がこれらに達していない場合は、「具体項目の根拠」を文書で照会し、必要に応じて専門家(弁護士や自治体相談窓口)の支援を受けましょう。
立退料の内訳を明確にし、「自分の被った損失を具体的に証明する」ことが、交渉を優位に進め、納得のいく条件に近づくための鍵です。次章では、こうした準備を前提にできる「交渉の進め方と専門家活用」をご紹介します。
5. 立退料交渉を成功させる秘訣:準備・資料・専門家活用

賃貸借で退去を求められた際、交渉を有利に進めるには、確実な事前準備と専門家の助力が不可欠です。特に判例を根拠に補償要求を裏付けることで、相手に説得力を持たせることが可能となります。
5-1 補償根拠を明確にして説得力を持たせる資料準備
まず以下の資料を整理してください:
- 家賃差額の計算:現住と代替物件の家賃差額×補償想定期間(1〜2年)の根拠として、周辺相場や不動産業者の見積を準備。
- 実費証明資料:引越し費用、敷金・礼金・仲介料などは見積書・領収書で整理し、「必要な補償額」であることを明示。
- 損失補填の根拠化:例えば通勤負担増や高齢の健康悪化などは「迷惑料」として可能な限り事実と数字でまとめ、交渉用の資料として整えましょう。
これにより、「家賃●ヶ月分」などの曖昧な表現ではなく、項目別に裏付けた根拠ある合計金額として提示できるようになります。これは相手にも納得されやすい形です。
5-2 判例を活用した交渉での説得力強化
以下の判例は、交渉を進めるうえで大きな説得材料になります。
- 事件番号:昭和41(オ)1005/判決日:昭和46年11月25日/裁判所:最高裁第一小法廷
老朽化店舗を対象に、建替えを要する等の事情があるほか、貸主が立退料300万円もしくはこれと格段の相違のない範囲内で裁判所の決定する額の立退料を支払う旨の意思を表明し、これと引換えに家屋の明渡を求めている場合において、裁判所は、500万円の立退料の支払と引換えに家屋の明渡請求を認容することは相当であると判断しました。 - 事件番号:平成2(オ)216/判決日:平成3年3月22日/裁判所:最高裁第二小法廷
建物明渡請求で立退料提供と引き換えで明渡請求が認められた判例です。建物賃貸人が解約申入後に立退料の提供を申し出て、または、解約申入時に申し出ていた金員からの増額を申し出た場合においても、かかる提供または増額に係る金員を参酌して解約申入れの正当事由を判断することができるとしました。
これらの判例は、「補償意思+具体的補償額の提示」が、交渉で相手に圧力をかける有効な材料になることを示しています。「家賃6ヶ月」など曖昧な提示額ではなく、裁判所に認められた実例として交渉資料に活用できます。
5-3 成功に導く交渉ステップ
| ステップ | 対応策 |
|---|---|
| 資料準備 | 家賃差額・見積書・補償項目を整理しファイル化 |
| 判例活用 | 上記2判例を交渉根拠として資料に添付 |
| 専門家相談 | 弁護士に資料と補償案の妥当性をチェック依頼 |
| 合意書作成 | 支払条件・時期などを文書化し、後のトラブルを防止 |
交渉成功には、「自分の被る損失を説明できる資料」と「判例を根拠とした補償提案」、そして「専門家によるチェック」が一体となって働くことが重要です。これにより、賃借人として納得できる条件を引き出しやすくなり、最終的に感情ではなく合理的な基準に基づいた合意が得られる可能性が高まります。
6. Q&A:よくある疑問と対策(契約違反・定期借家・自己使用など)
退去を求められた際、多くの借主が「自分はどうすべきか」と悩む質問をよくいただきます。以下に具体的な疑問と対応策をQ&A形式で整理しました。
6-1 契約違反で解除されたら立退料は出ないの?
はい。長期の賃料滞納や無断転貸など借主側に重大な契約違反がある場合、貸主は賃貸借契約を解除できます。この場合、借地借家法28条は適用されず、立退料の提供を求めることができません。解除後はただちに建物を明け渡す義務が生じ、不法占拠は遅延損害金の対象にもなります。
6-2 定期借家契約って?更新前に退去しなきゃいけないの?
定期借家契約とは、期間満了で契約が確定的に終了する契約です。法的には更新がなく、そのため借主は期間満了日までに退去に応じる義務があります。借地借家法28条は適用されず、立退料請求の提供を求めることはできません。定期借家契約の成立については、口頭または賃貸借契約書のみでは不十分で、「定期借家」である旨を別途書面で交付されていることが要件です。
6-3 自己使用や建て替えで退去要請が来たら?
貸主が「自己使用」や「建て替え」などを理由に退去を求めた場合、それは借地借家法が定める正当事由として認められる可能性があります。ただしその際には、立退料の提供、または、柔軟な再契約の提案が必要です。事前に根拠(老朽化状況や資金計画)と交渉内容の記録を用意し、補償条件の提示を文書で引き出すことが大切です。
6-4 高齢者や身体的に困難な事情があれば補償増額の交渉は可能?
はい。高齢や健康上の不安、転居が著しく困難な事情がある場合、慰謝料や迷惑料分として立退料の増額が認められる場合があります。不動産業者や弁護士も、高齢者対応が交渉材料となり得るとしています。
| 疑問 | 対策 |
|---|---|
| 契約違反で契約解除された | 素直に退去し、遅延損害金に注意 |
| 定期借家契約 | 書面の要件を確認 |
| 自己使用などの退去要請 | 正当事由と補償条件の確認が不可欠 |
| 高齢・通院・障害など | 事情を補償項目として整理し提出 |
契約状況や建物の用途によって「立退料が発生するかどうか」は大きく異なります。不安がある場合には、契約書類の内容チェックと資料準備、専門家への相談が非常に有効です。
7. まとめ
立退き交渉では、「正当事由の有無」だけでなく、生活再建に向けた具体的かつ合理的な補償が鍵になります。本記事では、補償内訳、相場、判例、交渉の進め方までを体系的に整理しました。
7-1 退去による損失への根拠ある補償を整える
立退料は単なる“家賃の●ヶ月分”ではありません。引越し・契約費用、家賃の差額、迷惑料や営業補償など賃借人が被る損失を具体的に補てんする金額です。
補償額を算定するには、実費根拠となる見積書や領収書を積み上げ、根拠ある補償額として提示できるかが重要です。補償対象の項目ごとに具体的かつ文書化された資料を準備し、自分の主張に裏付けを持たせましょう。7-2 判例や専門家を味方につけて交渉力を高める
判例では、補償意思や具体的補償額が立退き正当性に直結すると認められており、この考え方は交渉でも重要です。
また、判例によって「住宅で家賃数ヶ月分」「事業用では数百万円〜千万円以上」と補償額の実際が示されており、自らの希望額を根拠づける材料になります。専門家(弁護士・不動産)と連携して、これらの判例と補償の計算根拠を確認・補強しておくと、交渉時に相手が応じやすい条件を引き出しやすくなります。立退き交渉は、単なる合意ではなく「賃借人が生活や事業を再建できる条件」を確保するための交渉です。今お持ちいただいている資料や補償根拠、判例を整理・書面化し、専門家の力を活用することで、納得のいく退去条件を勝ち取りやすくなります。
このページの監修弁護士
弁護士
三上 陽平(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)
中央大学法学部、及び東京大学法科大学院卒。
2014年弁護士登録。
都内の法律事務所を経て、2015年にライズ綜合法律事務所へ入所。
多くの民事事件解決実績を持つ。第一東京弁護士会所属。