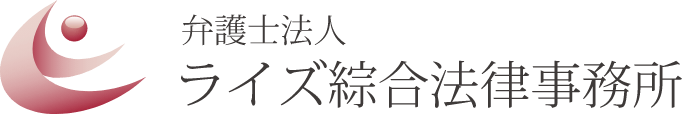立ち退き
2026/01/22
借地で立ち退き請求されたらどうする?法律と交渉のポイントを徹底解説

1.緊急導入:突然届く「借地立ち退き請求」に戸惑ったら
1-1 いきなりの立ち退き通知に揺れる気持ち
いつも通りの生活や事業を続けていたところに、不意に「立ち退き通知」が届くと、まず頭に浮かぶのは「なぜ自分が?」という戸惑いと「どこへ行けばいいのか」という不安です。借地人として築いた暮らしや業務が、一瞬で揺らいでしまうような衝撃を受ける方も多いでしょう。あなたの不安は決して小さくありません。こうした心情に寄り添いながら、冷静に次のステップを考えることが、大きな支えとなります。
以下、建物所有目的の土地賃貸借契約の場合を念頭に、解説をします。
1-2 正当事由があるの?法律に守られているの?
借地借家法では、建物所有目的の借地人を守るために、貸主が一方的に立ち退きを求めるには「正当事由」が必要とされています。すなわち、「貸主が自ら使いたい」「再開発の計画がある」など、社会的に納得できる事情がないと、借地人の退去を正当化することはできません。逆に、これらの事情が不明確であったり、立退料の提示がない場合、十分な交渉材料として権利を主張できます。正当事由の有無を判断することが、立ち退きに応じるかどうかの第一歩です。
1-3 契約のタイプで変わる立ち退き対応
借地人としての対応方針は、契約の形式によって大きく変わります。
- 普通借地契約では、貸主が立ち退きを求める場合、正当事由を満たさなければならず、借地人の権利がしっかり保護されています。
- 定期借地契約では、期間満了により契約が終了するため、貸主が立ち退きを求めやすい形になっているため、内容や手続きの妥当性が重視されます。資料によれば、契約のタイプに応じた対応は慎重に判断すべきとされています。
1-4 まず何から手をつける?借地人の最初の一歩
状況が許すのであれば、以下の点を順序立てて確認することから始めましょう:
- 通知の内容と形式を確認する:口頭よりも文書、特に内容証明郵便であるほうが通知があったことを示す意味で証拠として強力です。
- 契約書を確認する:普通借地契約か定期借地契約か、更新の有無や期限など、契約内容を再確認し、自分の法的立場を整理しましょう。
- 正当事由の有無と立退料の提示状況を調べる:貸主の立ち退き請求の理由が具体的か、補償が提示されているかは立ち退きを判断する重要な材料となります。
- 専門家への相談タイミングを見極める:今後の対応(交渉、合意、調停・訴訟)を見据えて、早期の相談があなたの主張を整理する鍵になります。
このように、通知を受けた借地人として、まずは冷静に事実関係を整理し、自分の法的立場や次の選択肢を見極めることが重要です。一人で抱え込まず、確かな根拠をもとに、次の対応を検討しましょう。
2.借地における立ち退き請求の法的背景
2-1 貸主が一方的に立ち退きを求められるの?法律上の枠組み
借地を貸主が一方的に返してほしいと言っても、法律上はそう簡単には返還請求は認められません。借地借家法第6条では、借地契約の更新拒絶や解約には「正当事由」が必要だと定められています。つまり、借地人であるあなたには、無意味に立ち退きを強いられることのないよう、法的に守られた権利があるのです。これは、ただ流れに任せて諦める前に、法律に基づいた冷静な対応の必要性を意味します。
2-2 正当事由とは?何を理由に立ち退きを認められるのか
具体的に「正当事由」とは以下の要素を総合的に検討したうえで認められます:
- 貸主・借地人の使用必要性の比較:貸主が本当に土地を必要としているのか、あなたにとっても不可欠な場所であるかどうかの判断が重要です。
- 賃貸借の経過内容:家賃滞納や契約違反があるか、信頼関係に亀裂があるかなど、過去の経緯も評価対象です。
- 土地の利用状況:借地人がどのような建物を建て、その土地をどのように利用しているかが考慮されます。①借地上の建物の存否、②借地上の建物の種類・用途、③建物の構造・規模、④建物の老朽化の度合い、⑤建物の面積、⑥建築基準法等の違反の有無、⑦借地人の利用状況が考慮要素になります。
- 立退料などの財産上の給付の提示:引越費用や代替物件の提示など、補償があるかどうかも重要です。
2-3 あなた(借地人)の事情が守られる仕組み
ただし、これらがすべて貸主に有利に動くわけではありません。むしろ、借地人としての事情が重視される場合があります。例えば、あなたにとって生活基盤や事業の拠点として不可欠な土地であること、移転によって受ける不利益が大きいと認められれば、正当事由として立ち退きを認められない可能性が高まります。
2-4 まず確認したいポイント:通知内容・契約種類・更新状況
立ち退き請求を受けたら、以下をチェックすることが重要です:
- 通知内容:どんな理由で、いつまでにどうすべきと書かれているのか明確にする。
- 契約の種類:「普通借地契約」か「定期借地契約」かで対応が変わります。普通借地契約なら正当事由が必要ですが、定期借地だと契約満了によって自動終了する場合もあります。
- 更新状況:契約更新が直近かどうかを把握しておきましょう。更新時期を逃すと、対応できる選択肢も限定されることがあります。
3.借地立ち退き請求で「拒否できるケース」とは?
3-1 借地人にも立ち退きを拒否できる法律上の理由があるから
借地契約を続けているあなたには、法律によって保護される権利があります。借地借家法の枠組みでは、貸主が一方的に立ち退きを求めることには制限があり、正当な理由(正当事由)がない限り拒否することが認められています。つまり、通知だけで慌てて対応する必要はなく、まずは自分の立場を確認することが大切です。借地人としての権利は、十分にあなたが行使できるものです。
3-2 立ち退きを拒否できる典型的なケースとは?
立ち退き申入れを拒否できる可能性が高い状況には、以下のようなものがあります:
- 貸主に差し迫った使用目的がない:自己居住や緊急な再開発など、緊急性が見られない場合、正当事由が弱くなる傾向があります。
- 借地人の居住・事業継続の必要性が高い:長く住み慣れた居住地や、事業を支える拠点で移転が困難な場合、裁判でもその必要性が評価される可能性があります。
- 契約違反など借地人側に非がない:家賃滞納や無断増改築などの契約違反がない場合、貸主の要求は不当とされることがあります。
これらの状況では、立ち退きを拒否しつつ、自らの必要性や契約履行の姿勢を示すことで、交渉を有利に進める土台となります。
3-3 拒否が難しい場面:正当事由が認められやすいケース
一方で、立ち退きを拒否しづらい事例もあります。以下のような場合は、法的にも拒否が困難となる可能性があります:
- 貸主に緊急な自己使用の事情がある:居住や事業上の利用目的で必要性が高いと判断された場合、正当事由と認められることがあります。
- 建物の著しい老朽化など安全上の問題:倒壊の危険性などが認められる場合、立ち退きが認められることがあります。
- 借地人に重大な契約違反がある:地代滞納や無断転貸など、信頼関係が破綻していると判断されれば、立ち退きが認められることがあります。
- 定期借地契約など、更新が前提でない契約形態:期間満了による終了であり、立ち退きの拒否が制限される場合があります。
こうした状況では、単純に拒否するのではなく、補償(立退料)や代替提案を交えた交渉が現実的な選択となることがあります。
3-4 拒否する際に確認すべきポイントと交渉の視点
立ち退きに応じるか否かを判断する前に、以下のポイントを整理しておくことが大切です:
- 通知の理由と形式が明確かどうか(文書か内容証明かなど)
- 契約書の種類(普通借地か定期借地か)と更新の可否
- 自身の居住・事業の継続にかかる実情や移転の困難さ
- 貸主が正当事由を主張できるかどうか(合理性・緊急性の有無)
- 建物の老朽化、安全性に関する状況の把握
- 契約違反がないか、地代支払状況などの確認
これらを整理したうえで、「話し合いを通じて、借地人としての生活基盤と権利を尊重した対応を求める姿勢」を明確にしましょう。強制的な立ち退きではなく、妥当な補償や猶予を得るための交渉を視野に入れることが、最良の対応です。次に交渉のポイントをみていきます。
4.立退料の交渉ポイントと相場の探り方

4-1 立退料には“一律の相場”はない—その背景とは
立退料については、「地代○ヶ月分」や「土地価格の○%」といった一律の基準は存在しません。これは、立ち退きを求める理由(正当事由)の強さや、借地人の事情(高齢・移転負担など)によって、必要となる補償額が大きく変わるためです。
つまり、あなたの状況に応じた「個別判断」が必要であり、交渉過程で柔軟に対応していくことが重要になります。
4-2 算定の基本は「借地権価格×補償割合」+実損の補填
法的な算定の参考として、まず「借地権価格の何割を補償として提示するか」を軸とするケースが多くあります。借地権価格は、更地価格に借地権割合(例:30〜90%)を乗じて算出されます。
一方、補償はこれだけではカバーしきれないこともあります。特に立ち退きによって生じる実際の損失、例えば引っ越し費用や賃料差額などとは、別途話し合いで加味されることが一般的です。
4-3 補償内容の具体例:引っ越し費用、営業損失、建物買取など
以下の補償項目が、立退料に含まれることが多い典型例です:
- 引っ越し費用:現住所から新居への移転にかかる経費
- 営業補償:移転に伴う休業や新規出店までの利益減支の補償
- 賃料差額補償:移転後に賃料が上がる期間(通常1〜3年分)分の調整
- 建物買取請求権の活用:借地人が建てた建物を地主が時価で買い取る権利を行使し、その対価を受け取る
特に建物買取請求権は、法律で借地人に保護された権利であり、立退料とは別に請求できるため重要です。
4-4 交渉を有利に進めるために借地人ができる準備とは
交渉で主導権を握るには、以下を整えておくことが大切です:
- 借地権価格を信頼できる方法で算定し、自らの保有資産として根拠をもつ
- 引っ越し見積もり・営業実績など損失の根拠を用意し、具体的な金額提示につなげる
- 建物買取請求権を行使するかどうか、事前に検討しておく
- 他の判例や交渉事例を把握し、自分のケースとの類似性を整理しておく
- 必要に応じて専門家(弁護士・不動産鑑定士など)に相談し、書面交渉なども用意
立退料は一律では決まらず、「借地権価格」「移転等の実損」「建物買取権」など複数要素を踏まえた個別の算定が必要です。あなた自身の現状と将来の見通しを明確に整理し、根拠ある交渉で納得できる条件を見つけていきましょう。次は、対応の流れを説明していきます。
5.借地特有の注意点:更新時期・再開発・建物買取請求権
5-1 契約更新のタイミングを見逃さないことが大切
借地契約には「契約終了」と「更新」が存在し、あなたがどちらの形で立場を維持するかは重要な選択です。まずは、契約満了のタイミングを正確に把握しましょう。普通借地契約なら、更新請求が可能で、更新料の支払いを伴う合意更新や、更新請求後に地主が異議を述べなければ法定更新となることがあります。
法定更新では、契約条件は基本的に変更されず、新たに更新の意思表示をしなくても契約が続くメリットがあります。ですが、更新を拒否する特約や更新料の取り決めなどが明記されている場合、それに従う必要があることもあり、事前確認が不可欠です。
5-2 再開発が進むとき、借地人はどんな選択肢があるのか
都市計画や再開発によって、自分が住んでいる土地にもその影響が及ぶことがあります。そんなとき、「家を壊されるのでは」「どう対応すればいいか」と不安になる借地人は少なくありません。
再開発の場合、国や自治体の都市計画法に基づく権利保護制度を通じて、立退きや代替住宅の提供、補償などの制度へアクセスできる可能性があります。また、地主との直接交渉で環境や生活・事業継続の必要性を説明し、支援を求める道もあります。まずは、補償制度の内容や周辺事例を事前に確認しておくことが重要です。
5-3 建物買取請求権は、借地人にとって守りの権利
借地契約が期間満了で終了すると、原則として土地を更地に戻す義務がある中、「利便性が高かったのに自分で壊さなければならないの?」という不安もあります。しかし、借地借家法13条により、借地人には「建物買取請求権」が認められています。これは、契約終了後に地主に対し、借地上の建物を時価で買い取らせることができる強力な権利です。
更新を望まない借地人の場合でも、この権利を行使することで、建物を自ら処分する負担から守られる場合もあります。期間満了時に契約が終了となったケースでは特に、建物買取請求権の存在が、借地人の生活や資産を守る最後の砦となります。
5-4 複雑な状況でも、準備と主張の順序を忘れずに
更新時期、再開発、建物買取請求権──複数のテーマにまたがる状況では、ただ不安になり対応が後手に回ることが多くなります。そこで、まずは以下の順序で準備し、冷静に対応できる体制を整えましょう:
- 契約の種類と満了タイミングの確認(普通借地/定期借地)
- 更新の可否・期限・更新料または同意状況の整理
- 再開発の計画や制度、補償内容の事前確認
- 建物買取請求権の活用の可能性と時期(契約終了が近いときの重要な資産保護策)
こうした整備が、いざというときに判断と行動を助け、あなたの生活や資産を守る力となります。
6.対応ステップ:チャートでわかる立ち退き請求時の行動フロー
6-1 通知を受けたらまず何をすべきか?最初の確認項目
立ち退き通知を受け取ったら、まず冷静に以下の点を確認しましょう:
- 通知の形式と内容:文書か口頭か、内容証明郵便かどうかなど。形式によって法的有効性が変わる場合があります。
- 立退きの理由:正当事由が明記されているかどうか(自己使用・再開発など)。
- 契約形態と更新時期:「普通借地契約」「定期借地契約」「更新済か否か」など、契約形態によって対応方法が異なります。
- 立退料の提示の有無:補償があるかどうかは交渉の基盤となります。
まずは状況を整理し、自分の立場と権利を「見える化」することが大切です。必要に応じて、専門家へ初期相談をしてください。
6-2 情報を整理し、「拒否」か「交渉」かを判断する
通知内容と契約状況を整理したうえで、以下の判断を検討しましょう:
- 借地人として立退きを拒否できる可能性がある場合(正当事由がない、あなたの使用が不可欠など)、拒否を検討しましょう。
- 一方で、立退きの合意を選ぶ場合には、立退料や代替措置を交渉する選択肢があります。
- 「拒否」する際も必ず通達や合意内容は文書化し、証拠として残すことが重要です。
法的に守られた権利があるからこそ、感情的にならず、状況に応じた冷静な判断と準備がカギとなります。
6-3 話し合いで進まないときに取るべき行動
交渉が難航する場合は、以下のような次のステップが考えられます:
- 正式な異議申し立てや見解表明書の送付:内容証明郵便で書面を送ることは有効な証拠になります。
- 調停・裁判手続きへの移行:話し合いで合意できない場合、貸主の立場からすると、裁判所での調停申立てまたは明渡請求訴訟の提起が選択肢に出てきます。貸主が調停申立てまたは訴訟提起をする場合、借地人はこれに対応をする必要が出てきます。
これらの手続きにつき、検討ないし対応する場合は、時間や手間がかかることもあるため、早めに専門家と相談し、戦略的判断を進めましょう。
6-4 最終的には「合意か裁判か?」—出口を見据えた判断
最終的には、以下の2つの見通しで判断を整理することが重要です:
- 合意による円満解決:立退料や代替案などを条件に合意し、書面化した形で確定するのが理想的な出口です。
- 裁判による終局的解決:合意が難しい場合には、裁判所の判断を仰ぐことになります。ただし、期間・費用・精神的負担も伴うため、主張や立証を尽くしたうえで裁判所の判断を求める必要があります。
どちらの選択をする場合でも、状況を正確に把握し、書面または専門家を通じて合意内容や手続きを確認しておくことが、納得できる解決の前提となります。
7.借地の立ち退き請求で「相談すべき」弁護士に依頼するメリット

7-1 “ひとりで悩む負担”から解放される心の支え
突然届いた「立ち退き請求」に直面すると、多くの借地人は「どうすればいいのか…」と頭が真っ白になります。書類の形式に不安がある、人と直接話すのが苦しい、ストレスで日常生活にも影響が…そんなとき、頼れる専門家がそばにいるだけで、心はずいぶん軽くなります。弁護士が「次に何をすべきか」という道筋を示してくれること自体が、精神的な救いになるのです。実際、交渉の負担を軽減し安心をもたらすことが、弁護士依頼の大きな利点として強調されています。
7-2 法的に「正当事由」を冷静に見極め、交渉の主導権を握る
借地人が立ち退きを強いられるか否かの分岐点は、「貸主の主張に正当事由(正当な理由)があるのかどうか」です。法律知識のないまま判断を誤ると、交渉の土台そのものが崩れてしまいかねません。しかし、弁護士であれば「正当事由の強弱」を法的な視点で的確に判断し、交渉方針を整理してくれます。これにより、有利な交渉を展開できる可能性がグッと高まります。
7-3 立退料だけでなく、あなたの事情に応じた包括的条件交渉
立退料は、あくまで交渉材料の一部にすぎません。例えば、引越し時期の調整、敷金の返還、残置物の処理など、「立ち退きに伴う細かい条件」をまとめて調整することも必要です。これらを見落とすと、後で後悔することになりかねません。弁護士なら、交渉項目を包括的に整理し、あなたの事情に沿ったバランスのよい条件交渉をサポートしてくれます。
7-4 話し合いが難航しても安心、調停・裁判まで任せられる
交渉が思うように進まず「話にならない」という局面も、残念ながら起こりうることです。そのとき、専門家がいれば、調停や裁判など法的手続きへの橋渡しがスムーズに進みます。答弁書、準備書面の作成、証拠による立証を含めて、あなたの声をしっかり伝える代理人として行動してくれることは、大きな安心材料となります。
弁護士に相談・依頼することは、以下のような安心と強さをあなたにもたらします:
- 精神的負担を軽減し、冷静な判断へと導く
- 法的視点に基づく交渉で主導権を握り、有利な結果を引き寄せる
- 立退料以外の条件まで整理可能な包括対応ができる
- 話がこじれても法的手段に安心して対応できる環境を整えられる
借地人としてのあなたの生活や財産を守るために、最初の一歩として“相談する安心”を選んでください。
8.よくある質問(FAQ)
Q1.「古くなった建物で取り壊しを理由に立退きを求められた…立退料は出るの?」
A1.老朽化が単に「古い」という理由だけでは、法的に正当事由として認められることは少なく、貸主はそれだけで立ち退きを強制できません。ただし、借地借家法では、老朽化による危険性(倒壊の危険・衛生問題など)がある場合には正当事由の補完要素となり得ます。また、「立退料」が無いと正当事由が認められないケースも多いため、老朽化が理由だったとしても、立退料を請求できる可能性があります。具体的な相場や判断基準については、事案により異なるため、専門家と判断することが重要です。
Q2.「再開発のために立ち退きになったとき、交渉する方法は?」
A2.再開発を理由にした立ち退きは、「再開発の需要性」が正当事由として認められる条件かどうかがまず鍵となります。例えば、具体的なプランや他の借地人もすでに立ち退いているなど、必要性が明確に認められる場合、正当事由は認められやすくなります。その上で、十分な立退料や代替居住地の提供などの条件を交渉できます。交渉が難航する場合には、書面で請求することや専門家による支援が効果的です。
Q3.「契約更新前の時期に請求が来たらどうなる?」
A3.普通借地契約では、貸主が更新を拒絶するには「正当事由」と適切な通知が必要です。また、更新が成立しないと、契約終了により借地権は消滅し、立ち退き請求が可能になります。更新の有無や通知時期によって権利関係が大きく変わるため、契約書を確認し、更新の可否や期限・通知の有無を整理する必要があります。
Q4.「借地で自宅を構えている場合、他人事じゃない…相談は早い方がいい?」
A4.はい、非常に重要なご判断です。自宅が対象である場合、立ち退きによる精神的・生活的ダメージが大きくなります。そのため、早い段階で専門家(弁護士)に相談し、正当事由の有無や補償の妥当性、交渉の方針などを整理しておくことが、後の流れを有利に進める鍵となります。
9.まとめ:借地立ち退き請求への備えと早めの相談の大切さ
9-1 まず必要なステップは冷静な事実整理
立ち退き通知を受けたあなたが最初にすべきことは、感情を切り離して「事実関係を整理すること」です。具体的には、通知の形式(口頭か書面か、内容証明かどうか)、立ち退きの根拠(老朽化か再開発か、その他法的な正当理由はあるかなど)、契約形態(普通借地or定期借地)、更新の有無、契約内容と更新状況を再確認してください。
借地借家法によって建物所有目的の土地賃貸借の借地人には保護措置があり、立ち退き請求には正当事由が必要で、立退料がその補完となり得る仕組みです。冷静な事実整理は、あなたの立場を守る第一歩となります。9-2 あなたの事情が判断基準になることを忘れずに
法的な判断では、あなた自身の事情も大切な要素です。たとえば、「自宅として生活の拠点になっている」「高齢や病気で移転が困難」といった借地人独自の実情が、正当事由を否定させる判断材料として重視されることがあります。あなたの事情は、条件交渉の「根拠」となり得ます。交渉に向けて、生活実態・事業継続の必要性・移転の負担などを記録や資料にまとめておくことが重要です。
9-3 立ち退き料だけでなく、生活再建への視点を持つ
立ち退き料はあくまで補償項目の一部にすぎません。移転にともなう引っ越し費用、賃料差額、事業損失、敷金の返還、残置物処理など、あなたの生活再建に直結する費用や条件すべてが含めて検討されるべきです。また、建物買取請求権という特有の権利を活用し、建物を売却して補償とする選択肢もあります。これらを包括的に整理し、交渉材料として整備することが交渉成功のカギです。
9-4 迷ったらすぐに専門家へ—早期相談が得をする選択
最後に、最も重要なポイントは「なるべく早く弁護士に相談すること」です。専門家が関与すれば、契約書や通知書の法的解釈、正当事由の評価、補償交渉、合意文書の作成、必要に応じた法的手続きまで、適切に対応できます。弁護士を通すことで、交渉はよりスムーズで安心なものになるばかりか、法的リスクの軽減にもつながります。
このページの監修弁護士
弁護士
三上 陽平(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)
中央大学法学部、及び東京大学法科大学院卒。
2014年弁護士登録。
都内の法律事務所を経て、2015年にライズ綜合法律事務所へ入所。
多くの民事事件解決実績を持つ。第一東京弁護士会所属。