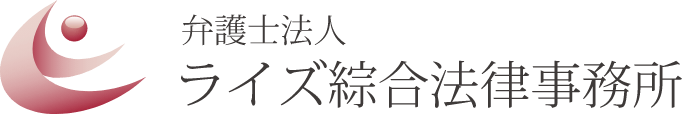1. アパート取り壊しによる立ち退き請求の正当性とは?

アパートの取り壊しを理由に大家から立ち退きを求められた場合、借主としてはその要請が法的に正当なものかどうかを確認することが重要です。日本の法律では、大家が一方的に借主を退去させることはできず、「正当事由」が必要とされています。
1-1 正当事由の必要性と借地借家法の概要
借地借家法第28条では、建物の賃貸人が契約の更新を拒絶したり、解約の申入れをする際には、「正当の事由」がある場合でなければならないと定められています。この「正当の事由」とは、以下の要素を総合的に考慮して判断されます。
- 建物の賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情
- 建物の賃貸借に関する従前の経過
- 建物の利用状況
- 建物の現況
- 建物の明渡しの条件として財産上の給付(立退料など)をする旨の申出
これらの要素を総合的に考慮し、正当事由があると認められる場合に限り、大家は借主に対して立ち退きを求めることができます。
1-2 建物の老朽化や再開発計画などの事由
アパートの取り壊しを理由とする立ち退き要請では、以下のような事由が正当事由として考慮されます。
- 建物の老朽化:築年数が経過し、耐震性や安全性に問題がある場合、建物の取り壊しが必要とされることがあります。ただし、単なる老朽化だけでは正当事由と認められない場合もあり、具体的な危険性や修繕の困難性が求められます。
- 再開発計画:地域の再開発や土地の有効活用を目的とした建て替え計画がある場合、正当事由として認められる可能性があります。ただし、借主の居住権とのバランスを考慮し、立退料の提示などが必要となることがあります。
これらの事由がある場合でも、借主の居住年数や生活状況、建物の使用状況などを総合的に考慮し、正当事由が認められるかどうかが判断されます
アパートの取り壊しによる立ち退き要請に対しては、大家が「正当事由」を有しているかどうかを確認することが重要です。次に、立退料の具体的な相場やその内訳について詳しく説明していきます。
2. 立退料の相場と内訳
アパートの取り壊しを理由に大家から立ち退きを求められた場合、借主としては立退料の相場や内訳を理解しておくことが重要です。
2-1 立退料の相場
居住用物件の立退料の相場は、一般的に家賃の6〜12ヶ月分とされています。例えば、月額家賃が10万円の場合、60万円〜120万円程度が目安となります。ただし、これはあくまで目安であり、実際の金額は立ち退きの理由や借主の事情によって変動します。
2-2 立退料の内訳
立退料には、以下のような費用が含まれることが一般的です。
①転居費用
引越しに伴う費用には、以下の項目が含まれます。
- 引越し業者への依頼費用
- 梱包資材の費用
- 不用品の処分費用
- 新居への移動費
これらの費用は、部屋の広さや荷物の量、移動距離などによって異なります。例えば、1LDKの部屋から同じ市内への引越しの場合、10万円〜20万円程度が相場とされています。
②新居の契約費用
新しい住居を契約する際には、以下のような初期費用が発生します。
- 敷金・礼金
- 仲介手数料
- 保証料
- 火災保険や地震保険の加入費用
- 電話・インターネットなどの設備契約費用
これらの費用は、物件の家賃や地域によって異なりますが、家賃の3〜6ヶ月分が目安とされています。
③家賃差額の補填
現在の住居と新居の家賃に差がある場合、その差額を一定期間分補填することがあります。例えば、現在の家賃が8万円、新居の家賃が10万円の場合、差額は2万円です。この差額を1年分補填する場合、24万円が立退料に加算されます。
立退料の内訳や金額は、個々の事情によって異なります。適切な補償を受けるためには、事前に費用の見積もりを行い、大家との交渉を進めることが重要です。次に、実際の交渉で注意すべきポイントを詳しく解説します。
3. 立ち退き交渉の進め方と注意点

アパートの取り壊しを理由に大家から立ち退きを求められた場合、借主としては冷静かつ戦略的に対応することが求められます。交渉を円滑に進めるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
3-1 交渉内容の記録を徹底する
立ち退き交渉では、口頭でのやり取りだけでなく、書面やメールなどでの記録を残すことが重要です。交渉内容や合意事項を明確に文書化することで、後々のトラブルを防ぐことができます。また、交渉の際には、録音やメモを取るなどして、詳細な記録を残すことをおすすめします。
交渉内容を記録する際のポイントは以下の通りです。
- 日時と場所:交渉が行われた日時と場所を明確に記録します。
- 参加者:交渉に参加した全員の氏名と役職を記録します。
- 議題と内容:交渉で話し合われた議題とその内容を詳細に記録します。
- 合意事項:合意に至った事項については、具体的な内容と合意日を明記します。
これらの記録は、万が一のトラブル時に証拠として活用できるため、交渉の各段階で徹底的に行うことが重要です。
3-2 専門家への相談の重要性
立ち退き交渉は、法律や契約に関わる複雑な問題を含むため、専門的な知識が求められます。弁護士に相談することで、法的な観点からのアドバイスを受けることができ、自身の権利を適切に主張することが可能になります。
弁護士に相談するメリットは以下の通りです。
- 法的アドバイスの提供:立ち退き交渉に関する法律や判例に基づいたアドバイスを受けることができます。
- 交渉の代理:弁護士が交渉の代理人として対応することで、感情的な対立を避け、円滑な交渉が可能になります。
- 書類の作成と確認:合意書や契約書などの法的文書の作成や内容確認を行ってもらえます。
- トラブル時の対応:交渉が決裂した場合や訴訟に発展した場合でも、適切な対応をサポートしてもらえます。
特に、交渉が難航する場合や、相手方が法的手段を取る可能性がある場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。続いて、実際の裁判例を通じて立ち退き請求の判断基準を深掘りしてみましょう。
4. 実際の裁判例から学ぶ立ち退きのポイント

アパートの取り壊しを理由とした立ち退き請求において、裁判所が「正当事由」を認めるか否かは、個別の事情を総合的に判断して決定されます。以下に、取り壊しが正当事由と認められた事例と認められなかった事例を紹介します。
4-1 正当事由が認められた事例
事例1:築38年以上のアパートの老朽化による立ち退き
- 判決日:2020年3月31日
- 裁判所名:東京地方裁判所
- 事件番号:平成30年(ワ)第39647号
- 概要:築38年以上が経過したアパートの老朽化により、賃貸人が建物の取り壊しを決定。賃借人に立ち退きを求めたが、賃借人が応じなかったため、賃貸人が、明け渡しを請求。裁判所は、建物が耐震強度不足にあることを認め、他方、賃貸人が長期にわたり賃借を継続して居住をしたこと、賃借人が高齢で要介護の状態にあり、建物から退去には相当の困難を伴うことを考慮し、立退料400万円の支払いをもって正当事由を認め、建物明渡請求を認めた。
事例2:耐震性の欠如による取り壊しと立ち退き
- 判決日:2016年3月8日
- 裁判所名:東京地方裁判所
- 事件番号:平成26年(ワ)第22436号
- 概要:築50年を超える建物の耐震性に問題があり、賃貸人側が取り壊しを決定。賃借人に立ち退きを求めたが、賃借人が拒否。賃貸人側が立退料100万円を提示し、明け渡しを請求。裁判所は、建物が大地震動によって倒壊する可能性が高いこと、大地震動によって一応倒壊しない程度に耐震改修工事をするためには1194万円程度の費用を要すること、賃貸人には同改修工事費用を負担する能力はなかったことを認定し、賃借人の引っ越しに伴う不利益は立退料によって補うことが可能であるとして、賃貸人が100万円の立退料を提供していることを考慮して、賃貸人側の解約申入れに正当事由があると認めて、建物明渡請求を認めた。
4-2 正当事由が認められなかった事例
事例3:建物の老朽化を理由とした立ち退き請求
- 判決日:2018年2月21日
- 裁判所名:東京地方裁判所
- 事件番号:平成28年(ワ)第23134号
- 概要:建40年が経過した建物につき、老朽化による建物倒壊または大破壊の危機があり、賃貸人が建物の建て替えの必要があるとして、賃借人に立ち退きを求めた。賃借人は、建物に居住目的で賃借し、また、賃貸人の承諾を得た上で仕事上の事務所としても使用し、さらに、持病の治療や検査のために近くの病院に通院するために、建物を使用する必要性が高いと主張。裁判所は、建物については、賃借人の自己使用の必要性が極めて高いのに対し、賃貸人の自己使用の必要性がほとんどないこと、建物の現況としては、近い将来に倒壊する危険性があることをうかがわせる徴候はなく、差し迫った建て替えの必要性までは認められないことを考慮し、立退料120万円の提供があるとしても、正当事由を補完するに足りないと判断し、建物明渡請求を棄却した。
これらの事例から、取り壊しによる立ち退き請求が正当事由と認められるか否かは、建物の老朽化や耐震性、賃貸人・賃借人の事情、立退料の額などを総合的に判断して決定されることがわかります。
5. 立退料の内訳と具体的な金額例
5-1 立退料の内訳
アパートの取り壊しを理由に大家から立ち退きを求められた場合、借主としては立退料の内訳と相場を理解しておくことが重要です。立退料は、借主が転居する際に必要となる費用や損失を補償するためのものであり、以下のような項目が含まれます。
①引っ越し費用
引っ越し業者への依頼費用や梱包資材の費用、不要品の処分費用などが含まれます。これらの費用は、部屋の広さや荷物の量、移動距離などによって異なりますが、一般的には10万円〜20万円程度が相場とされています。
②新居の契約費用
新しい住居を契約する際には、敷金・礼金、仲介手数料、保証料、火災保険料などの初期費用が発生します。これらの費用は、物件の家賃や地域によって異なりますが、家賃の3〜6ヶ月分が目安とされています。
③家賃差額の補填
現在の住居と新居の家賃に差がある場合、その差額を一定期間分補填することがあります。例えば、現在の家賃が8万円、新居の家賃が10万円の場合、差額は2万円です。この差額を1年分補填する場合、24万円が立退料に加算されます。
④借家権の補償
借家権(借地権)にも経済的価値があるとして、立退料の算定の基礎にしたり含めたりする考え方もあります。借家権価格として算定された金額が直ちに立退料になるわけではありませんが、裁判所が立退料を決定する際の参考となることがあります。
5-2 具体的な金額例
以下は、家賃10万円の物件において移転先の物件の賃料は家賃13万であると想定する場合の立退料の一例です。
- 引っ越し費用:15万円
- 新居の契約費用:30万円(家賃の3ヶ月分)
- 家賃差額の補填:36万円(差額3万円×12ヶ月)
- 借家権の補償:30万円(家賃の3ヶ月分)
合計:111万円
このように、立退料の内訳や金額は、個々の事情によって異なります。適切な補償を受けるためには、事前に費用の見積もりを行い、大家との交渉を進めることが重要です。最後に、これまでの内容をまとめてポイントを整理します。
まとめ
アパートの取り壊しを理由に大家から立ち退きを求められた場合、借主としては以下のポイントを押さえて対応することが重要です。
①正当事由の確認
大家が立ち退きを求めるには、借地借家法に基づく「正当事由」が必要です。単なる建物の老朽化や取り壊し計画だけでは正当事由と認められない場合があります。借主は、大家の主張する理由が法的に正当とされるかを確認し、必要に応じて専門家に相談しましょう。
②立退料の内訳と相場
立退料は、以下のような項目で構成されます。
- 引っ越し費用:10万〜20万円程度
- 新居の契約費用:家賃の3〜6ヶ月分
- 家賃差額の補填:1〜3年分の差額家賃
- 借家権の補償:物件や地域により異なる
これらを合計すると、一般的な住居用物件では100万〜200万円程度が相場とされています。ただし、具体的な金額は個別の事情によって大きく異なります。
③交渉の進め方と注意点
- 記録の保持:交渉内容は書面で記録し、トラブル防止に努めましょう。
- 専門家への相談:弁護士などの専門家に相談することで、適切な対応が可能になります。
- 裁判例の参考:過去の判例を参考にすることで、交渉の方向性を定めやすくなります。
立ち退き交渉は、法的知識と慎重な対応が求められます。不安がある場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
このページの監修弁護士
弁護士
三上 陽平(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)
中央大学法学部、及び東京大学法科大学院卒。
2014年弁護士登録。
都内の法律事務所を経て、2015年にライズ綜合法律事務所へ入所。
多くの民事事件解決実績を持つ。第一東京弁護士会所属。