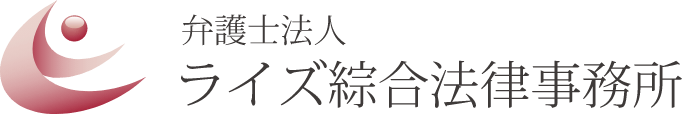1.老朽化による立ち退きの正当性とは?

建物の老朽化を理由に大家から立ち退きを求められた場合、その要請が法的に正当と認められるかどうかは、借地借家法の「正当事由」の有無にかかっています。以下では、老朽化が正当事由として認められるための要件や、具体的な判断基準について解説します。
1-1 単なる老朽化では正当事由とならないケース
築年数が経過していること自体は、必ずしも立ち退きの正当事由とはなりません。例えば、築50年以上の建物であっても、適切な維持管理が行われており、安全性や居住性に問題がない場合、老朽化を理由とした立ち退き要請は正当事由として認められない可能性があります。裁判所は、建物の状態や賃借人の居住状況などを総合的に判断し、正当事由の有無を決定します。
1-2 居住に危険が及ぶ程度の老朽化が必要
一方で、建物の老朽化が進行し、居住者の安全に重大な影響を及ぼす場合には、正当事由として認められる可能性が高まります。例えば、耐震診断の結果、建物が倒壊の危険性が高いと判定された場合や、雨漏りや設備の故障が頻発し、修繕が困難な状態にある場合などが該当します。このような場合、大家は建物の安全性確保のために立ち退きを求めることが正当とされることがあります。次に、立ち退き料の相場と交渉におけるポイントを詳しく説明します。
2.立ち退き料の相場と交渉ポイント
建物の老朽化を理由に立ち退きを求められた場合、借主としては適切な立ち退き料を受け取ることが重要です。立ち退き料は、引越し費用や新居の契約費用、精神的な負担への補償などを含むものであり、交渉によって金額が決定されます。
2-1 立ち退き料の相場
立ち退き料の金額は法律で明確に定められているわけではなく、建物の種類や立地、契約内容、立ち退きの理由など、さまざまな要素を考慮して個別に決定されます。一般的な相場としては、以下のような目安があります。
- アパート・マンションなどの賃貸住宅:月額賃料の6ヶ月〜10ヶ月分
- 戸建て賃貸住宅:月額賃料の12ヶ月〜24ヶ月分
例えば、月額家賃が10万円のアパートであれば、立ち退き料の相場は60万円〜100万円程度となります。ただし、これはあくまで目安であり、実際の金額は個別の事情によって異なります。
2-2 交渉のポイント
立ち退き料の交渉においては、以下のポイントを押さえることが重要です。
① 移転にかかる費用を具体的に算出する
引越し費用、新居の敷金・礼金、仲介手数料、家具・家電の買い替え費用など、移転に伴う具体的な費用を算出し、貸主に提示することで、立ち退き料の妥当性を主張できます。
② 貸主の立ち退き理由の正当性を確認する
借地借家法では、貸主が契約の更新を拒絶したり、立ち退きを求めたりする場合、「正当事由」が必要です。この正当事由が十分でない場合、借主には強い交渉権があり、立ち退き料を増額させる余地が生まれます。
③ 交渉の記録を残す
交渉の過程では、口頭でのやり取りだけでなく、書面やメールなどでの記録を残すことが重要です。交渉内容や合意事項を明確に文書化することで、後々のトラブルを防ぐことができます。
④ 専門家への相談
立ち退き交渉は、法律や契約に関わる複雑な問題を含むため、専門的な知識が求められます。弁護士に相談することで、法的な観点からのアドバイスを受けることができ、自身の権利を適切に主張することが可能になります。それでは、交渉の際に特に意識すべき具体的なポイントについて解説します。
3.立ち退き交渉の進め方と注意点
老朽化を理由とした立ち退き要請に直面した際、借主としては冷静かつ戦略的に対応することが求められます。交渉を円滑に進めるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
3-1 交渉内容の記録を徹底する
立ち退き交渉では、口頭でのやり取りだけでなく、書面やメールなどでの記録を残すことが重要です。交渉内容や合意事項を明確に文書化することで、後々のトラブルを防ぐことができます。また、交渉の際には、録音やメモを取るなどして、詳細な記録を残すことをおすすめします。
交渉内容を記録する際のポイントは以下の通りです。
- 日時と場所:交渉が行われた日時と場所を明確に記録します。
- 参加者:交渉に参加した全員の氏名と役職を記録します。
- 議題と内容:交渉で話し合われた議題とその内容を詳細に記録します。
- 合意事項:合意に至った事項については、具体的な内容と合意日を明記します。
これらの記録は、万が一のトラブル時に証拠として活用できるため、交渉の各段階で徹底的に行うことが重要です。
3-2 弁護士への相談の重要性
立ち退き交渉は、法律や契約に関わる複雑な問題を含むため、専門的な知識が求められます。弁護士に相談することで、法的な観点からのアドバイスを受けることができ、自身の権利を適切に主張することが可能になります。
弁護士に相談するメリットは以下の通りです。
- 法的アドバイスの提供:立ち退き交渉に関する法律や判例に基づいたアドバイスを受けることができます。
- 交渉の代理:弁護士が交渉の代理人として対応することで、感情的な対立を避け、円滑な交渉が可能になります。
- 書類の作成と確認:合意書や契約書などの法的文書の作成や内容確認を行ってもらえます。
- トラブル時の対応:交渉が決裂した場合や訴訟に発展した場合でも、適切な対応をサポートしてもらえます。
特に、交渉が難航する場合や、相手方が法的手段を取る可能性がある場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。相手方が立退料を提供しようとしない場合もあります。
次章では実際の裁判例を取り上げ、具体的な判断基準を確認しましょう。加えて、実際の裁判例を参考に、立ち退きが認められる基準を掘り下げていきます。
4. 実際の裁判例から学ぶ立ち退きのポイント

建物の老朽化を理由とした立ち退き請求において、裁判所が正当事由を認めるか否かは、建物の状態や賃借人の居住状況、立退料の提示など、さまざまな要素を総合的に判断して決定されます。以下に、老朽化を理由とした立ち退き請求が認められた事例と認められなかった事例を紹介し、それぞれのポイントを解説します。
4-1 老朽化が正当事由と認められた事例
ある裁判例では、築95年以上経過し、耐震性や耐火性に問題がある木造建物において、賃貸人が解約の申入れをして、賃借人に立ち退きを求めた事案において、裁判所は、建物の建替えの必要性と高齢である賃借人の従来の日常生活及び通院治療を継続する必要性とを衡量した上で、立退料215万円が提供されることによって正当事由が具備されると判断しました。
□判決日:平成25年(2013年)12月11日
□裁判所:東京地方裁判所
□事件番号:平成25年(レ)第697号
□概要:
築95年以上が経過し、国土交通省が発表した「地震時に著しく危険な密集市街地」に所在している木造建物において、賃貸人が解約の申入れを行いました。
裁判所は、建築士の診断結果や区役所の危機管理担当部長の文書による要望等を踏まえ、建物が耐震性の点で危険性を否定できず、耐火性も欠いていると認定し、賃貸人の建替えについて相当の合理性があると評価しました。他方、賃借人も高齢で年金以外に収入がないことを踏まえると、転居による生活環境の変化から受ける心理的・肉体的負担は通常の場合よりも大きいものと推察でき、賃借人が建物で居住する必要性も相当高いと評価しました。
その上で、賃貸人と賃借人の双方の必要性を比較し、賃貸人の必要性の方が高いと認めるべきではあるものの、賃借人に生じる不利益も看過できないことから立退料の提供によって正当事由が具備されると判断しました。
そして、立退料の検討に入り、賃借人が家財を搬出して退去する費用相当額、新たな賃貸物件等住居を確保するために要する費用相当額、相当期間について当該物件の賃料と賃借人が従前に支払っていた賃料との差額相当分を考慮すべきであるとし、立退料を215万円とするのが相当としました。
この事例では、建物の老朽化が進行し、耐震性に問題があることが専門家の診断によって明らかになっており、安全性確保の観点から立ち退きの必要性が認められました。また、賃貸人が立退料を提示し、賃借人の移転に伴う負担を補償しようとした点も、正当事由の補完要素として評価されました。
4-2 老朽化が正当事由と認められなかった事例
一方で、築年数が経過していること建物につき立ち退きを求めた事例のなかには、裁判所が正当事由を認めなかったケースもあります。例えば、建物の老朽化が進んでいるものの、具体的な安全性の問題や修繕の困難性が立証されていない場合、単なる築年数の経過だけでは正当事由とは認められません。
□判決日:令和2年(2020年)3月13日
□裁判所:東京地方裁判所
□事件番号:平成30年(ワ)第33300号、平成31年(ワ)第6915号
□概要:
築約50年の建物について、賃貸人が賃貸借の解約申入れをして、300万円の立退料の提供をすると申し出て、立ち退きを求めましたが、裁判所は、建物の壁のひび割れや漏水跡、鉄部の発錆は見られず、目視で分かるような傾斜も見られず、また、建物の耐震性能の検証も出来ておらず、証拠上、地震等により建物が倒壊する危険があると認められないと、判断をしました。裁判所は、賃貸借が元々は親族関係にある者に対する扶助として開始したことを認定しつつ、賃借人が長期間にわたり生活の本拠として使用してきたことを勘案して、賃借人の賃貸借継続に対する期待を保護する必要性は高いと判断して、賃貸人の解約申入れに正当事由があるとはいえないとしました。
4-3 裁判例から学ぶポイント
これらの裁判例から、老朽化を理由とした立ち退き請求において正当事由が認められるためには、以下のポイントが重要であることがわかります。
- 建物の具体的な老朽化の程度:耐震診断や専門家の意見など、客観的な資料をもとに建物の安全性に問題があることを立証する必要があります。
- 賃借人の居住状況:長期間居住している場合や、高齢者など移転が困難な事情がある場合、賃借人の保護が重視されます。
- 立退料の提示:賃借人の移転に伴う負担を補償するため、適切な立退料を提示し、正当事由を補完することが求められます。
老朽化を理由とした立ち退き請求を行う際は、これらのポイントを踏まえ、慎重に対応することが重要です。また、賃借人としては、立ち退き要請を受けた場合、建物の状態や自身の居住状況を確認し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。こうしたケースを踏まえつつ、次章では正当事由を補強するために、実際に支払われる「立ち退き料」の相場や構成要素についてご紹介します。
5. 立退料の内訳と具体的な金額例
立退料は、借主が退去する際に発生するさまざまな費用や損失を補填するためのものです。具体的な内訳と金額例を以下に示します。
5-1. 転居費用
引越しに伴う費用には、以下のような項目が含まれます。
- 引越し業者への依頼費用
- 梱包資材の費用
- 新居への移動費
- 家財の運搬にかかる保険料
- 不用品の処分費用
これらの費用は、部屋の広さや荷物の量、移動距離などによって異なります。例えば、1LDKの部屋から同じ市内への引越しの場合、10万円〜20万円程度が相場とされています。
5-2. 新居の契約費用
新しい住居を契約する際には、以下のような初期費用が発生します。
- 敷金・礼金
- 仲介手数料
- 保証料
- 火災保険や地震保険の加入費用
- 電話・インターネットなどの設備契約費用
これらの費用は、物件の家賃や地域によって異なりますが、家賃の3〜6ヶ月分が目安とされています。
5-3. 家賃差額
現在の住居と新居の家賃に差がある場合、その差額を一定期間分補填することがあります。例えば、現在の家賃が8万円、新居の家賃が10万円の場合、差額は2万円です。この差額を1年分補填する場合、24万円が立ち退き料に加算されます。
5-4. 営業補償(店舗・事務所の場合)
店舗や事務所の立ち退きでは、営業の中断や移転に伴う損失を補償するための営業補償が必要となります。具体的には、以下のような項目が含まれます。
- 休業期間中の売上損失
- 従業員の給与
- 移転費用
- 新店舗の内装工事費用
- 得意先を失うことによる損失
これらの費用は、事業の規模や業種によって大きく異なります。例えば、飲食店の移転では、数百万円から1,000万円以上の営業補償が認められるケースもあります。 最後に、本コラム全体の要点を整理し、立ち退き要請への対応策を振り返ります。
まとめ:老朽化による立ち退き要請に冷静かつ適切に対応するために
建物の老朽化を理由とした立ち退き要請に対しては、以下のポイントを押さえて対応することが重要です。
1. 正当事由の有無を確認する
老朽化が立ち退きの正当事由となるかは、建物の状態や安全性、修繕の困難性などを総合的に判断する必要があります。単なる築年数の経過だけでは正当事由と認められない場合もあります。
2. 立ち退き料の内訳と相場を理解する
立ち退き料には、引越し費用、新居の契約費用、家賃差額などが含まれます。一般的には家賃の6〜12ヶ月分が目安とされていますが、個別の事情により増減します。
3. 交渉内容の記録を徹底する
交渉の過程では、日時、場所、参加者、議題、合意事項などを詳細に記録することが重要です。書面やメールでの記録を残すことで、後のトラブルを防ぐことができます。
4. 専門家への相談を検討する
立ち退き交渉は法的な知識が求められるため、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。弁護士は、法的アドバイスの提供、交渉の代理、書類の作成・確認、トラブル時の対応など、さまざまな面でサポートしてくれます。
5. 裁判例を参考にする
過去の裁判例を参考にすることで、立ち退き要請の正当性や立退料の相場を把握することができます。ただし、個別の事情により判断が異なるため、専門家の意見を仰ぐことが重要です。
老朽化による立ち退き要請に直面した際は、冷静に対応し、自身の権利を守るための行動を取ることが求められます。適切な情報収集と専門家の助言を得ることで、納得のいく解決策を見つけることができるでしょう。
このページの監修弁護士
弁護士
三上 陽平(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)
中央大学法学部、及び東京大学法科大学院卒。
2014年弁護士登録。
都内の法律事務所を経て、2015年にライズ綜合法律事務所へ入所。
多くの民事事件解決実績を持つ。第一東京弁護士会所属。