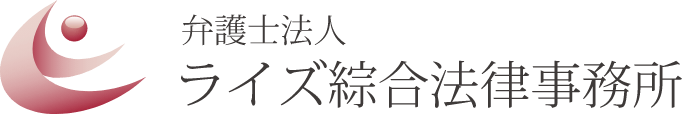1.大家都合による立ち退きとは?正当事由の必要性と借地借家法の概要
建物の賃貸物件において、大家(賃貸人)から「立ち退いてほしい」と求められた場合、入居者(賃借人)は必ず応じなければならないのでしょうか?実際には、大家の一方的な都合のみでは退去を強制することはできず、「正当事由」の存在が必要です。本コラムでは、借地借家法における正当事由の考え方とともに、立ち退き料の相場や支払いの有無、交渉方法、過去の裁判例をもとに、入居者がとるべき対応策について詳しく解説します。
まずは、借地借家法における正当事由の考え方について詳しく見ていきます。
1-1 借地借家法による入居者の保護
日本の借地借家法は、賃貸借契約における入居者の地位を保護することを目的としています。特に、大家からの一方的な契約解約や更新拒絶を制限し、入居者の安定した居住を確保するための規定が設けられています。この法律により、大家が契約の解約や更新拒絶を行うには、「正当事由」が必要とされています。
1-2 正当事由とは何か
借地借家法第28条では、大家が契約の解約や更新拒絶を行うには、「正当事由」が必要であると規定されています。この「正当事由」とは、単に大家の都合だけではなく、以下のような要素を総合的に考慮して判断されます。
- 物件の使用を必要とする事情:大家自身やその家族が物件を使用する必要性がある場合。
- 貸借契約の経緯:契約の締結や更新の経緯、期間、条件など。
- 物件の利用状況:入居者が契約に違反していないか、適切に物件を使用しているか。
- 物件の現況:建物の老朽化や損傷の程度。
- 財産上の給付(立ち退き料)の申出:大家が入居者に対して立ち退き料を支払う意思があるか。
これらの要素を総合的に判断し、正当事由があると認められた場合に限り、大家は契約の解約や更新拒絶を行うことができます。
1-3 立ち退き料の役割
立ち退き料は、大家が入居者に対して退去を求める際に支払う金銭であり、正当事由の補完要素として考慮されます。正当事由が弱い場合でも、相当額の立ち退き料を支払うことで、契約解約や更新拒絶が認められる可能性があります。一般的に、立ち退き料の相場は家賃の6ヶ月から12ヶ月分とされていますが、具体的な金額はケースバイケースで異なります。
1-4 入居者の対応策
大家から立ち退きを求められた場合、入居者は以下の点に注意して対応することが重要です。
- 正当事由の有無を確認する:大家の主張する理由が正当事由に該当するかを確認しましょう。
- 立ち退き料の提示があるかを確認する:立ち退き料の支払いがあるか、金額が妥当かを検討しましょう。
- 専門家に相談する:弁護士などの専門家に相談し、適切な対応策を講じることが望ましいです。
正当事由が十分であれば、立ち退きが法的に認められる可能性があります。一方で、事由が弱い場合は、大家からの立ち退き料の支払いが条件になることもあります。
さらに、正当事由を補完する手段として、実際に支払われる立ち退き料についても押さえておく必要があります。
2. 立ち退き料の相場と交渉ポイント

大家都合による立ち退き要請において、立ち退き料の提示は入居者との交渉を円滑に進めるための重要な要素です。しかし、立ち退き料の金額には法的な規定がなく、具体的な相場や交渉のポイントを理解することが求められます。
2-1 立ち退き料の相場:家賃の6〜12ヶ月分が目安
立ち退き料の金額は、物件の種類や立ち退き理由、地域の慣習などによって異なりますが、一般的な目安としては家賃の6〜12ヶ月分とされています。例えば、月額家賃が10万円の場合、60万円から120万円程度が相場となります。この金額には、引っ越し費用や新居の契約費用、家賃差額、慰謝料などが含まれます。
ただし、これはあくまで目安であり、実際の金額は個別の事情によって大きく変動します。そのため、具体的な立ち退き料の金額を決定する際には、専門家の意見を参考にすることが重要です。
2-2 正当事由の強度による立ち退き料の変動
立ち退き料の金額は、大家が主張する「正当事由」の強度によっても変動します。正当事由が強い場合、例えば建物の老朽化や再開発計画など、立ち退きの必要性が高いと認められる場合には、立ち退き料は比較的低く抑えられる傾向にあります。
一方、正当事由が弱い場合、例えば大家の個人的な事情や収益性の向上を目的とした立ち退き要請など、入居者にとって納得しにくい理由である場合には、立ち退き料を高めに設定することで、交渉を円滑に進めることが求められます。このように、正当事由の強度と立ち退き料の金額は密接に関連しており、適切なバランスを取ることが重要です。
2-3 交渉を円滑に進めるためのポイント
立ち退き交渉を円滑に進めるためには、以下のポイントに留意することが有効です。
- 誠意ある対応:入居者に対して誠実な態度で接し、立ち退きの理由や必要性を丁寧に説明することが信頼関係の構築につながります。
- 適切な立ち退き料の提示:入居者の負担を考慮した適切な立ち退き料を提示することで、納得を得やすくなります。
- 代替物件の提案:可能であれば、入居者に対して代替となる物件を提案することで、安心感を提供できます。
- 専門家への相談:立ち退き交渉に不安がある場合や複雑な事情がある場合には、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
これらのポイントを踏まえて交渉を進めることで、入居者との合意形成がスムーズに進み、トラブルの回避につながります。なお、具体的な金額は物件の条件や地域慣習、正当事由の強度によって変動します。
ところが、中には立ち退き料が支払われないケースもありますので、次章でその具体例を見ていきましょう。
3. 立ち退き料が支払われないケースとは?
大家都合による立ち退き要請において、通常は立ち退き料の支払いが求められますが、特定の条件下では支払われないケースも存在します。以下では、立ち退き料が支払われない主なケースについて解説します。
3-1 定期借家契約の期間満了
定期借家契約は、契約期間が満了すると自動的に終了する契約形態です。この契約では、期間満了に伴う退去は事前に合意されているため、原則として立ち退き料は支払われません。ただし、契約期間中に大家から中途解約と期間満了前の立ち退きを求められた場合など、特別な事情がある場合には、立ち退き料が発生する可能性もあります。
3-2 賃借人の契約違反
賃借人が契約違反をした場合、例えば家賃の長期滞納や無断での転貸、特約で禁止されているペットの飼育などが該当します。このような場合、大家は契約を解除し、立ち退きを求めることができます。契約違反による退去は賃借人の責任であるため、立ち退き料は支払われないのが一般的です。
3-3 大家の自己使用による立ち退き
大家が自身やその家族の居住を目的として物件を使用する場合、正当事由として立ち退きを求めることができます。この場合、立ち退き料の支払いが必要であるかが争いとなりえますが、賃借人の生活への影響を考慮し、交渉の中で支払われることもあります。
3-4 立ち退き料請求を禁止する特約がある場合
賃貸借契約書に立ち退き料の請求を禁止する特約が含まれている場合、原則としてその特約は無効とされます。借地借家法では、賃借人に不利な特約は無効とされるため、立ち退き料の請求を禁止する特約があっても、賃借人は立ち退き料を請求する権利があります。
3-5 賃借人がほとんど居住していない場合
賃借人が物件にほとんど居住していない場合、例えば長期間空き家状態である場合など、大家は正当事由として立ち退きを求めることができます。このような場合、立ち退き料が支払われないこともあります。
このような事例を踏まえつつ、実際の立ち退き交渉を円滑に進めるためのポイントを次章でご紹介します。
4. 立ち退き交渉の進め方と注意点
大家都合による立ち退き要請を受けた場合、入居者としては自身の権利を守りつつ、円滑に交渉を進めることが求められます。ここでは、立ち退き交渉を進める際の基本的な手順と注意点について解説します。
4-1 立ち退き要請の内容を確認する
まず、大家からの立ち退き要請の内容を正確に把握することが重要です。立ち退きの理由、期限、提示されている立ち退き料などを確認し、賃貸借契約書や関連する書類と照らし合わせて、要請が正当なものであるかを判断します。
4-2 交渉内容の記録を徹底する
交渉の過程では、口頭でのやり取りだけでなく、書面やメールなどでの記録を残すことが重要です。交渉内容や合意事項を明確に文書化することで、後々のトラブルを防ぐことができます。また、交渉の際には、録音やメモを取るなどして、詳細な記録を残すことをおすすめします。
4-3 弁護士への相談の重要性
立ち退き交渉は、法律や契約に関わる複雑な問題を含むため、専門的な知識が求められます。弁護士に相談することで、法的な観点からのアドバイスを受けることができ、自身の権利を適切に主張することが可能になります。また、弁護士が交渉に同席することで、交渉が円滑に進む場合もあります。
4-4 冷静かつ論理的な対応を心がける
立ち退き要請に対して感情的にならず、冷静かつ論理的に対応することが重要です。自身の権利や立場を明確にし、相手の主張にも耳を傾けながら、建設的な話し合いを進めることが望まれます。
4-5 合意内容の確認と契約書の作成
交渉の結果、立ち退きに関する合意に至った場合は、その内容を明確に契約書として文書化します。契約書には、立ち退きの理由、期限、立ち退き料の金額や支払い方法など、合意した事項を詳細に記載し、双方が署名・押印することで、法的な効力を持たせます。
4-6 立ち退き後の対応
立ち退き後も、敷金の返還や原状回復費用の精算など、さまざまな手続きが必要となります。これらの手続きについても、事前に確認し、円滑に進めることが大切です。不明な点がある場合は、弁護士や専門家に相談することをおすすめします。
そして、これらの交渉ポイントは、過去の裁判例を通じても裏付けられています。次章で具体的な事例を見ていきましょう。
5. 実際の裁判例から学ぶ立ち退きのポイント
立ち退き交渉においては、過去の裁判例が重要な参考となります。以下では、立ち退き料が高額に認められた事例や、立退請求が認められなかった事例を紹介し、立ち退き交渉のポイントを解説します。
5-1 高額な立ち退き料が認められた事例
①老朽化したビルの居酒屋に対する立ち退き請求(東京地方裁判所平成30年7月20日 判決)
築年数が経過し老朽化したビルに入居する居酒屋に対し、貸主が建物の建て替えを理由に立ち退きを求めた事例です。裁判所は、借主の営業継続の困難さや移転費用等を考慮し、立ち退き料として1156万1000円の支払いが必要であると判断しました 。
②賃料7万4,000円のアパートに対する立ち退き請求(東京地方裁判所平成29年1月17日 判決)
築44年のアパートに居住する借主に対し、貸主が建物の老朽化を理由に立ち退きを求めた事例です。裁判所は、借主の健康状態や転居の困難さを考慮し、借主に立ち退きを命じつつ、立ち退き料として200万円の支払いと引き換えとなることが必要だと判断しました。
③賃料4万6,750円の木造建物に対する立ち退き請求(東京地方裁判所平成29年5月11日 判決)
築75年が経過した木造建物に居住する借主に対し、貸主が建物の老朽化を理由に立ち退きを求めた事例です。裁判所は、借主の長期居住や立ち退きによる生活環境の変化の影響を考慮し、借主に立ち退きを命じつつ、立ち退き料として360万円の支払いと引き換えとなることが必要だと判断しました。
5-2 立退請求が認められなかった事例
①店舗に対する立ち退き請求が棄却されたケース(東京地方裁判所平成28年7月26日判決)
貸主が借主に対して、営業中の店舗からの立ち退きを求めた事例です。裁判所は、貸主側が主張する事情につき正当事由を認めず、立退請求を棄却しました。
②店舗に対する立ち退き請求が棄却されたケース(東京地方裁判所平成28年9月23日判決 )
貸主が借主に対して、店舗からの立ち退きを求めた事例です。裁判所は、貸主側が主張する事情につき正当事由を認めず、立退請求を棄却しました。
5-3 裁判例から学ぶポイント
- 正当事由の有無:立ち退きを求める際には、貸主の事情だけでなく、借主の生活状況や健康状態なども考慮されます。
- 立ち退き料の算定:立ち退き料は、引っ越し費用や新居の契約費用、営業補償などを含めて算定されます。借主の事情によっては高額になることもあります。
- 交渉の重要性:裁判に至る前に、双方が納得できる形での交渉が望まれます。専門家の助言を受けながら、適切な対応を検討することが重要です。
これらの裁判例から、立ち退き交渉においては、法的な正当事由の有無や借主の事情を総合的に考慮する必要があることがわかります。
6. 立ち退き交渉を円滑に進めるためのポイント

大家都合による立ち退き要請において、入居者との交渉を円滑に進めるためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。ここでは、交渉内容の記録と専門家への相談の重要性について解説します。
6-1 交渉内容の記録を徹底する
立ち退き交渉では、口頭でのやり取りだけでなく、書面やメールなどでの記録を残すことが重要です。交渉内容や合意事項を明確に文書化することで、後々のトラブルを防ぐことができます。また、交渉の際には、録音やメモを取るなどして、詳細な記録を残すことをおすすめします。
交渉内容を記録する際のポイントは以下の通りです。
- 日時と場所:交渉が行われた日時と場所を明確に記録します。
- 参加者:交渉に参加した全員の氏名と役職を記録します。
- 議題と内容:交渉で話し合われた議題とその内容を詳細に記録します。
- 合意事項:合意に至った事項については、具体的な内容と合意日を明記します。
これらの記録は、万が一のトラブル時に証拠として活用できるため、交渉の各段階で徹底的に行うことが重要です。
6-2 専門家への相談の重要性
立ち退き交渉は、法律や契約に関わる複雑な問題を含むため、専門的な知識が求められます。弁護士に相談することで、法的な観点からのアドバイスを受けることができ、自身の権利を適切に主張することが可能になります。
弁護士に相談するメリットは以下の通りです。
- 法的アドバイスの提供:交渉が行われた日時と場所を明確に記録します。
- 交渉の代理:弁護士が交渉の代理人として対応することで、感情的な対立を避け、円滑な交渉が可能になります。
- 書類の作成と確認:合意書や契約書などの法的文書の作成や内容確認を行ってもらえます。
- トラブル時の対応:交渉が決裂した場合や訴訟に発展した場合でも、適切な対応をサポートしてもらえます。
特に、交渉が難航する場合や、相手方が法的手段を取る可能性がある場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。最後に、本コラムの要点を整理します。
まとめ
大家都合による立ち退き要請においては、借地借家法に基づく「正当事由」の有無が重要な判断基準となります。正当事由が認められない場合でも、立ち退き料の支払いによって立ち退きが認められるケースもあります。立ち退き料の相場は、家賃の6〜12ヶ月分が目安とされますが、借主の生活状況や建物の状態など、個別の事情によって増減することがあります。
立ち退き交渉を円滑に進めるためには、以下のポイントが重要です。
- 交渉内容の記録:口頭でのやり取りだけでなく、書面やメールなどでの記録を残すことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
- 専門家への相談:立ち退き交渉は法律や契約に関わる複雑な問題を含むため、弁護士などの専門家に相談することで、法的な観点からのアドバイスを受けることができます。
また、過去の裁判例からも、立ち退き料の算定や立ち退きの可否に関する判断基準を学ぶことができます。例えば、老朽化した建物の建て替えを理由とする立ち退き請求において、借主の生活状況や移転費用等を考慮し、高額な立ち退き料の支払いが命じられた事例があります。
立ち退き交渉は、入居者の生活に大きな影響を及ぼす重要な問題です。適切な手順を踏み、専門家の助言を得ながら、自身の権利を守るための交渉を進めることが求められます。不安や疑問がある場合は、早めに弁護士などの専門家に相談し、適切な対応を図りましょう。
このページの監修弁護士
弁護士
三上 陽平(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)
中央大学法学部、及び東京大学法科大学院卒。
2014年弁護士登録。
都内の法律事務所を経て、2015年にライズ綜合法律事務所へ入所。
多くの民事事件解決実績を持つ。第一東京弁護士会所属。